

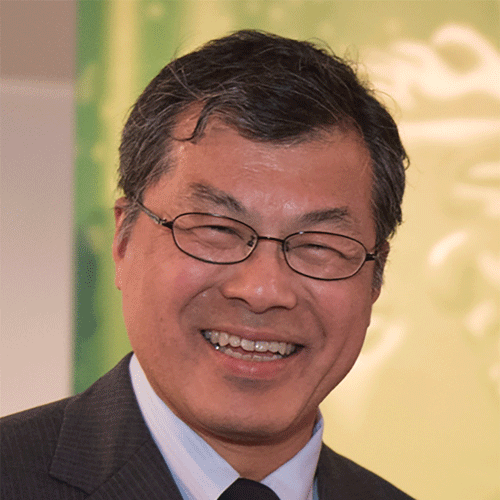
2016年4月の大学改革にともなって科学技術創成研究院を構成する一研究所として改組しました。当研究所は、人類社会の現状と将来を見据えて研究所のミッションを、「分子を基盤とする化学および生命科学に関する基礎から応用までの研究の深化、発展を通じて、新しい学理の創成と次世代科学技術の創出を実現し、人類の高度な文明の進化と、より豊かで持続可能な社会の具現化に貢献する。」と設定しています。多面的に対応できる組織運営を目指して、所内の研究グループを4つの領域(分子創成化学領域・分子組織化学領域・分子機能化学領域・分子生命化学領域)に再編しました。分子科学のみならず生命科学の領域も大きな柱の1つとして、物質・資源・エネルギー・生命を新たな軸として基礎研究を基盤として、豊かな暮らしの実現に向けて活動を続けます。
世界最小サイズの発光酵素picALuc®の開発に成功
創薬スクリーニング・検査・診断のために用いられるレポータータンパク質としての発光酵素には、明るさや熱安定性等の高さに加えて、サイズの小ささが求められる。そこで本研究では、カイアシ類由来発光酵素ALuc®(21 kDa)の発光活性を維持したまま、分子量が13 kDaになるまで小型化することにより、新規発光酵素picALuc®を開発した。これはこれまでに開発されている実用レベルの発光酵素の中で最小のサイズである。またpicALuc®は、高い発光活性をもつ発光酵素NanoLuc®と同等の発光値と熱安定性を示した。さらに、picALuc®を分子間相互作用検出のための汎用法である生物発光共鳴エネルギー移動(BRET)ベースアッセイに用いたところ、NanoLuc®よりも高い応答が観察された。picALuc®は今後、ライフサイエンス分野から創薬スクリーニング・診断・検査までの幅広い分野において、有用なツールとなることが期待される。
最小の三元素合金:金・銀・銅原子からなる三角分子の直接観測に成功
原子間結合の形成や切断によって得られる膨大な化合物の知見は、今日の有機化学や錯体化学、無機化学の基礎になっている。近年、一過性の過渡的にしか生成されない不安定な金属原子の集合体が、触媒反応における真の活性種であると考えられるケースも多く、特に「どのような集合体が一過性に形成されるのか」を知ることは重要であった。しかし、安定して結合する化合物でなければ、その存在を観測し、構造解析することは極めて困難である。
本研究では、グラフェン上にさまざまな金属原子を分散させたサンプルを用意し、原子を観察できる分解能を持つ電子顕微鏡で、結合の様子をリアルタイムに動画観察した。収録した動画を適切に画像処理することで、動く原子ひとつひとつの元素の種類を特定し、観察中に次々と生成していく分子の種類や構造を決定した。
安定的に単離できない、一過性の金属集合体でも準安定構造の観測を可能にした本手法によって、これまで未知であった原子集合体を形成する元素や形成過程の解明が可能になり、触媒の機構解明や新たな設計などにつながることが期待される。
赤色蛍光タンパク質型cGMPセンサーの開発と多色イメージングへの応用
今回開発されたRed cGullは、赤色蛍光タンパク質mAppleを二分割し、その間にcGMP分解酵素(phosphodiesterase 5α, PDE5α)のcGMP結合ドメインを挿入した構造をもつ、蛍光タンパク質センサーです。mAppleとPDE5αの間のリンカーアミノ酸配列を最適化することで、cGMPに対する蛍光応答を調節しました。Red cGullはcGMPに応答して蛍光輝度が約6.7倍上昇します。
Red cGullをヒトやマウスのさまざまな臓器由来の細胞に発現させ、蛍光顕微鏡によるイメージングを行うことで、細胞内のcGMP動態をリアルタイムで可視化解析することに成功しました。また、Ca2+特異的な緑色蛍光色素や、青色光活性型タンパク質と同時に使用することで、2色イメージングや光遺伝学ツールとの併用が可能であることを示しました。
さらに、Red cGullをマウス小腸内分泌細胞株に発現させ、消化管ホルモン分泌時における細胞内cGMP動態について解析した結果、アミノ酸であるL-アルギニンが、一酸化窒素合成酵素を介して小腸内分泌細胞のcGMP産生を促すことを明らかにしました。
生細胞内タンパク質の量と動態を蛍光抗体で観察することに成功
蛍光色素で部位特異的に化学修飾した抗体断片であるクエンチ抗体(Quench body/Q-body)を構築してきた。Q-bodyは、励起光を照射したときの蛍光強度の変化を見ることで、抗原としてさまざまな物質を検出できる。しかしこれまでは、細胞表面にあるバイオマーカータンパク質の簡便な検出は可能だったが、細胞内タンパク質の検出やイメージングには成功していなかった。
今回研究グループでは、がん抑制タンパク質であるp53を細胞内で高い応答で検出できる、安定なQ-Body(Intra Q-body)を構築した。これを細胞内に電気穿孔法を利用して導入することで、固定化細胞のみならず、洗浄が不可能な生細胞内でもガン抑制タンパク質p53[用語5]のリアルタイムイメージングに成功した。
このIntra Q-bodyを用いたシステムでは、抗がん剤投与による生細胞内でのp53量の時間変化を、高い応答と精度で24時間以上にわたり観察できた。さらに、発現量の異なる細胞群の中からp53発現細胞のみをセルソーターで濃縮することにも成功した。
この方法によれば、今後さまざまな細胞内バイオマーカー発現細胞を簡便に検出・単離でき、将来的には効果的な細胞治療につながると期待される。
光が当たると光合成酵素が活性化する分子メカニズム
植物の光合成機能は、光環境の変化に合わせて柔軟かつ精密に調整されており、そのメカニズムの解明は今日の植物生理科学の中心的課題のひとつである。吉田准教授らは、この光合成の制御メカニズムの解明に向けて、光合成反応を支える酵素(タンパク質)の酸化還元制御に注目した。この酸化還元制御システムの情報伝達経路については、半世紀近く前に具体的な経路が提案されていたが、この経路が植物体内で実際に作用していることを示す明確な証拠はなく、植物にとってどれほど重要なのかも明らかにされていなかった。
今回の研究では、ゲノム編集技術CRISPR/Cas9[用語1]を活用して、この情報伝達経路の機能を抑制した変異株植物を作成することで、酸化還元制御システムが光に応答して酵素を活性化させる分子メカニズムを解明した。さらに、この経路を含めた酸化還元制御システムが実際に、植物の光合成や生育に極めて重要な役割を果たしていることを明らかにした。この成果は、農作物の光合成機能や生産性の向上といった今後の応用展開のための重要な指針になると期待される。
臨床検体中のコロナウイルスタンパク質を蛍光抗体で迅速定量することに成功
今回研究グループでは、まず新型コロナウイルスの構成成分のうちスパイク(S1)タンパク質を検出するQ-bodyを開発し、疑似ウイルス粒子の高感度検出に成功した。さらに、ヌクレオカプシド(N)タンパク質の検出においては、反応条件を最適化することで、東京医科歯科大学病院で採取した臨床サンプル中にある新型コロナウイルス検出ならびに感染有無を判定することに成功した。
また、反応液にポリエチレングリコールなどの高分子を適量添加することで、反応を加速し高感度化できることを明らかにした。
この方法を発展させれば、唾液や鼻咽喉ぬぐい液などから目的病原体を簡便迅速に定量検出でき、将来効果的な診断法につながると期待される。
これらの成果は、英国時間9月15日に科学誌「Scientific Reports(サイエンティフィックレポーツ)」、9月30日に英国化学誌「Analyst(アナリスト)」にオンライン掲載され、特に後者はHot Article(注目論文)と掲載号のBack Cover(裏表紙)に選ばれた。
熱電変換性能を左右する分子–電極界面構造を解明
熱電変換は廃熱を電気エネルギーへ変換することが可能であることから環境調和型のエネルギー源として注目されてきた。これまでは無機化合物が熱電変換材料として用いられてきたが、軽量性、安全性の観点から有機化合物への代替に近年注目が集まっている。電極と有機材料の界面構造が熱電変換材料の性能に重要な役割を果たしており、単分子膜の熱電変換材料を調査することでこれを明らかとすることができる。一方、熱電変換材料の性能指数の一つであるゼーベック係数は分子構造に関わらず小さい値に留まっており、分子設計の確立が課題であった。本研究ではこれまで着目されてこなかった電子豊富な有機金属錯体の単分子膜を用いた熱電変換材料を開発した。さらに、金属錯体の数と有機配位子の構造を変えることで劇的にゼーベック係数が増大することを見いだした。本研究により、さらなる有機熱電変換材料の性能向上が見込まれる。
“構造活性相関転移”による低分子医薬品候補の設計
低分子医薬品の開発では、母骨格の構造が異なっていても類似したSARを示すという、SAR転移を可能とする阻害剤の組み合わせが知られている。SAR転移の予測は迅速な構造最適化につながるが、これまでそうした阻害剤の組み合わせは十分に探索されていなかった。
研究グループはMMP-1阻害剤について、大規模な活性データベースを網羅的に検索することで、SAR転移を起こす既存阻害剤を発見した。活性の向上が予測された新規化合物を実際に合成して評価すると、既知化合物よりも3.5倍高いMMP-1阻害活性が得られた。ファーマコフォア[用語5]フィッティングにより結合様式を解析すると、ハロゲン結合の形成が活性の向上に寄与したことが示唆された。
葉緑体ATP合成酵素の酸化還元制御のしくみを解明
光合成を行う葉緑体内の酵素は、自然界で変化する光環境に応じてその活性を調節し、代謝機能を切り替えるのに不可欠な「酸化還元スイッチ」を備えている。中でも、分子モーターとして知られる葉緑体ATP合成酵素は、回転軸になるタンパク質部分に制御スイッチを持っており、このスイッチが回転を制御するしくみは以前から注目されてきた。
研究グループは、この葉緑体ATP合成酵素の制御スイッチのしくみを調べるため、遺伝子改変が容易な緑藻クラミドモナスを用い、遺伝子組み換えによって制御スイッチ部分のさまざまな構造変異体を作出した。具体的には、制御スイッチを構成するアミノ酸配列の部分的な切除・置換を行い、スイッチの動作の詳細を調べた。これまでの研究での構造解析から、このスイッチは大きく2つの構造単位(ドメイン)で構成されていることがわかっていたが、今回の研究により、この2つのドメインがそれぞれ果たす役割と、それによって酵素の活性、すなわち分子モーターの回転を制御するしくみが明らかになった。
この酵素の活性制御の研究では、これまで部分複合体を用いてATP加水分解時の活性変化が調べられていたが、今回の研究では初めて完全な酵素複合体を用いて、ATP合成活性そのものが酸化還元スイッチによって制御されていることを明らかにした。
共同研究拠点事業を通じて、災害やパンデミックなどの緊急事態に迅速に対応し地域の連携と研究教育力の向上と持続に努めている。ホームページに「最新の研究」という欄を設けており、毎月、各研究室の最先端の研究を簡明に解説したWebジャーナルとして、社会に広く公開しています。大学広報を通じて国内外へのプレスリリースや記者セミナーの開催などを行い積極的に優れた成果の発信を行なっている。平成26年度から「研究所フォーラム」のシリーズ開催を企画し、隔年で国内フォーラムと国際フォーラムを開催しています。また、所内、学内、国内外の研究者の講演を行って、国内外の多様な聴衆に対応できる情報発信を行っています。大学祭では研究室公開を行い、一般の見学者に対して演示実験を展示する、あるいは、体験してもらうことによって、最先端の成果を紹介しています。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京医科歯科大学
東京外国語大学
東京工業大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png