

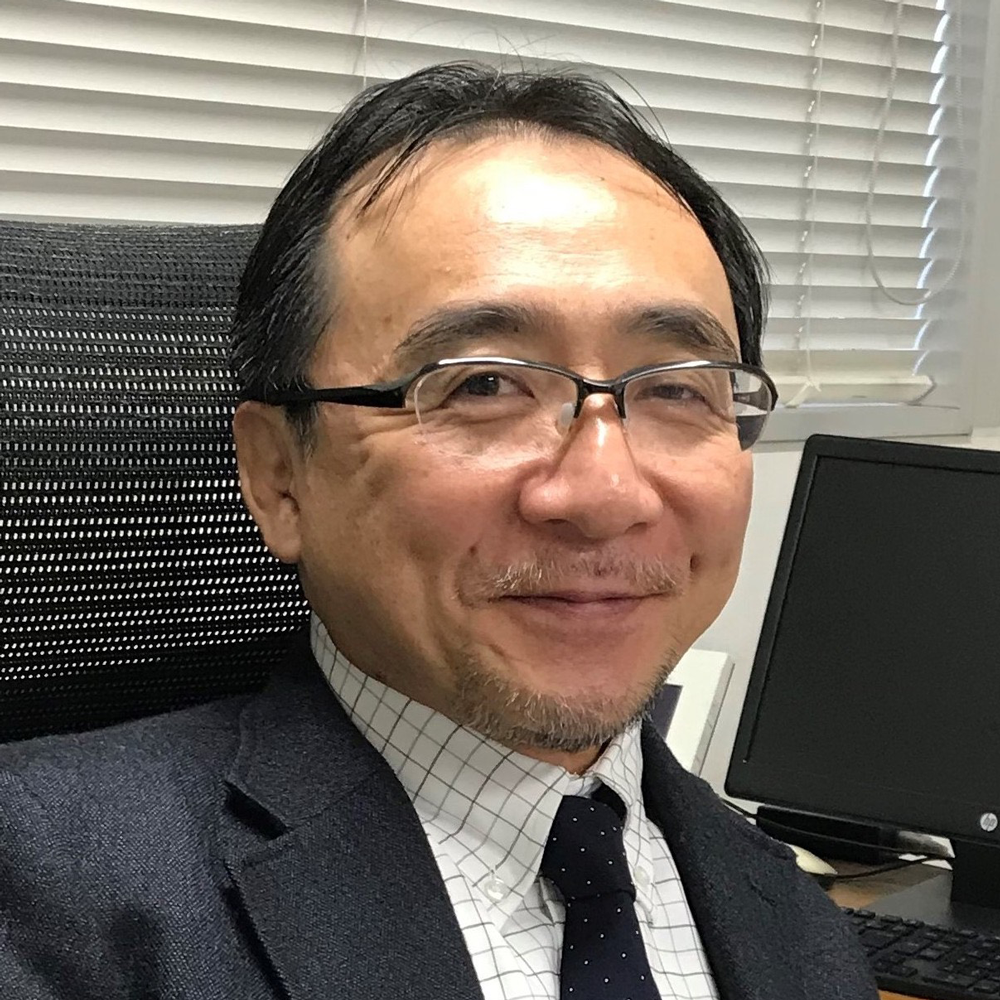
昭和37年に「原爆被爆者の後障害の治療並びに発症予防、及び放射線の人体への影響に関する総合的基礎研究」を目的に設置され、1990年代からチョルノービリ・カザフスタン、2011年からは福島へも活動の場を広げ、平成25年には長崎大学附置研へと改組しました。ミッションを「国内外の大学・研究機関との連携の下、放射線健康リスク管理学を中心とした被ばく医療学を推進し、人類の安全・安心を担う専門家を輩出する」と再定義し、幅広い放射線の影響と障害発生機序解明の研究を展開、被ばく者の国際的調査や医療協力も推進しています。平成28年度からは広島大学原爆放射線医科学研究所、福島県立医科大学ふくしま国際医療科学センターとともに拠点ネットワーク「放射線災害・医科学研究拠点」として共同利用・共同研究拠点に認定され、令和4年度から6年間、第2期拠点事業が開始しました。令和7年度から共同利用・共同研究を発展的に推進するため、放射線・環境健康影響共同研究推進センターを放射線・環境健康影響研究部門としました。その中に甲状腺がん研究センターを新設し、放射線被曝や治療・診断との関連の深い甲状腺結節に関する国内外の医療機関との包括的共同研究を推進します。
医学雑誌の中で最もインパクトファクターが高い雑誌の一つであるLANCETの2024年12月21/28日号において、原研の原爆被爆者医療に関する研究活動が報告されました。被爆者におけるがんや放射線誘発性疾患のリスク評価研究に加え、原研が被爆者の血液、組織、DNA サンプルを包括的に保管する大規模なバイオバンクを立ち上げ、今後の放射線被ばく影響研究の実証的な基盤を構築していることが紹介されました。
皮膚創傷治癒過程において、炎症によって発現誘導される9種類の瘢痕形成関連遺伝子を特定し、中でもItgbl1が痕形成に深く関与していることが明らかとなりました。本研究は、ケロイドや臓器線維化に関連する疾患の新たな治療法開発に繋がると期待されます。
骨髄異形成症候群の世界的分類は2022年にWHO分類第5版、およびInternational Consensus Classification の2つが発表され両者が並立することとなり、そのため世界的に臨床現場での混乱が生じています。これを収拾するために、世界の骨髄異形成症候群研究者が共同で研究データに基づく新たな分類を作成し、原爆後障害医療研究所血液内科学研究分野が日本を代表してこの研究に参画しました。この成果はLancet Haematology誌に掲載されました。
医療従事者の放射線被ばくに関する研究結果を2024年度に4報の論文として発表しました。電離則改正前(2018)年の調査にて、大学病院勤務者に比べて総合病院勤務者の被ばく量がわずかではあるが高いこと(Jpn J Radiol 2024)、大学病院における調査で、2021年の電離則改正前後で被ばく量には変化がないが、被ばく管理に変化が見られること(Health Phys 2024)、全国200を超える病院の調査にて、大規模病院ほど内視鏡部門での被ばく管理に問題が見られること(Jpn J Radiol 2024)、鉛入り防護眼鏡の着用で、透視業務従事者の水晶体被ばくが2/3に低減できること(Health phys 2024;127:712-718.)が明らかとなりました。医療従事者の被ばくを低減するための鍵となる因子が明らかとなり、今後の対策に生かされます。
放射線事故時の被ばく医療の実効性向上を目指し、わが国の原子力災害時の(基幹)高度被ばく医療支援センターとなっている量子科学技術研究開発機構(QST)、弘前大学、福島県立医科大学、福井大学、広島大学及び長崎大学が、令和6年5月に「ヒト末梢血を用いた生物学的線量評価の高度被ばく医療支援センター間連携解析システムの開発」を開始しました。長崎大学原爆後障害医療研究所の研究者も参画し、血液サンプルや分析標本等を互いに送付し合い、輸送条件の最適化、各施設間の線量評価に関する課題の抽出、解析手法の標準化を目標とした生物学的線量評価の体制整備に取り組んでいます。
福島原発事故後、いち早く現場に入り、緊急被ばく医療支援、放射線リスクコミュニケーションに努めてきました。現在の復興期では、福島県立医科大学と放射線教育・研究協力を継続しています。全村避難から帰村宣言をした川内村に拠点を置き、きめ細かな対応で帰村を支援すると共に、富岡町、大熊町、双葉町でも拠点を置いて復興支援を続けています。
1969年から1980年頃にかけて採取された長崎原爆投下による黒い雨等の放射性物質降下地域の土壌について、2020年(令和2年)より参画した厚労省事業により、保管状況の改善とデータベース化を実施し、2022年、医学ミュージアム地階に「原爆土壌試料保管室」として一般公開を開始しました。2024年度においても本事業は継続され、土壌残留放射能の測定、土壌中の溶融金属粒子の検出等の取り組みを行っています。今後も原爆の放射性降下物の実態調査を行った貴重な試料を後世に残すことにより、原爆に関する学生教育への対応、さらに新たな放射性粒子等の研究への寄与が期待されます。
「放射線を正しく怖がる」ことは大切で、住民にきめ細やかな対応をする被ばく医療学を推進するため、社会医学から基礎研究まで広範な研究分野から情報を発信しています。また、福島県立医科大学とともに災害・被ばく医療科学共同専攻大学院を立ちあげ、人材育成に取り組むとともに、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科では博士課程放射線医療科学専攻と先進予防医学共同専攻を担当しています。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png