

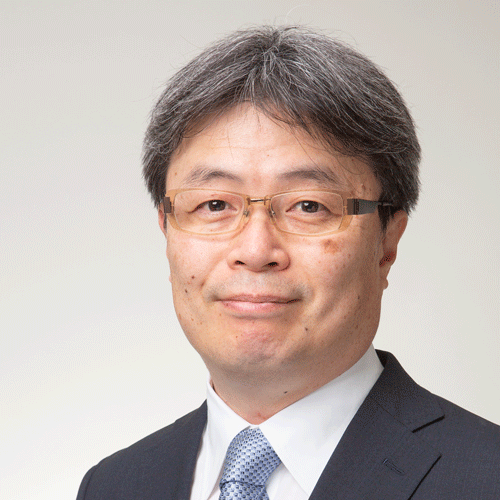
本研究所は、「がんに関する学理及びその応用の研究」を主たる目的として、1967年にがん研究所として設立されました。以来、基礎研究の知見の蓄積と臨床応用を両輪とし、がん研究の先端分野において研究の深化を図るとともに、卓越した研究能力と独創的思考を兼ね備えた人材の育成に努めてきました。特に、「がん幹細胞」と「がん微小環境」に焦点を当てて、転移や薬剤耐性などの悪性形質の制御を目指す研究を進め、その研究成果を臨床へと還元することに取り組んでいます。2011年には、「がんの悪性進展過程」の制御という研究所の使命を明確化するために、「がん進展制御研究所」へと名称を変更しました。さらに2023年からは、共同利用・共同研究システム形成事業「学際領域展開ハブ形成プログラム」による支援を受け、「健康寿命の延伸に向けた集合知プラットフォームの形成」プロジェクトを開始し、学際研究領域「健康寿命科学」の中核的拠点として、研究成果を社会実装につなげる活動を展開しています。
膀胱癌は、加齢と発症・悪性化の関係性が顕著であり、比較的予後の悪い癌とされています。本研究所研究グループは、膀胱組織内に存在するp16陽性老化線維芽細胞が、腫瘍形成後に腫瘍内でがん関連線維芽細胞となって、CXCL12ケモカインを分泌し、膀胱癌の進行を助長することを発見しました(Nat Aging, 4(11), 1582-97, 2024)。また、p16陽性細胞を除去可能な遺伝子改変マウスや老化細胞除去薬を用いた実験により、これらの細胞を除去すると膀胱癌の進行が有意に抑制されることが確認されました。加えて、マウスの老化がん関連線維芽細胞で発現上昇が見られる遺伝子セットは、ヒト膀胱癌の遺伝子発現データと照合すると、病理学的病期分類と同等の予後予測能を示すこともわかりました。本研究は、膀胱癌治療の新たな標的として老化がん関連線維芽細胞の重要性を示し、今後の治療薬開発に新しい可能性を示すものです。
がんは、日本人の死亡原因の第1位であり、国民のおよそ4人に1人がこの疾患により生命を落としています。特に、遠隔臓器への転移や薬剤耐性による再発に代表される「がんの悪性進展」が、患者の生存率の低下と深く関係しています。そのため、これらを制御することが、がん治療における重要な課題として認識されています。本研究所では、悪性進展に焦点を当てた基礎研究の成果を基に、創薬や臨床試験を含むトランスレーショナルリサーチを推進し、研究成果を社会に還元する取り組みを強化しています。さらに、一般市民に最先端の研究内容を紹介する公開講座や高校生を対象とする「がん研究早期体験プログラム」の開催を通して、がんに関する正確な知識の普及と次世代の研究者育成にも力を入れています。今後も、新たな研究シーズの創出や産学連携を通じた社会実装の推進など一連の活動を加速化させ、国民の健康寿命の延伸と福祉の質的向上に貢献したいと考えています。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png