

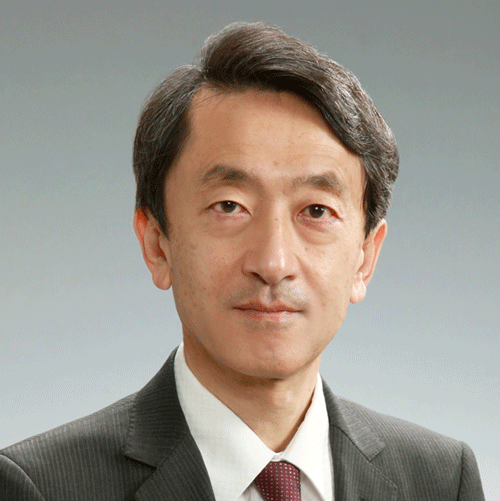
地震研究所は、1925年に設立されて以来、地震・火山現象の科学的解明とそれらに起因する災害軽減の研究を使命としています。プレートの沈み込み帯に位置する日本は、地震・火山活動が世界的に見ても非常に活発な地域です。地震・火山噴火の解明には、その根源としての地球内部ダイナミクスまでを含めた包括的な理解が必要です。私たちは、固体地球科学の諸課題を対象として、観測・実験・理論的アプローチに基づく先端的研究を推進しています。全国の大学や国の研究・行政機関が参画する「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」(令和6年度より第3次)などの大型研究プロジェクトを企画・推進しています。また、海外の大学等と共同で大型観測研究を実施し、外国人研究者の長期・短期招聘を行うなど、国際共同研究を進めています。
2024 年1月1日に、石川県能登地方の深さ約15 km でM7.6の地震が発生しました。地震研究所では、地震に伴う海岸地形や内陸の地表変状の現地調査、被害調査、2020年以来の活発な地震活動と合わせた震源再決定、津波モデリング、海底調査等を実施しました。被害要因を把握することを目的として、建物の被害状況の現地調査を複数回にわたり実施しました。鉄筋コンクリート造柱のせん断破壊、地盤沈下,鉄筋コンクリート造建物の転倒などの被害について、これらの原因を明らかにするための調査研究が進められています(図1)。能登半島北東部では2020年12月から地震活動が活発な状態が続いていましたが、M7.6の地震発生に伴い、地震活動の範囲が大きく広がりました。拡大した活動域は、能登半島の広い領域と北東側の海域を中心とした北東-南西方向に伸びる150km程度の範囲にわたっています。海域に広がった地震活動を精査するために、地震研究所では、全国の大学、研究機関と共同で海底地震計の観測研究をおこない北東側海域下の地震活動を調査しました。観測された地震分布は、能登半島から離れた北東部では北西傾斜、陸寄りでは南東傾斜するように分布しており、観測された地震波形から推定された震源断層モデルと整合的な結果となりました(図2)。今後は陸上での観測データを統合した解析により、より詳細な地震像を明らかにしていく予定です。
地震研究所の研究・教育活動に関する情報をウェブサイト、パンフレット、広報誌等を通じて紹介しています。パンフレットと広報誌はウェブサイトからもダウンロードできます。重要な調査観測や研究成果については、ウェブサイトに掲載するほか、プレスリリースを通じて情報発信しています。また、地震・火山に関する研究活動を紹介するし動画をYouTubeで公開しています。報道関係者からの取材や一般からの問合せへの対応も広報アウトリーチ室が対応しています。地震・火山防災の担当者や報道関係者との日頃からのコミュニケーションに務め、研究の動向等の紹介や意見交換を行う場を設けています。令和6年度は、広報誌で取り上げた記事を深掘りして紹介する「懇談の場」を3回開催し、また地震・火山噴火予知研究協議会との共催で「地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ」を6回開催しました(図1)。
地震・火山に関する研究最前線とその魅力を中高生や一般の方々に広く伝えるため、公開講義や一般公開、施設見学会を開催しています。令和6年度は一般公開のライブ配信等を実施し、自治体や教育機関等の施設見学、研修として約1000名を受け入れました(図2)。国内外で開催される学会において、地震研究所の研究活動を紹介する展示ブースを出展しました。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png