

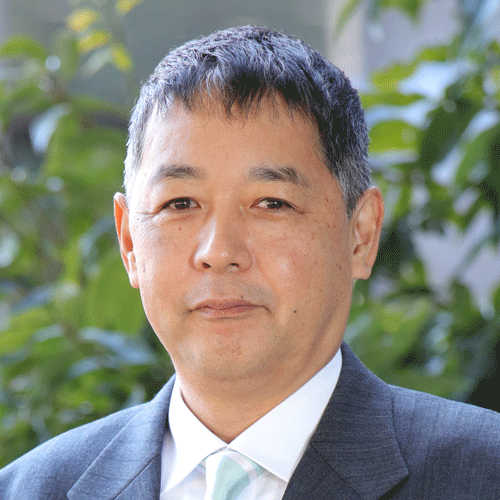
本研究所は、名古屋大学に所属していた3つの研究組織(太陽地球環境研究所、地球水循環研究センター、年代測定総合研究センター)を統合して、2015年10月に創設された附置研究所です。全国でただ一つ、宇宙科学と地球科学を結び付ける国際共同利用・共同研究拠点として活動しています。宇宙地球環境研究所では、地球・太陽・宇宙を一体としたシステムとしてとらえ、そこに生起する多様な現象のメカニズムや相互関係の解明を通して、地球環境問題の解決と宇宙に広がる人類社会の発展に貢献することをミッションに掲げ、室内実験や地上/海洋/人工衛星観測、さらに、これらのデータ解析と理論/モデリングを組み合わせた研究を多角的に展開しています。7つの研究部(総合解析、宇宙線、太陽圏、電磁気圏、気象大気、陸域海洋圏生態、年代測定)からなる基盤研究部門と、融合研究戦略室、超学際ネットワーク形成推進室、国際連携研究センター、統合データサイエンスセンター、飛翔体観測推進センターで構成される体制のもと、全国に附属観測所を配備し、世界の研究機関と学術協定を結んで、国際的な拠点活動を展開しています。
GPSをはじめとする測位衛星(GNSS)から送信された電波は、地球の大気を通過して地上の受信機で受信されます。この特性を利用することで、電離圏における電子密度の積分値である全電子数(TEC:Total Electron Content)を算出することが可能です。しかしながら、TECは積分値であるため、高度ごとの詳細な電子密度分布を把握することができないという限界があります。本研究では、国土地理院が運用するGNSS観測網(GEONET)に加え、民間企業(SoftBank)から提供されたGNSSデータを活用し、新たな三次元トモグラフィー手法を開発しました。その結果、従来の二次元的な観測手法では捉えることが困難であった電離圏擾乱の三次元構造を明らかにすることに成功しました。今後は、本手法を用いることで、さまざまな要因によって引き起こされる電離圏擾乱の三次元構造を統一的に解析することが可能となり、超高層大気研究の新たな展開が期待されます。
論文情報:
Fu, W., Otsuka, Y. & Ssessanga, N. High-resolution 3-D imaging of electron density perturbations using ultra-dense GNSS observation networks in Japan: an example of medium-scale traveling ionospheric disturbances. Earth Planets Space 76, 102 (2024). https://doi.org/10.1186/s40623-024-02051-2
北海道陸別町の陸別小学校と陸別中学校にて、2024年11月29日に出前授業を実施しました。出前授業は、陸別町と名古屋大学・北海道大学・北見工業大学・国立環境研究所・国立極地研究所による陸別町社会連携連絡協議会の活動の一環として毎年開催しているものです。2024年度は名古屋大学宇宙地球環境研究所が小学校5・6年生と中学校2年生の授業を担当しました。陸別小学校では「気候や健康に影響するエアロゾル」をテーマに、大気中の目に見えない微粒子(エアロゾル)の存在や地球環境への影響について、ペットボトルの中でエアロゾルから雲が生成する実験の実演も交えて紹介しました。また、陸別中学校では「地球大気環境の観測的研究を支える“ものづくり技術”」をテーマに、ミリ波・サブミリ波帯という高周波の電波の技術がこの時代にも未開拓であること、そのために電波を用いた大気観測装置は研究者・技術者・メーカー・大学院生が協力して開発し、陸別町を含む世界各地で運用を行っていることを紹介しました。授業後のアンケート等からは、参加した小学生・中学生が宇宙地球環境により深く興味を持つ良い機会となったことが窺えました。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png