

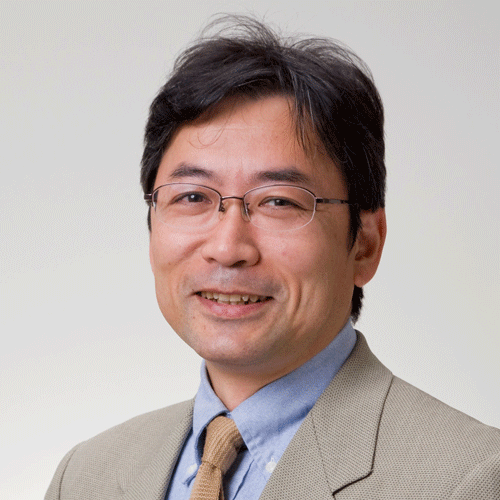
環日本海域から東アジア全域におけるさまざまな環境問題の解決を目指し、2002年に設立された自然計測応用研究センターを2007年に「環日本海域環境研究センター」へ改組し、2研究部門(研究領域部門と連携部門)と4研究領域(大気環境、海洋環境、陸域環境及び統合環境の4領域)で文部科学省の共同利用・共同研究拠点「越境汚染に伴う環境変動に関する国際共同研究拠点」事業を推進しています。共同利用施設として、能登大気観測スーパーサイト、臨海実験施設、低レベル放射能実験施設、尾小屋地下測定室、植物園を有します。
2011年3月の福島原子力発電所事故により海洋環境中に放出されたセシウム-137 (137Cs) は海水循環のトレーサーとして有効である。本研究では、2024年9月JAMSTEC海洋地球調査「みらい」航海に参加、ベーリング海を中心に、137Csの表層分布を調査した。リンモリブデン酸アンモニウム沈殿法により放射性セシウムを海水より分離、地下測定室に設置のゲルマニウム検出器を使用した低バックグラウンドγ線測定法を適用し、137Cs濃度を測定した。2024年のベーリング海および周辺海域における137Cs濃度の水平分布を、図1に示す (本海域のグローバルフォールアウト137Csは0.5mBq/L)。137Csは、ベーリング海東北域で高濃度を示した。これは、事故より13年後、その一部がベーリング海表層に存在することを示唆する。この濃度分布は137Csのみならず、他の汚染物質を含むあらゆる溶存成分の循環パターンの推測にも有効である。
能登半島を中核とした研究フィールドでの成果を国内外に広く発信し、地域社会や国際社会へ国際共同研究拠点が目指す取組みを理解してもらうとともに、地域のステークホルダーとの協働活動体制の構築や地域人材育成を図ることを目的とする公開講座、市民講演会を開催しています。令和6年度には、公開講座「海外学術調査旅ノート2024」と4つの市民講演会を実施しました。また、第71回日本地球化学会年会を金沢大学で実施し、共催で高校生ポスターセッションを開催しました。奥能登2市2町の小中学生を対象に「海と人と生き物と:絵画コンクール」を行い、141枚の応募作品から最優秀賞・優秀賞・特別賞の計16作品を表彰しました(写真参照)。さらに、3件の国際シンポジウム、共同研究成果報告会を開催するとともに、環日本海域環境研究センターの研究活動を紹介する動画をホームページに掲載し、研究活動・成果の発進力強化に努めています。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png