

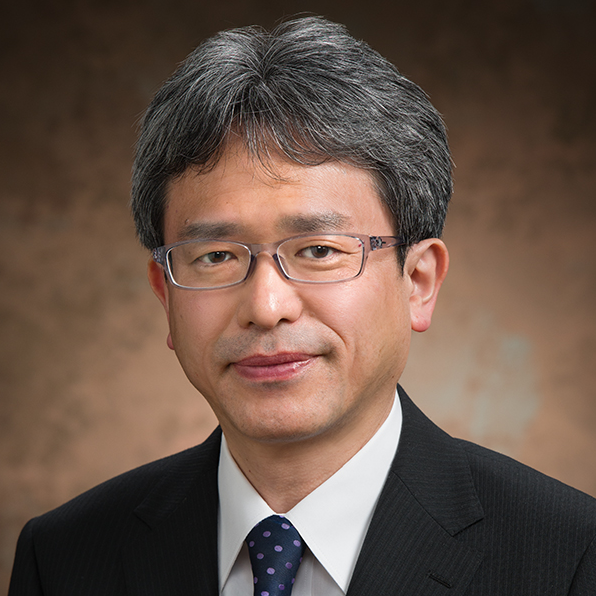
当研究所は、1963年に内分泌研究所として設立され、1994年に生体調節研究所へと改組されました。内分泌・代謝学を中心に、生体を統合的に調節するシステムの分子機構と、その破綻によって起こる疾患の成因・病態生理・治療の研究を行っています。主なテーマは、生体恒常性を司る細胞内シグナル伝達や細胞内物質輸送等の分子機構、膵β細胞や脂肪細胞の機能制御・再生、生体における代謝制御、糖尿病・肥満症をはじめとする生活習慣病の成因・病態生理、そしてゲノム・エピゲノム研究などです。最近では食事や腸内細菌と糖尿病との連関、そしてヒト膵島を対象とした研究なども推進しています。2010年度から内分泌代謝学の共同利用・共同研究拠点に認定されています。
当研究所の個体代謝生理学分野らの研究グループは、過剰なタンパク質摂食を防ぐ仕組みの一端を解明しました。生物は摂取した栄養素を体内で感知し、足りない栄養素を補うように食物を選択することで栄養バランスを保っています。このためには、栄養素のバランスを感知するシステムと、その情報を食物の選択へと出力するシステムの双方が必要であると考えられますが、その仕組みについては不透明でした。今回、研究チームはキイロショウジョウバエの腸内分泌細胞から分泌される腸内分泌ホルモンCCHa1がタンパク質に対する食欲を抑制することを明らかにしました。腸内分泌細胞から分泌されたCCHa1は、腸へと伸びる神経により受け取られ、味覚神経へと情報を伝達することによりタンパク質の過剰な摂取を防ぐことが判明しました。さらに、CCHa1シグナルが正常に機能しないと、キイロショウジョウバエは高タンパク質食を過剰に摂取してしまい、有害なアンモニアを体内に蓄積してしまうことが明らかになりました。本研究成果により、摂食障害や偏食といった疾患に腸内分泌ホルモンが関与する可能性が示唆され、今後腸内分泌ホルモンをターゲットとした治療が期待されます。本研究の成果は、Nature Commun.2024 Dec 30; 15(1)10819. に掲載されました。
当研究所の代謝疾患医科学分野らの研究グループは、組織周囲の微小環境が、体の中でインスリンをつくる膵β(ベータ)細胞を増殖させ、インスリンをふやすために重要なことを明らかにしました。インスリンは体の中で、血糖値を下げることができるただ1つのホルモンです。膵臓の膵島という組織に存在するインスリンをつくりだす膵β細胞の量が少なくなると、インスリンが不足することで血糖値が高くなり、糖尿病の発症につながることがわかっています。
これまで、膵β細胞が周囲の微小環境を構成する細胞外マトリックスと呼ばれる構造成分の1つであるFbln5(フィブリン-ファイブ,Fibulin-5)というタンパク質を分泌することを見出しており、今回、その機能を詳しく調べました。すると、体の中でFbln5がなくなると、インスリンを作り出す膵β細胞が増えにくくなることが明らかになりました。今回発見された、周囲の微小環境を構成するFbln5というタンパク質は、ヒトの膵島においても同様に作られていることが認められました。本研究によって、糖尿病患者さんの体の中では周囲の微小環境が膵β細胞を再生させるためにも大事であることがわかり、インスリンを作り出す新しい糖尿病の治療法開発に貢献すると思われます。本研究の成果は、iScience. 2025 Jan 21;28(2):111856 . に掲載されました。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png