

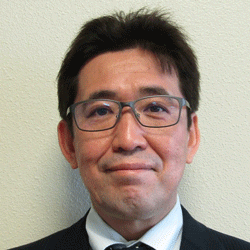
熱帯生物圏研究センターは、沖縄北部・瀬底島に設置される瀬底研究施設、西表島に設置される西表研究施設と沖縄本島中部の琉球大学キャンパス内に設置される分子生命科学研究施設・西原研究施設より構成される、日本最南端の共同利用・共同研究拠点(熱帯生物圏における先端的環境生命科学共同研究拠点)です。本センターでは、琉球列島をはじめとする亜熱帯から熱帯域の多様な生物群を主な対象として、熱帯圏特有の生命現象に関する研究を行っています。研究組織は5つの研究部門と客員研究部門から成り、国内外の研究者との共同研究を行うほか、外部研究者が主体となった研究プロジェクトへの施設・設備の提供も実施しています。また野外での実習や調査のベースなどとしても機能し、大学院生や学部学生の教育にも利用されています。
島嶼多様性生物学部門では、琉球列島のホウライカズラ属植物について核や葉緑体のDNAを用いた分子系統解析を行い、これまで認識されていたリュウキュウホウライカズラに複数の種が含まれることを明らかにしました。サンゴ礁生物科学部門では、浅場から水深40mの深場にサンゴ2種を移植して順応性を調べました。その結果、深場の低水温環境でもサンゴの耐熱性が維持され、さらに弱光環境により白化が抑制されたことから、深場が温暖化の避難地として機能することを明らかにしました。応用生命情報学部門では、沖縄微生物ライブラリーを用いた京都大学との共同研究で、Kitasatospora属放線菌より抗菌活性を示す新奇化合物としてPrecezomycinを見出しました。マングローブ学部門では、国際的な研究ネットワークの中心として、アジア・アフリカ地域の研究機関と共に環境DNAを用いたマングローブ生態系の生物多様性研究を推進しました。また、関連する国内外の研究組織との協力・連携体制を構築しました。感染生物学部門では、腸管出血性大腸菌の病原因子(志賀毒素B鎖)の分子不安定性を克服する技術を開発し、その成果を国際誌に発表しました。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png