

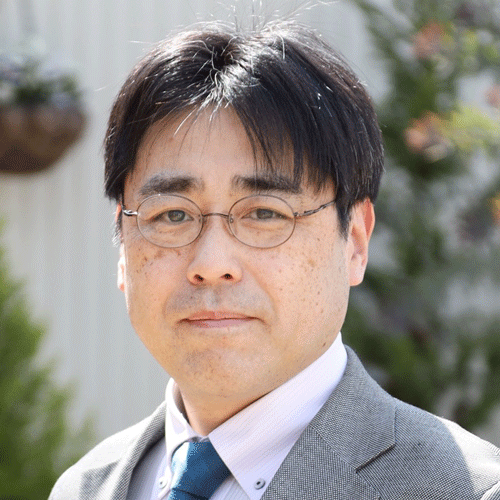
東北大学先端量子ビーム科学研究センターは、電子加速器やサイクロトロンで生成される多様な量子ビーム、非密封放射線源を利用できる実験施設を共用に供し、原子核物理学、放射化学、核医学、核薬学、医工学など幅広い分野で基礎から応用研究まで推進しています。特に電子・光子ビームを活用した未踏領域研究の開拓に取り組むとともに、次世代を担う若手研究者育成(電子光理学研究拠点)にも力を注いでいます。さらに、原子核物理、ハドロン物理、放射性同位元素製造とその応用、コヒーレント光源開発など、電子加速器の特性を活かした独自の研究活動を展開しています。量子ビーム科学の発展と社会への貢献を目指し、国内外との連携も積極的に推進しています。
当センターは、全国共同利用・共同研究拠点として、研究者コミュニティーの活性化を重要な使命と位置づけ活動を続けています。とりわけ若手研究者に発表や議論の場を提供し、人的ネットワークの形成と研究の促進に注力しています。2024(R6)年度は、物理学、医工学、ビーム物理学などの分野から提案された10件の研究会・ワークショップを支援し、学際的な交流の場を提供しました。
本センターが保有する、機能と特徴が異なる複数の大型電子加速器を最大限に活用し、その加速器が生み出す広いエネルギー領域をカバーする電子光ビームを共同利用に供するとともに他研究機関と連携した共同研究を推進しています。
1) クォーク核物理研究部は、大阪大学との連携のもと、SPring-8のLEPS2ビームラインにおけるハドロン物理研究を推進しています。世界最高エネルギー分解能の電磁カロリーメータBGO-eggを用いたη′中間子の光生成実験を通じて、ハドロンの質量獲得機構の解明に貢献しています。また、センター内の1.3GeV電子シンクロトロンを用いたωやη中間子の光生成実験から、中性中間子と核子・原子核との相互作用の研究も進めています。さらに、J-PARCでのK中間子原子核探索実験やINFN-LNFでのK中間子原子脱励起X線測定といった国際共同実験を通じて、K中間子と核子間の相互作用の理解を深めることを目指しています。
2) 同位体科学研究部では、陽子半径の謎に迫るため、史上最低エネルギーとなる60MeV大強度電子リナックを整備し、新型スペクトロメータとビーム輸送系を建設して電子散乱実験を開始しました。2024年度までにデータ取得を終え、現在は解析を進めています。また、理化学研究所と連携し、蓄積リングSCRITを用いた世界初の不安定核への電子散乱実験に取り組んでおり、2023年にはセシウム137での実験に成功しました。さらに、対象核種の拡大に向けた装置の改良も進めています。加えて、大強度電子ビームにより生成される多様な放射性同位元素を学術・産学連携研究に活用しており、近年注目されるセラノスティクスに必要な短寿命RIの製造・分離に関する共同研究も活発化しています。
3)加速器・ビーム物理研究部では、電子線形加速器や1.3GeV電子シンクロトロン(BSTリング)の高度化に加え、試験加速器t-ACTSを用いた超短パルス電子ビームやテラヘルツ領域のコヒーレント放射光発生など、ビーム物理に関する先端的な研究を展開しています。t-ACTSでは、特殊な高周波電子銃と進行波型加速管によって、100フェムト秒以下の超短パルス電子ビームの生成が可能であり、これを用いて多様なコヒーレント放射光源の研究を行っています。永久磁石アンジュレータを使ったコヒーレント・テラヘルツ光の発生では、直線偏光から円偏光・楕円偏光への変換にも成功しました。また、高エネルギー加速器研究機構(KEK)や物質・材料研究機構(NIMS)と連携し、液体ヘリウムを必要としないニオブスズ超伝導高周波空洞の開発も進めており、将来的には汚染水浄化やRI製造などへの応用も視野に入れています。
毎年恒例の「拠点シンポジウム」を2024(R6)年度は3月7日に実施しました。本年も現地・オンライン併用形式で実施、参加者は74名でした。特別講演には、地球惑星科学の土屋卓久教授(愛媛大学)および、素粒子研究への量子計測応用について寺師弘二教授(東京大学)に講演を依頼、当センターのユーザーとの交流を図りました。また、ユーザーによる口頭発表4件、ポスター発表17件が行われ、活発な議論が展開されました。
我々の研究成果の広報活動だけではなく、基礎科学の面白さを積極的に伝えるため、教員が中学や高校に出向き出前授業を実施してきました。また、令和6年度も地元の高校、企業などからの見学者を多く受け入れました。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png