

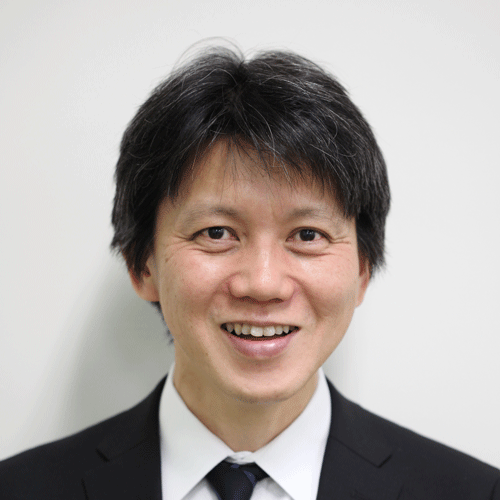
研究所では、「加齢に伴って増加する認知症などの脳加齢疾患および難治がんの克服」を具体的な⽬標として、「加齢制御」、「腫瘍制御」、「脳科学」の三つの研究部⾨、附属施設である環境ストレス⽼化研究センター、医⽤細胞資源センター、⾮臨床試験推進センター、脳MRIセンター、学内共同教育研究施設であるスマート・エイジング学際重点拠点研究センターで研究を推進しています。加齢制御部⾨では、加齢の分⼦メカニズムや、ゲノム損傷修復機構、⽣体防御機構の解明を⾏います。腫瘍制御部⾨では、腫瘍増殖制御のメカニズムを解明しています。脳科学部⾨では、脳の発達と加齢の基礎研究を⾏うとともに、認知症など脳加齢疾患の最先端の診断・治療法の開発を⾏います。以上により、個⼈や社会のスマート・エイジング達成に貢献することを、理念に掲げております。なお研究所は「加齢医学研究拠点」として、全国共同利⽤・共同研究を積極的に推進しています。
東北大学加齢医学研究所は、超高齢社会に対応した老化関連疾患の病態解明を加速するため、2020年度に環境ストレス老化研究センター(CERA)を設置しました。食事や運動といった現実社会の環境要因を反映する老化モデルマウスを開発し、加齢速度を可視化するモデルとして共同利用・共同研究の領域を拡大しています。2024年度には850匹のCERAモデルマウスを飼育し、433匹から脳、肝臓、骨格筋、褐色脂肪組織など臓器別に検体保存を実施しました。そのうち計2446検体を学内7部局および学外13研究機関へ提供し、各種オミクス解析や薬剤効果検証、老化マーカー探索など多彩な共同研究を支援しました。通常の加齢モデルマウス供給事業では、老齢マウスと対照の若齢マウスをセットで提供する仕組みを導入し、2020年度に6件の共同利用・共同研究課題を採択以降、毎年6~8件のプロジェクトに老齢マウスを供給しました。これまでに計503匹を提供し、加齢分子機構解析や予防・治療法開発の基礎データとして活用されています。CERAモデルマウスを活用した研究成果は、Frontiers in Neuroanatomy(2024年)におけるドーパミン神経細胞の老化変化解析や、Journal of Cell Science(2023年)掲載の染色体不安定性発症機構解明など、国際専門誌で論文化されました。これにより神経変性疾患やがん研究に新たな知見を提供し、創薬シーズの創出にも貢献しました。加えてCERAは、世界初かつ最大規模のヒト呼気バンキング事業を展開し、250人分の呼気試料を非侵襲で収集・保管しました。呼気は炎症や代謝状態を反映するユニークな試料として注目され、メタボローム、プロテオーム、トランスクリプトームを含むマルチオミクス解析を実施中です。さらに独自開発の動物呼気採取デバイスにより、ヒト呼気データをモデルマウスで検証し、ヒト・マウス間比較による老化メカニズム解明を可能にしました。これらCERAモデルマウスデータ、呼気オミクスデータ、若齢・老齢マウスの肺線維芽細胞、肝臓、骨格筋、脳など多組織のオミクス解析結果を統合データベースとして公開予定です。これにより研究者は、ブラウズ可能なデータプラットフォームを通じて、データ駆動型の老化研究を加速できます。また高脂肪食負荷マウスや運動負荷マウスを提供し、食事・運動といった環境要因を組み込んだ次世代老化研究を多角的に支援しました。これら一連の取り組みは、国内外の老化研究コミュニティに多大な恩恵をもたらすとともに、加齢医学研究所が老化医学研究の国際的拠点として揺るぎない地位を確立する原動力となっています。
東北大学加齢医学研究所では、RNAをはじめとする核酸の修飾に着目し、老化のメカニズムを分子レベルで解き明かすことを目的とした研究を推進しています。2024年度には、炎症に伴い細胞内に放出されるRNA修飾分子m6A(N6-メチルアデノシン)に結合するA3受容体の立体構造を初めて特定し、その成果を高インパクトの国際学術誌(Nat. Commun. 2024)に発表しました。A3受容体は、炎症や免疫応答に深く関わる分子として知られており、これまで詳細な三次元構造が不明だったため、リガンドであるm6Aとの相互作用がどのように生じているかは大きな謎でした。加齢医学研究所では、先端的な構造解析技術を駆使することで、A3受容体の分子配置やm6Aがどの部位にどのように結合するかを可視化することに成功しました。これにより、m6Aが炎症信号を制御する仕組みや、老化や様々な疾患でみられる細胞機能異常との関連をより正確に理解できるようになりました。さらに、A3受容体を標的とする創薬設計や予防的アプローチが可能となり、加齢関連疾患や炎症性疾患の新たな治療戦略の開拓が期待されます。本研究成果は、老化機構を解明し、社会実装につなげた事例の一つです。今後も、基礎研究から臨床応用までを見据え、研究を総合的に進めていく予定であり、これらの取り組みにより、老化の遅延や加齢関連疾患の克服に貢献し、社会全体の健康寿命延伸を目指します。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png