

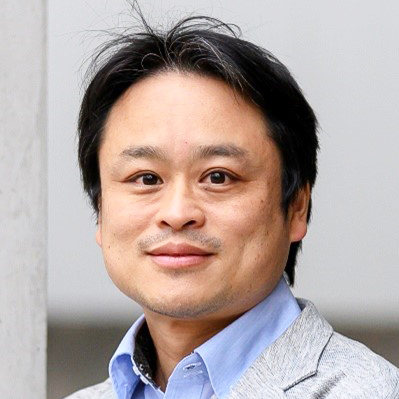
空間情報の汎用的な操作手法と応用研究をするのが空間情報科学です。当センターは、空間情報科学を創成、深化、普及し、合わせて全国の研究者の支援を進めています。空間現象の解析手法を開発し都市現象など人文社会的空間現象や地形・水文など自然的空間現象を分析する空間情報解析研究部門、リアルタイムを含む空間情報の取得から利用に至る過程を一体として研究開発を進める空間情報工学研究部門、社会経済現象を時間と空間を切り口にして理論・実証分析と統計解析手法を開発する空間社会経済研究部門、空間データや空間知識を空間情報基盤として再構築する共同利用・共同研究部門の4部門で構成されています。また学内18部局の連携によるデジタル空間社会連携研究機構の幹事部局として時空間データ解析・応用の新たな学理の構築を行っています。
空間情報科学は本質的に分野融合的学問でありその研究成果も多岐に渡ります。本年度も以下のように多様な研究を展開しました。
国土情報や公共施設等の社会インフラに関するデジタルデータの幅広い流通と、地方創生分野におけるデータ活用を、全国の産官学やシビックテック組織の約30団体と連携し「アーバンデータチャレンジ」を2014年度から連続開催しています。コロナ禍においてもデジタル環境をうまく用いてオンラインイベントを開催し、2024年度まで120~250件程度の応募作品があります。
また、都市の三次元のデジタルツイン環境の構築に関する取組も自治体と進めており、デジタルシティサービスとして、全国の自治体のデジタルツイン環境の公開を行いました。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png