

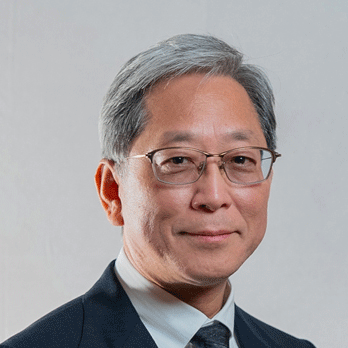
大気海洋研究所は、地球表層を覆う海洋と大気の構造や変動メカニズム、および海洋に生きる生物に関する様々な基礎的研究を推進するとともに、地球環境の変動や生命の進化、海洋生物群集の変動など、人類と生命圏の存続にとって重要な課題の解決につながる研究を展開しています。また、大気海洋科学に係わる全国の研究者のための共同利用・共同研究拠点として、本所(柏キャンパス)と附属国際・地域連携研究センター地域連携研究部門大槌研究拠点(岩手県大槌町︓2022年度に国際沿岸海洋研究センターから改組、以下大槌沿岸センター)において世界最先端の研究施設・機器、充実した研究環境を提供するとともに、海洋研究開発機構の所有する2隻の学術研究船「白鳳丸」と「新青丸」および深海潜水調査船支援母船「よこすか」を用いた共同利用・共同研究を企画・運営し、世界の大気海洋科学を先導することを目指しています。さらには、大学院教育や様々なプロジェクト研究の推進などを通じて、次世代の大気海洋科学を担う若手研究者の育成にも力を入れています。
東京大学大気海洋研究所、海洋研究開発機構、富山大学、九州大学、東京大学地震研究所、金沢大学、新潟大学、神戸大学、高知大学、琉球大学、中央大学、鳴門教育大学、産業技術総合研究所からなる研究チームは、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を踏まえ、令和6年3月4日より学術研究船「白鳳丸」(写真1)を用いた共同利用研究航海を実施しました。
本共同利用研究航海に先立ち、学術研究船「白鳳丸」を用いた緊急調査航海が令和6年1月(第一次)および2月(第二次)に実施され、海底地震計等の設置、回収等によって、今回の地震を起こした震源断層の同定や地震・津波の発生メカニズムの調査が行われました。第三次にあたる本共同利用研究航海の目的は、A)令和6年能登半島地震発生域の高分解能構造探査(マルチチャンネル反射法地震探査)を実施し、今回の地震に関連する深部流体の上昇を調べ、今後の長期的にみた地震発生ポテンシャルを把握すること、B)地震発生域周辺の採水・採泥調査・熱流量計測、地震に伴う海底面変形の深海カメラ撮影、乱泥流観測機器の設置を実施し、地震・津波による海洋環境や海洋生態系への影響を調査すること、です。
長期的な地震発生ポテンシャルと海洋生態系への影響の把握に向けて
学術研究船「白鳳丸」は、全国の大学・研究機関のための共同利用船として研究航海を実施しており、30名を越す研究者が同時に乗船し、研究できる全国で唯一の学術研究船です。本共同利用研究航海も、全国の研究機関を対象とした公募を行い、全国の研究者から組織される委員会の審査のもと、応募された研究課題から実施研究課題を採択し、実施するボトムアップ型の研究航海です。第一次、第二次の緊急調査航海では、震源断層の同定を行うため緊急性が特に高い海域における地震観測・地形調査等を緊急措置として実施しました。さらに、長期的には、今回の地震に関連する海底活断層や深部流体の挙動を調査し、能登半島周辺を含む日本海東縁地震発生帯の地震・津波発生ポテンシャルを把握する必要があります。また、地震・津波の海洋環境や海洋生態系への影響を早急に把握し、今後対策を講じる根拠となる科学的情報を収集する必要があり、幅広い科学的見地からの調査が必要となります。このため、第三次緊急調査航海では、緊急公募を行い、ボトムアップ型の学術研究船「白鳳丸」の共同利用による調査を実施することとなりました。本研究航海で得られるデータを詳しく分析することで、長期的な地震発生ポテンシャルと地震・津波が沿岸域の海洋環境や海洋生態系に与えた影響が明らかになることが期待されます。
東京大学大気海洋研究所の渡辺泰士特任研究員(研究当時)・阿部彩子教授らによる研究グループは、気候モデルを用いた大規模な数値シミュレーションにより、現代との違いが特に顕著である約160-120万年前の氷期・間氷期サイクルをコンピュータ上で再現する事に成功しました。
地球の軌道や自転軸の方向は一定ではなく、長い時間では変化します。そして、それらの天文学的要因により地球の気候は変動します。具体的には、地上における日射量およびその季節変化幅などが変化し、それが大気や海洋、氷床の状態に影響するのです。こうした諸因は気候に対する「天文学的外力」と呼ばれますが、それに対して地球の気候、とりわけ氷床は敏感に反応し、拡大と縮小を繰り返します(氷期・間氷期サイクル)。こうした現象については長い研究の歴史がありますが、昨今の観測的証拠の精細化や理論モデル、数値モデルの発展により大きな進展が見られつつあります。
研究グループは、約80万年前より古い時代(更新世前期)の氷期・間氷期サイクルが持つ周期性が現代の周期性と大きく異なる事に注目しました。そして気候モデルを用いた大規模な数値シミュレーションにより、現代との違いが特に顕著な約160-120万年前の氷期・間氷期サイクルに対して天文学的外力がどのような影響を与えているのかの解明を試みました。その結果、更新世前期の氷期・間氷期サイクルをコンピュータ上で再現する事に成功しました。シミュレーションからは、天文学的外力が従来の認識よりもはるかに精妙に地球の気候に影響を与え、現代との差異を生んでいることも分かりました。将来、この方向の研究が進む事で、地球の気候に関する天文学的外力の役割や氷床と気候変動の仕組みが更によく理解され、地球の歴史や未来の変化をよりよく把握できることが期待されます。
この研究の成果は2023年5月15日付で国際学術誌 Communications Earth & Environment に掲載されました。
東京大学大気海洋研究所の伊藤進一教授、兵藤晋教授らを中心とする研究チームは、自ら開発したマイワシ、カタクチイワシ、マサバ、ゴマサバなど青魚と呼ばれる小型浮魚類から海水中に放出されたDNA(環境DNA)を定量分析するqPCR法(Wong et al., 2022)を利用して、黒潮周辺海域における小型浮魚類の分布を調査しました。この結果得られた小型浮魚類の分布と、水温などの環境データとを比較し、小型浮魚類の分布特性を明らかにしました。
魚類は周囲の水温によって体温が変化する外温動物であるため、一般的に水温に強く依存した分布を示すことが知られています。本研究の解析結果でも、マイワシ、カタクチイワシは水温に強く依存した分布を示しました。これに対し、マサバ、ゴマサバなどのさば類は、水温よりもカタクチイワシに強く依存した分布を示すことが明らかにされました。マサバ、ゴマサバは成長とともに魚食性が増し、カタクチイワシを主餌料としていることから、さば類は餌料が得られる海域に分布を集中させることが推察されました。
本研究では、環境DNAを用いて広域の魚類分布特性を調べ、魚食性魚類が餌料魚の分布に依存していることを明示した初めての研究となります。地球温暖化影響下での魚食性魚類の分布予測を行う際に、餌料となる魚類の分布変化も加味することで予測精度が向上することが期待されています。
東京大学大気海洋研究所と九州大学応用力学研究所の研究チームは、日本海の洋上を通過する台風によって発生する海洋内部を伝搬する波(内部波)に関する全深度での観測を成功させた。これまでの研究では、海洋内部への台風の影響は、主に台風が通過した海域を中心に、台風の通過直後の数日間にのみその影響が現れると考えられてきた。しかしながら、今回の観測から、台風が通過して1週間以上が経過しても内部波のエネルギーは減衰せず、むしろ中・深層において最大値を示すほど活発である事実が明らかになった。この結果を受けて、漁業資源や海洋インフラなどへの内部波の影響に関して、既存の概念を更新し、より長い時間スケールで対策を講じる必要性が示唆される。
今回の観測は、波がどのような経路で、どのようなスピードで海中を伝搬するのかを明らかにするため、対馬暖流の勢力が顕著に現れる佐渡の沖合に係留観測ステーションを設定し、1年間を通して波の観測を行なった。観測では、海底から垂直に立ち上げたロープに沿う形で流速計を数多く配置した。それぞれの装置から得られた流速のデータを繋ぎ合わせることで、台風によって励起された波のエネルギーを海面から深層までシームレスに追跡する調査を行った。係留系での観測に加えて、台風の通過によって日本海の各海域に分配された運動エネルギーをマップ化し、それぞれの波の伝搬速度や波長などの知見を組み合わせることで、係留点で観測された波の発生源を特定し、また、対馬前線との関係性における波の増幅機構などについて明らかにした。このような研究のアプローチ、および、得られた成果は極めて斬新と言える。
東京大学大気海洋研究所の横山祐典教授、山梨県富士山科学研究所の山本真也主任研究員らによる研究グループは、山中湖の湖底及び湖畔から採取した過去8000年に及ぶ堆積物の放射性炭素年代測定を行い、過去の噴火で噴出した富士山の降下火砕物(テフラ)の詳細な堆積年代を明らかにしました。更に、過去に論文等で報告されたテフラの堆積記録との比較から、富士山北東麓では5050年前から3900年前にかけて、これまで報告されていない噴火が少なくとも6回発生していたことが明らかとなりました。本研究の成果は、従来の研究がこの時期の富士山の火山活動を過小評価していた可能性を示しており、火山防災上重要な新知見となるものです。
なお、研究成果をまとめた研究論文は、エルゼビア社の国際学術誌Quaternary Science Advancesに令和5年6月30日に掲載されました。
東京大学大気海洋研究所の新里宙也准教授を中心とする研究グループは、サンゴと褐虫藻の共生に重要な役割を担っている可能性が高い遺伝子群を特定しました。
本研究では、世界中のサンゴ礁で一般的な造礁サンゴの一種であるウスエダミドリイシ(学名:Acropora tenuis)の初期生活期(プラヌラ幼生と初期ポリプ)において、天然海域で実際に共生している褐虫藻種、Symbiodinium microadriaticumと共生した時に起こる遺伝子発現を網羅的に解析しました。その結果、糖や脂質の輸送、免疫制御や抗酸化防御に関わる15個の遺伝子は、褐虫藻と共生している時に、体内の褐虫藻数に応じて発現量が増加することが明らかとなりました。これら遺伝子群の進化的起源を探ると、一部の遺伝子はミドリイシ属サンゴの共通祖先のゲノム上で重複している(遺伝子重複)ことが明らかとなりました。この結果は、それぞれのサンゴ系統で独自に獲得した遺伝子が、それぞれの系統で共生に関与する可能性を示しています。また、遺伝子重複が安定した共生関係を構築するための進化の原動力であったこと、サンゴの共生メカニズムは系統・種ごとに多様であることを示唆します。これらの成果は今後、サンゴと褐虫藻の共生メカニズム全容解明に役立つことが期待されます。
東京大学大気海洋研究所の藤井賢彦教授とベルナルド・ローレンス・パトリック・カセス特任研究員らによる研究グループは、国内水産業において重要な貝類養殖種であるマガキの養殖が盛んな国内2地点(岡山県備前市日生海域と宮城県南三陸町志津川湾)の河口部や沖合、藻場、養殖場の付近など環境が異なる複数箇所において、地元の漁業協同組合などと協働し、実際のマガキ養殖域での海洋酸性化の進行状況を連続観測しました。また、本研究グループが自ら開発した数値モデルを上記の観測点に適用し、マガキ養殖の海洋酸性化・地球温暖化影響の将来予測を行いました。その結果、場所や時期によっては海洋酸性化がマガキに影響を及ぼす可能性のある水準に達していることが分かりました。また、今世紀末までに日本沿岸のマガキ養殖は海洋酸性化と地球温暖化に伴う水温上昇による深刻な複合影響を受ける可能性が予測されました。本研究の結果は、今後、マガキ養殖に対する深刻な影響を回避するためには、人為起源CO2の大幅削減を世界中で行っていくことに加えて、河川からマガキ養殖域への淡水や有機物の流入を抑制する取り組みを地域で行うことも有効であることを示唆しており、地域の実情に応じた対策を講じる上で必要な科学的指針を具体的に提示するものと期待されます。
東京大学の齋藤綾華大学院生(大学院農学生命科学研究科)、坂本健太郎准教授(大気海洋研究所)らからなる研究グループは、潜水能力の高い海生爬虫類であるアカウミガメ(Caretta caretta)において、海面で呼吸するときに1分間に約21回である心拍数が、潜水すると急激に低下し1分間に約13回となること、特に140 mより深く潜ったときは1分間に2回まで低下すること、そして深く潜るほど心拍数はより低くなることを明らかにしました。
本研究では、世界で2例目となる、ウミガメが海を潜るときの心拍数測定に成功しました。その結果、爬虫類で報告された潜水中の心拍数の記録としては、これまでで最も深い場所での記録を得ることが出来ました。本研究により、活動中の肺呼吸動物としては、アカウミガメは最も心拍数が低下する動物のひとつであることがわかりました。爬虫類であるウミガメが深く潜るときの心拍数が明らかになったことで、肺呼吸動物が海で生きていくための仕組みの理解につながると考えています。
本研究所附属の大槌沿岸センター(岩手県大槌町)は、東日本大震災によって壊滅的な被害を受けましたが、2018年2月に新しい研究実験棟と宿泊棟が竣工しました。文部科学省のプロジェクト研究「東北マリンサイエンス拠点形成事業」の一拠点として、震災後の海洋生態系の変化を総合的に記録し続けると同時に、地域水産業の復興・発展に資する沿岸海洋生態系の理解に向けた学際的フィールド研究拠点としての発展を目指した活動を行いました。次世代の人材育成等を通じて三陸地域の復興・発展を目指す文理融合型研究教育プロジェクト「海と希望の学校in三陸」は岩手県、さらには奄美群島にも拡大し、文部科学省の「海洋資源利用促進技術開発プログラム、市民参加による海洋総合知創出手法構築プロジェクト」の中核機関に採択されるところまで成長してきました。
また、2024年3月に金沢大学環日本海域環境研究センターと連携協定を締結しました。令和6年能登半島地震の震源を含む日本沿岸域及び外洋域における大気海洋科学を推進するとともに、これまで大槌で震災復興に取り組んだ経験を活かし、教育研究の進展と人材育成に寄与することで、よりよい未来社会の形成に貢献してまいります。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)評価報告書の執筆に多数の教員が参加しているほか、ユネスコ政府間海洋学委員会、北太平洋海洋科学機構、Future Earthやアジア研究教育拠点事業などに参画し、国際協力が必須の大気海洋科学に関する諸問題の解決、そして国連海洋科学の10年(2021-2030)の実施に向けて取り組みを進めています。
気候と社会連携研究機構(UTCCS)には、多様な学術に取り組む学内12の部局から70名を超える教員が参画しており、大気海洋研究所はその主管部局を務めています。気候変動の理解と予測、気候変動の生態系への影響解明、温室効果ガスの排出経路を決める将来の社会システムデザイン、気候正義にかかわる公共政策、さまざまな階層における行動変容、などの分野横断研究を推進する拠点であるとともに、本学のGX推進に協力し、広い視野をもつ若手人材を教育することを目指しています。
海洋アライアンス連携研究機構には学内の7研究科と5研究所が参画しており、大気海洋研究所はその主管部局を務めています。海に関わる研究・教育の部局横断的なネットワーク組織として、我が国が目指す「SDGs実施指針」の優先8分野の1つである「生物多様性、森林、海洋等の環境保全」を中心に現代的課題の発掘とその解決に必要な基礎科学・応用科学の探究を行っています。その一方、学際的な海洋問題に即応できる高度海洋人材の育成に取り組むとともに、シンクタンクの役割を果たすことによって一般社会への情報発信と社会貢献を図り、海洋関連分野における研究・教育の国際的な核を形成することを目的としています。
「さいえんす寿司BAR」や講演会の開催、一般向け書籍・小冊子の刊行など、大気海洋科学に親しみ研究内容について楽しみながら広く知っていただく活動を行っています。毎年10月に柏キャンパスで一般公開を行っており、8,000人以上が来場する一大イベントになっています。大槌沿岸センターでは、2021年4月に開設した展示資料館「海の勉強室」において研究成果の発信と交流を行っています。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png