

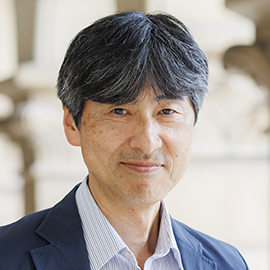
医科学研究所は1892年に設立された大日本私立衛生会附属伝染病研究所を前身とし、1967年に医科学研究所として改組されました。この明治、大正、昭和、そして令和へと繋がる133年の歴史を背景に、本研究所は生命現象の普遍的な真理と疾患原理を探究し、革新的な予防法・治療法の開発とその社会実装による人類社会全体への貢献を目指しています。現在、約700名の教職員とポスドク研究員、約230名の大学院学生が所属しており、国立大学の附置研究所としては唯一の、先端医療の開発を実践する附属病院を持つ学際的かつ社会性に富む研究所です。2009年には全国共同利用・共同研究拠点の認定を受け、従来からの産学官連携に加えて、全国公募した多くの共同研究を実施しています。さらに、2018年には国際共同利用・共同研究拠点の認定を受け、日本と世界の最先端研究の架け橋としての役割を果たしています。
生命現象の真理と疾患原理の探究、革新的な予防法・治療法の開発を推進するために、自由な発想に基づく基礎・橋渡し研究を推進する基幹研究部門として基礎医科学部門、癌・細胞増殖部門、感染・免疫部門の3部門が設置されています。また、多様な研究成果を社会実装するために必要な課題に取組むセンター・施設として、生命科学では国内最大の性能をもつスーパーコンピュータ(SHIROKANE)を擁するヒトゲノム解析センターや、革新的医療を開発する先端医療研究センター等の7センター、5研究施設が設置されています。さらに、国立大学附置研究所では唯一の附属病院では、世界トップレベルの研究成果に基づく臨床試験や先端医療が進められています。
令和6年度は、主な大型プロジェクト研究として、「橋渡し研究プログラム」、「新興・再興感染症研究基盤創成事業(海外拠点研究領域)」、「ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム」を展開し、「基礎・応用医科学の推進と先端医療の実現を目指した医科学国際共同研究事業」、「医科学研究の推進と先端医療の実現を加速する国際研究組織整備事業」、「連携基盤を活用した感染症制御に向けた最先端研究・次世代人材育成事業」などの事業を推進しました。
最近の主な成果は以下のとおりです。
人類社会全体への貢献を目指す本研究所の基礎・橋渡し・臨床研究を基盤として、国際共同利用・共同研究拠点などの活動を通じて国内外の研究者や製薬企業等との学際的な共同研究・連携研究を積極的に進めています。さらに、本研究所や各共同研究機関が保有するライフイノベーションのシーズを、基幹研究部門や研究センター・施設、附属病院が有する多様な研究基盤を活用することで、革新的な医薬品の開発や、再生医療、遺伝子・細胞治療、ウイルス療法等の確立へと展開しています。その上で、生命現象の真理と疾患原理の解明を目指す基礎研究や新規予防・治療法の開発を目指す応用研究の将来を担う人材の育成を精力的に進めています。以上の活動により、最先端の基礎・臨床医科学の研究成果を医療の現場に届け、社会に貢献することが我々の使命です。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png