

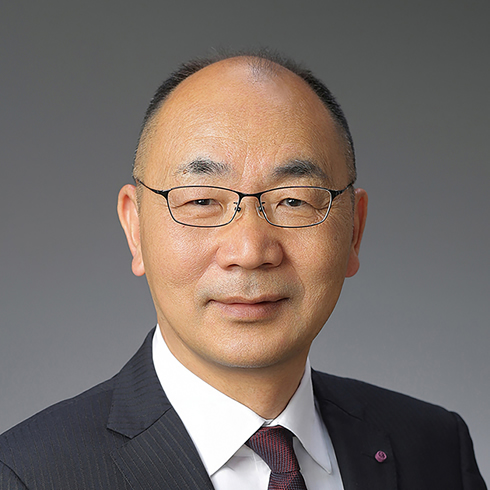
資源植物科学研究所は、基礎科学的な知識の活用による農業生産の改善を目的に1914年に創立された財団法人大原奨農会農業研究所を起源とし、第二次世界大戦後に岡山大学に移管された以降、幾たびかの改組を経ながら農学に関連する教育研究を実施してきました。2010年より「植物遺伝資源・ストレス科学研究」に関する研究を推進する共同利用・共同研究拠点として、植物のストレス応答の基礎研究を進め得られた知見を基盤に遺伝資源を活用し、将来予想される気候に適応できる作物の育種をめざした研究活動を推進しています。地球温暖化による環境の変化がもたらす作物生産の低下と世界人口増加による食糧需要の増加が重なり、近い将来の食糧不足が危ぶまれるなか、当研究所の役割はますます重要性を増していると認識しています。
植物は土壌からケイ素を吸収し、葉の表面などに蓄積することで、様々なストレスから身を守ります。イネ科植物、特にイネは多量のケイ素を吸収・蓄積しますが、その制御機構はほとんど未解明でした。私たちはイネのケイ素吸収を促進するシグナルタンパク質SSS(Shoot-Silicon-Signal)を発見しました。SSS遺伝子はケイ素欠乏時の葉や節のみに発現し、根には発現しません。しかし今回私たちは、吸汁中のウンカの口針をレーザーで狙って切断し、その切り口から篩管液を回収する「DIY-インセクトレーザー法」の開発に成功し、SSSタンパク質を篩管液や根からも検出しました。長距離シグナルSSSによって、イネはより積極的にケイ素を利用できるようになったと考えられます。
植物は、NLR型免疫受容体を用いて病原菌を認識し、免疫反応を誘導します。河野教授を含む複数の研究チームによる研究の結果、2種類の異なるNLR型免疫受容体がそれぞれ病原菌の認識を担うセンサーと、免疫反応を誘導する役割を果たしながら、協調して1つの受容体複合体として機能する「ペアNLR受容体」が発見されました。今回の研究では、イネいもち病菌に対応する新たなペアNLR受容体であるPit1とPit2が発見されました。進化解析の結果、免疫誘導型NLR受容体であるPit1遺伝子が遺伝子重複によって2つに分かれ、そのうちの1つがセンサー型NLR受容体へと分化し、パラログ遺伝子であるPit2が形成されたと推測されました。これらの発見は、イネがいもち病菌を認識する進化的プロセスを理解する上で重要な知見を提供します。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png