

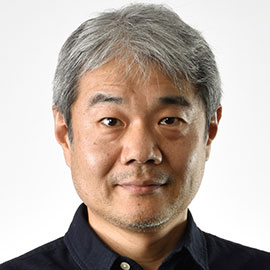
北海道大学低温科学研究所は、1941年の創設以来、寒冷圏および低温環境下における自然現象の基礎と応用の研究を行っています。2010年からは低温科学に関する共同利用・共同研究拠点として活動の幅を拡げ、国内外の研究機関と連携したプロジェクト等も推進しています。南極・北極など世界各地でさまざまなフィールド研究に注力するとともに、基礎研究では低温をキーワードとした学問分野を超えた新たな科学の創成に取り組んでいます。物理学、化学、地球惑星科学、海洋科学、生物環境科学など、様々な分野の研究者が有機的に繋がることで、世界的にも類を見ないユニークな研究を展開しています。
現在、南極氷床の崩壊が地球の海水位を押し上げるプロセスに世界的な注目があつまっている。将来の海水位上昇を予測するうえで、もっとも影響が大きくまた評価が難しいのがこの南極氷床の流出プロセスである。人工衛星を用いた観測により、南極のなかでも南米大陸の南方にあたる西南極氷床の流出が大きく加速している様子が捉えられ、現在世界各国が詳細観測とメカニズム解明の努力をしている。この領域に加え、近年、オーストラリアの南方にあたる東南極・トッテン氷河に流出加速の兆しがみられるようになってきた。この領域の氷床は、海水位を4メートルほど上昇させる潜在力をもつ。こうした氷床の崩壊には、海がもつ熱の役割が重要だと考えられている。しかし、トッテン氷河付近は厚い海氷に阻まれ、海底の地形や海洋の温度構造など、これまでほとんど調べられてこなかった。
本研究所は、国内外の海洋・気候研究者を糾合して、南極地域観測の重点研究観測(2016-2022年度)としてこの地域を現地調査するプロジェクトを提案し、これまでにない規模での観測を実施することに成功した(図1)。砕氷船しらせに搭載された水深測定装置で、沖側の大陸棚の縁は比較的深く、氷河の前面にあるさらに深い氷河浸食谷へとつながる海底地形のつながりを明らかにした。海洋の水温・塩分の鉛直プロファイル観測で、下層の比較的暖かい海水が陸棚縁のうえを通って入り込み、氷河末端部の棚氷の下まで到達する様子を捉えた(図2)。水温の時系列観測からは、水温にはさまざまな時間スケールの変動があることが確認できた。一連の観測や数値実験で、沖側からの暖水流入による熱供給は、トッテン氷河を下から融かすのに十分な量があることが明らかになった(図3)。
地球温暖化の進展に対し、こうした海洋からの熱供給は今後どのように変動するのか、それに対して氷河の流出はどのように応答するのか、過去の温暖な時期にはどの程度まで氷床崩壊がすすんだのか、などさらなる詳細なシナリオの研究が必要である。こうした研究を進めることで、将来の海水位上昇の予測精度向上に貢献することを目指している。
■共同研究・研究集会の開催
多くの所外研究者を招いて、共同研究の実施や研究集会の開催を推進しています。特に研究集会は、既存の学会や研究コミュニティを横断的に繋げる新たなコミュニティの創設を目指す企画を強化しています。
■国際連携の強化
現在までに33の国外研究機関、組織との連携研究協定を締結するなど、低温科学における世界的拠点としての機能を果たすために国際化を推進しています。
■雑誌「低温科学」
本研究所が毎年発行する「低温科学」は、毎年テーマを決めて、地球惑星科学、物性科学、地球化学、海洋学、生物分子科学、環境科学などを専門とする所内外の研究者により執筆し、専門家、初学者、さらには一般向けに研究所の研究をわかりやすく伝えていこうという趣旨の雑誌です。掲載記事は、「北海道大学学術成果コレクション(HUSCAP)」において公開し、自由にダウンロードも可能です。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png