

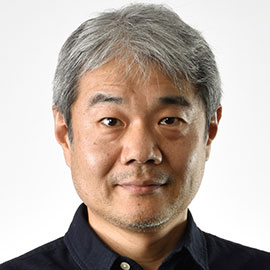
北海道大学低温科学研究所は、1941年の創設以来、寒冷圏および低温環境下における自然現象の基礎と応用の研究を行っています。2010年からは低温科学に関する共同利用・共同研究拠点として活動の幅を拡げ、国内外の研究機関と連携したプロジェクト等も推進しています。南極・北極など世界各地でさまざまなフィールド研究に注力するとともに,基礎研究では低温をキーワードとした学問分野を超えた新たな科学の創造に取り組んでいます。物理学、化学、地球惑星科学、海洋科学、生物環境科学など、様々な分野の研究者が有機的に繋がることで、世界的にも類を見ないユニークな研究を展開しています。
地球温暖化に伴い生息環境の気温が上昇すると、様々な生物が、適切な気温帯を求めて、寒冷な地域へ移動(逃避)することが知られている。一般的に、気温1℃の低下を達成するためには、水平方向にして約145kmの北上(南半球では南下)が、垂直方向にして約167mの上昇が必要になる。従って、多くの生物にとって、水平方向よりも垂直方向への移動(例えば、山岳地域への移動)が容易な逃避行動になる。しかし水平方向の移動に比べて垂直方向への移動は、生物に様々な影響をもたらす。とくに注目されているのは、標高の上昇に伴う酸素分圧の低下である。もともと低地に棲んでいた生物は、体内に酸素を十分に取り込むことが難しくなり、代謝機能が低下し、1年をとおした生活サイクルに大きな影響をもたらす。実際に、大気圧(海面で1013hPa)は、垂直方向に100m上昇するごとに12hPa低下するため、生物の呼吸に必要な酸素分圧は、低地(0m)に比べて、1000mで約11%、2000mで約22%も低下する。
そこで本研究所では、米国・ウィスコンシン大学と共同で、北海道の大雪山系において、様々な標高で昆虫(マルハナバチ、マメコバチなど)や両生類(オタマジャクシ)を採取し(図1)、生育高度による体長、体重などの変化や、それに伴うエネルギー消費率の変化(図2)を調査するプロジェクトを立ち上げた(2024-2029年度)。2024年度の調査の結果、近年、多くの昆虫の生息域が高標高域に移動していることを確認し、また垂直方向の移動に伴い、昆虫の体サイズが減少していることが明らかになった(図3)。またこの傾向は、研究室で減圧チャンバーを用いた飼育実験の結果とも一致した。
「生息域の標高が、生物の代謝機能に与える影響」を正確に評価することは、昨今の深刻な地球温暖化に伴い、世界中の研究機関・大学で注目されている課題の1つになっている。本プロジェクトは、この「影響」の解明し、将来的には、「環境変化に対する生物の適応機構」に関しての理解を深めるとともに、「温暖化から生物を守り、生物多様性を維持するための施策」に資する正確な基礎情報を提供することを目指している。
■共同研究・研究集会の開催
多くの所外研究者を招いて、共同研究の実施や研究集会の開催を推進しています。特に研究集会は、既存の学会や研究コミュニティを横断的に繋げる新たなコミュニティの創設を目指す企画を強化しています。
■国際連携の強化
現在までに33の国外研究機関、組織との連携研究協定を締結するなど、低温科学における世界的拠点としての機能を果たすために国際化を推進しています。
■雑誌「低温科学」
本研究所が毎年発行する「低温科学」は、毎年テーマを決めて、地球惑星科学、物性科学、地球化学、海洋学、生物分子科学、環境科学などを専門とする所内外の研究者により執筆し、専門家、初学者、さらには一般向けに研究所の研究をわかりやすく伝えていこうという趣旨の雑誌です。掲載記事は、「北海道大学学術成果コレクション(HUSCAP)」において公開し、自由にダウンロードも可能です。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png