

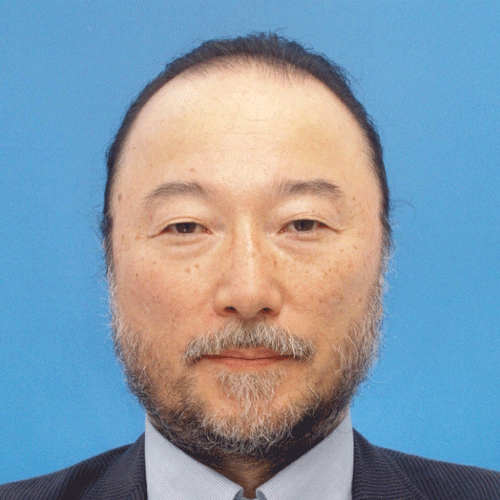
平成17年4月に人獣共通感染症リサーチセンターとして活動を開始し、人獣共通感染症病原体の自然宿主と伝播経路の解明、宿主域と病原性の分子基盤の解明、出現予測、診断・予防・治療法の開発を目指して、地球規模で疫学研究活動を展開すると共に、基礎・応用研究を推進しています。また、人獣共通感染症の制圧に向けて、科学的見地に基づき、人獣共通感染症対策のための提言を国際機関、政府および関連機関に向けて発信しています。教育面では、北海道大学One Healthフロンティア卓越大学院プログラムと連携して、人獣共通感染症対策専門家の育成に取り組んでいます。令和3年4月から、人獣共通感染症リサーチセンターを基盤として組織を充実させた3ユニットから成る人獣共通感染症国際共同研究所となりました。
本研究所では、人獣共通感染症制圧に向けた基礎研究および予防・診断・治療薬の開発を推進しています。令和6年度の成果の一部を以下に記します。
東京大学医科学研究所、大阪大学微生物病研究所、長崎大学熱帯医学研究所および長崎大学高度感染症研究センターと共同で提案し文部科学省より採択された「連携基盤を活用した感染症制御に向けた最先端研究・次世代人材育成事業」(令和4−9年度)、JICA「健康危機対応能力強化に向けた感染症対策グローバルリーダー育成プログラム」との連携および国際感染症学院での大学院教育等を通して、感染症制御に向けた次世代人材育成および社会への情報発信等に取り組んでいます。
世界保健機関(WHO)、国際獣疫事務局(OIE)および国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関との連携に加え、ウイルス、細菌および原虫感染症の基礎研究および診断・予防・治療法の開発において海外の30以上の機関と様々な共同研究を展開するなど、人獣共通感染症研究の世界的拠点としての機能を果たしています。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png