

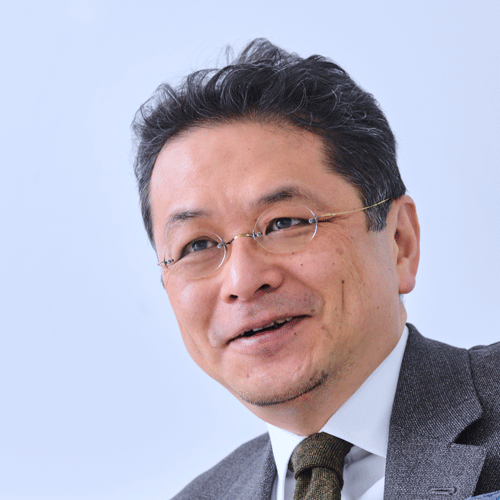
一橋大学経済研究所は設置目的である「日本及び世界の経済の総合研究」の推進を目指し、30名ほどの研究スタッフを擁して、厳密で周到なアプローチをとりつつ、同時に幅広い関心・好奇心を持って、先進的な研究活動に取り組んでいます。本研究所は1940年に東京商科⼤学東亜経済研究所として設置され、日本の経済社会に関する歴史的統計データの構築とその提供が、当初の活動の大きな部分を占めてきました。1980年代以降は研究領域を広げ、データと結びついた高度な理論・実証研究や政策研究を展開し、多くの優れた成果をあげてきました。
現在は、個々のスタッフによる高い水準の研究の推進に加えて、大型研究プロジェクトを立ち上げ、所内に複数の機構・センターを設置して、国際的に開かれた研究ネットワークのハブとしての役割を担った研究活動を行っています。組織としては、「経済・統計理論」「経済計測」「⽐較経済・世界経済」「経済制度・経済政策」「新学術領域」の5つの研究部門と、「社会科学統計情報研究センター」「経済制度研究センター」「世代間問題研究機構」「経済社会リスク研究機構」の4つの附属研究施設体制で研究を推進しています。また2010年度以降、⽂部科学省の共同利⽤・共同研究拠点制度の下で「⽇本および世界経済の⾼度実証分析」の拠点として、公募による共同研究プロジェクトなどの各種事業を行っています。
以下では研究所の活動のうち、2024年度の特徴あるものとして4つを紹介します。
① 「日本および世界経済の高度実証分析」拠点の参加型事業:本研究所は文部科学省により共同利用・共同研究拠点として認定されており、公募による共同研究プロジェクトなどの各種事業を行っています。2024年度には、政府統計やミクロデータを用いた家計・企業の実証研究等に関して、合計40件の公募共同研究プロジェクト、1件の政府統計匿名データ利用促進プログラム、4件の参加型研究プロジェクト、総計45件を採択し外部研究者の研究を推進しています。特筆すべきプロジェクトとしては「高齢化と社会保障に関する研究」、「金利と企業のダイナミクスに関する研究」、「将来の不確実性とマクロ経済のパフォーマンス」に関する研究などがあり、興味深い研究成果があがっています。また、物価・資産価格・生産性・地域経済・アジア長期経済統計等を中核とするデータ・アーカイブのアップデートと公開を継続しています。
② 経済社会リスク研究機構:独自の「SRI一橋大学消費者購買指数」を公表しつつ、様々な独自サーベイを行いながら、家計消費や物価等に関する多くの研究を内外の研究者と共同で行っています。SRI指数は市場調査会社の協力を得て、スーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア・大型小売店をカバーする日本全国4000店舗のPOSデータに基づいたもので、消費者の購買行動の変化を詳細に把握することを目的として作成され、毎週データを更新しています。
③ 世代間問題研究機構:世代間問題研究機構は、急速に進行する日本社会の少子高齢化の進行を踏まえ、年金・医療・介護・雇用等の世代間問題を主として経済学の立場から分析・検討し、政策提言を行うことを目指して活動しています。また内外の研究者や政府機関から継続的に任期付教員を受け入れています。2024年度は、内閣府と日本銀行からの出向者を受け入れ、連携して研究を推進しており、以下の国際コンファレンスの開催の際にも、彼らを通じた省庁との連携関係が非常に重要な役割を果たしています。
④ 国際コンファレンスの開催
2024年度は、International Association of Research in Income and Wealth(IARIW)及び本学のソーシャル・データサイエンス学部や内閣府・麗沢大学と共同で、国際コンファレンス IARIW-Hitotsubashi University Conference on “Population Ageing: Implications for Economic Measurement and Economic Performance”をホストしました(2025年3月24-25日開催)。また直後(3月27日-28日)に開催された、世界各国の経済成長と生産性に関する分析のためのコンソーシアムであるWorld KLEMSのthe 8th World Conferenceでも、深尾京司特命教授などを中心に、学習院大学・経済産業研究所とともに日本側の主要メンバーとして当研究所が重要な役割を果たしています。本研究所のメンバーは、その他にも数多くの国内の主要コンファレンスや、国際コンファレンスに主要なオーガナイザーとして関わっています。
本研究所は、中央官庁等との間で人事交流・研究連携を積極的に進めている。2024年度時点では社会科学統計情報研究センターに総務省統計局から2名、世代間問題研究機構に内閣府から1名のスタッフを受け入れたほか、日本銀行とも人事交流を行っている。さらには、経済産業研究所、国立社会保障・人口問題研究所、財務省財務総合政策研究所、内閣府経済社会総合研究所、ニッセイ基礎研究所、日本銀行金融研究所、日本経済研究センター、日本貿易振興機構アジア経済研究所とは覚書を結んで研究連携を深めている。
経済研究所スタッフは、一橋大学アカデミア、一橋大学政策フォーラム、各種シンポジウム等での一般向け講演・レクチャー、啓発的研究書出版、テレビ・新聞、雑誌等での発言等々の形で一般向けの研究成果の発信を積極的に行っている。また日本経済新聞の「経済教室」、「やさしい経済学」などに主要な経済政策議論に多くのスタッフが参加し、政策議論を展開している。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png