

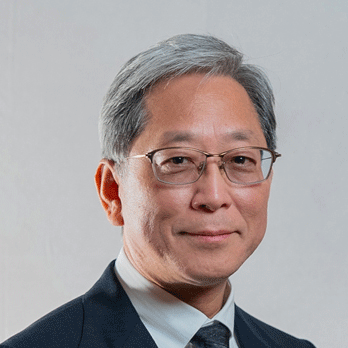
大気海洋研究所は、地球表層を覆う海洋と大気の構造や変動メカニズム、および海洋に生きる生物に関する様々な基礎的研究を推進するとともに、地球環境の変動や生命の進化、海洋生物群集の変動など、人類と生命圏の存続にとって重要な課題の解決につながる研究を展開しています。また、大気海洋科学に係わる全国の研究者のための共同利用・共同研究拠点として、本所(柏キャンパス)と附属国際・地域連携研究センター地域連携研究部門大槌研究拠点(岩手県大槌町︓2022年度に国際沿岸海洋研究センターから改組、以下大槌沿岸センター)において世界最先端の研究施設・機器、充実した研究環境を提供するとともに、海洋研究開発機構の所有する2隻の学術研究船「白鳳丸」と「新青丸」および深海潜水調査船支援母船「よこすか」を用いた共同利用・共同研究を企画・運営し、世界の大気海洋科学を先導することを目指しています。さらには、大学院教育や様々なプロジェクト研究の推進などを通じて、次世代の大気海洋科学を担う若手研究者の育成にも力を入れています。
東京大学大学院総合文化研究科博士課程(研究当時)の蘭慧、大気海洋研究所の横山祐典教授らによる研究グループは、黒潮大蛇行時期の黒潮の内部構造を初めて海水中の炭素14(溶存無機炭素中の放射性炭素同位体比:DICΔ14C)によって可視化することに成功し、黒潮内部での海水混合の実態について明らかにしました。
黒潮大蛇行とは、本州南方を流れる黒潮の流れの中心が東経136度から140度の区間で、北緯32度よりも南を流れる現象です。現在の大蛇行は過去最長の約7年間にもおよびます。近年その大蛇行が長期化していることから、気候や海洋生態系にも影響を与えると考えられています。たとえば魚の稚魚分布の変化による漁業への影響や流路変動による沿岸地域への高波の影響などです。本研究では、学術研究船「白鳳丸」KH-22-5次研究航海により、本州南方の黒潮海域の8地点において複数の深度で採水を行い、DICΔ14Cの高精度分析を行いました。その結果、黒潮大蛇行時期の黒潮の内部構造を初めてDICΔ14Cから捉えることに成功し、水塊混合プロセスを明らかにしました。特に炭素14が海洋水塊混合のダイナミクスを探るために非常に有効なトレーサーであることが明らかになりました。本研究の成果は、黒潮大蛇行によって引き起こされる海洋物理的な水塊変動への影響を理解する上で重要であり、炭素14を分析することで、海洋の鉛直循環やそれに伴う海洋生態系の変化について重要な知見を与える可能性を提示しました。
東京大学大学院農学生命科学研究科の細野将汰大学院生と、大気海洋研究所の岩田容子准教授、河村知彦教授らによる研究グループは、ヤリイカの雄の繁殖戦術が孵化日によって決定されることを明らかにしました。
同種の同性内に複数の繁殖戦術が見られる現象(代替繁殖戦術)は、幅広い分類群で知られています。“誕生日仮説”は、各個体がとる繁殖戦術がどのように決定されるかを説明する仮説として提唱されましたが、実証例はこれまで魚類3例のみでした。今回、大型雄と小型雄という代替繁殖戦術を持つヤリイカで、平衡石を用いて孵化日を調べたところ、魚類以外でも誕生日仮説が成り立つことが初めて明らかになりました。この成果は、孵化時期の環境条件が気候変動等によって変化すると、繁殖戦術、ひいては成熟サイズも変化することを示しており、気候変動が海洋生物に与える影響を予測する上で役立つことが期待されます。
東京大学大気海洋研究所の川口悠介助教の研究チームは、ドイツのアルフレッド・ウェゲナー海洋研究所の砕氷船「ポーラーシュテルン号」による北極海の観測に参加しました。研究チームは、海氷や海氷直下の海水中のごく微小な水温や水流の変化を検出し、それが北極海全域にわたる大規模なスケールでの海氷や海水の動きにどのように影響するかを明らかにしました。観測では、渦相関法と呼ばれる技術を採用し、海氷底面付近での海氷の融解や海水の凍結といった異なる相状態における海氷と海洋間の運動量の伝達率を詳細に計測しました。
観測データを基に、海水の相状態(融解や結氷)を海水の熱収支から計算し、海水の静的安定度という客観的な指標に置き換えることに成功しました。これにより、地球温暖化などを評価する全球シミュレーションに実装可能な形での定式化が実現しました。この成果は、北極海や南極海などの海氷の広がりを長期予測するためのシミュレーションの精度向上に大きく貢献することが期待されます。
東京大学の沖野郷子教授、升本順夫教授が率いる研究グループが、学術研究船「白鳳丸」を用いて約3ヶ月間にわたるインド洋での観測調査を行います(図1)。本航海には、全国15の大学や研究機関から総勢65名の研究者(大学院生含む)が乗船します。前半は、海洋物理学、生物地球化学、生態学などの分野横断的な研究チームによる東部インド洋海域の統合的な観測調査です。生物生産の元となる海洋中の栄養分が乏しい熱帯から亜熱帯の外洋域の中でも特に現場での観測データが少ない海域で観測を行うことにより、貧栄養海域における微量元素や各種物質の分布、また海洋構造と生物動態との関係などについて新知見が得られることが期待されます。後半は、中央インド洋海嶺の巨大断層に沿って、地球物理観測や岩石採取を主とした総合調査を行います。海底に存在する亀裂であるトランスフォーム断層では、過去から現在に至る海洋地殻の断面が露出しています。長大なトランスフォーム断層という特異な条件を利用して、現在から過去1100万年前までの海洋底の形成の履歴を明らかにし、地球システムの長期変動の実態と要因に迫ります。
東京大学先端科学技術研究センターの小坂優准教授、同大学大気海洋研究所の渡部雅浩教授らの研究チームは、近年の熱帯太平洋ウォーカー循環の強化が、熱帯外の海面水温変動が熱帯域にもたらす遠隔影響で定量的に説明できることを、気候モデルを用いたシミュレーションにより明らかにしました。さらにその影響の大部分が亜熱帯南太平洋からもたらされること、通常の気候モデルシミュレーションではこの鍵となる海域の海面水温変動が十分に表現されていないことも示しました。ウォーカー循環の変動は地球の平均気温変動にも影響する重要な気候要素ですが、観測された強化の要因は不明で、気候モデルでもこの強化は捉えられていませんでした。本研究により、強化をもたらした要因の解明への道筋が立ち、また気候モデルがそれを再現できていなかった原因についても示唆が与えられたことから、気候変動予測の精緻化に貢献することが期待されます。
東京大学大気海洋研究所の髙木亙助教と兵藤晋教授、同大学大学院理学系研究科の増田絢美大学院生(研究当時)、専修大学経済学部・同大学自然科学研究所の髙部由季講師、アクアワールド茨城県大洗水族館の徳永幸太郎副参事らの共同研究グループは、細菌数計測と群集構造解析を組み合わせ、トラザメ卵殻内の微生物環境を詳細に解析しました。卵生の板鰓類は、産卵から孵化までに数ヶ月から1年を要しますが、この長い発生期間中、胚がどのようにして海水中の病原性細菌から守られているかは不明でした。卵生の板鰓類の胚は、コラーゲンでできた丈夫な卵殻の中で発生します。また、多くの卵生種では、発生期間の1/3を過ぎた頃に卵殻の一部が開き、卵殻内外を海水が自由に出入りするようになる「プレハッチ」という現象が知られています。プレハッチ以前の初期胚は免疫機能が未発達で、病原性細菌に対する抵抗性がないと考えられていましたが、実験的に検証された例はありませんでした。本研究グループは、まず胚の病原性細菌に対する抵抗性を調べるため、発生中のトラザメ胚を用いて生存実験を行いました。プレハッチ前の初期胚を卵殻から取り出し、天然海水に曝露したところ、20日以内にすべての個体の死亡が確認されました。一方、抗生物質を添加した海水への曝露では全ての個体が生存したため、これまで予想されていた通り、発生初期の胚は、病原性細菌への感染に脆弱であることが確かめられました。
▼発表内容の続きは、プレスリリース掲載ページにてご確認ください。
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2024/20241023.html
東京大学の三木志緒乃大学院生、白井厚太朗准教授、山口飛鳥准教授、棚部一成東京大学名誉教授、海洋研究開発機構 窪田薫研究員、産業技術総合研究所 中島礼総括研究主幹、マインツ大学Schöne教授、Brosset大学院生による研究グループは、ビノスガイ(学名:Mercenaria stimpsoni)の化石を用いて、過去の温暖期(約10万年前、約20万年前、約30万年前)の古東京湾の海水温の季節変化を明らかにしました。
本研究では、100歳を超える長寿二枚貝であるビノスガイと、過去の海水温の復元のための良好な条件に恵まれた千葉県の下総層群(しもうさそうぐん)に着目しました。貝殻の成長線解析と酸素同位体比分析を用いることで、当時の海水温の季節変動を復元し、最高水温をこれまでより高い信頼性で明らかにすることに成功しました。これらの過去の温暖期は海水準が高く関東平野が海面下にあった時代ですが、最高水温は現在の千葉県の沿岸域の水温よりも5度以上低く、現在の東北地方や北海道の沿岸域の水温に近かった時期があったことが分かりました。今後、当時の海洋の環境を理解することを通して、モデリングなどによる気候の将来予測に役立つことが期待されます。
東京大学大気海洋研究所の平井惇也講師と、紋別市産業部水産課の片倉靖次参事、水産研究・教育機構水産技術研究所の長井敏主幹研究員らによる研究グループは、これまで謎に包まれていた海洋性ウイルスが動物プランクトンの個体数や生理状態に与える影響を調査しました。動物プランクトンは一次生産者である植物プランクトンを主に摂餌し、水産重要種を含む魚類仔魚等の重要な餌となり海洋生態系を支えています。一方、海洋性ウイルスは微生物や植物プランクトンに感染することで物質循環に大きな影響を与えるのみならず、養殖業では時に大量斃死(へいし)を引き起こし我々の生活にも密接に関わっています。しかし、動物プランクトン-ウイルスの相互作用については圧倒的に理解が進んでおらず、長らく海洋生態系を理解する上で欠けたピースとなっていました。そこで本研究グループは、海洋モニタリングが行われる北海道紋別市オホーツクタワーにおいて高頻度採集を行い、調査地域で優占するカイアシ類Pseudocalanus newmaniに着目してウイルスとの関係を調べました。はじめに、カイアシ類から次世代シーケンサーを用いてRNAの塩基配列を取得するRNA-seqを行ったところ、これまで未報告のウイルスの配列が取得されました。また、これらのウイルスのカイアシ類からの検出率、各個体におけるウイルスコピー数を定量PCR法で調べたところ、カイアシ類の個体数の減少時期とウイルスが検出される時期が一致し、ウイルスがカイアシ類の増減に関与している可能性が示されました。
▼発表内容の続きは、プレスリリース掲載ページにてご確認ください。
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2024/20241119.html
東京大学大気海洋研究所の黒田潤一郎准教授が、ドイツ、イタリア、米国の研究者らと共同で、大西洋と太平洋の海底掘削コアから得られた様々な古気候記録を「時刻合わせ」してつなげ、白亜紀-古第三紀境界直前、つまり恐竜が絶滅する直前の100万年間に起こった火山活動と気候変動の関係を、これまでにない時間解像度で詳細に解明しました。新たに得られた高時間解像度の地球化学的記録は、6700~6600万年前に、インドのデカン高原をつくった洪水玄武岩の形成時に2回の大規模な火山噴火があったことを示しました。さらに研究チームは地球化学モデルを駆使して、これら2回の大規模玄武岩噴火が、二酸化硫黄や二酸化炭素といった異なる揮発性物質を段階的に排出し、それぞれが地球規模の気候と生態系に多様な影響を及ぼしたことを明らかにしました。その影響は、後に訪れる天体衝突での壊滅的な大量絶滅の下地を作るのに寄与したかもしれません。
本研究所附属の大槌沿岸センター(岩手県大槌町)は、東日本大震災によって壊滅的な被害を受けましたが、2018年2月に新しい研究実験棟と宿泊棟が竣工しました。文部科学省のプロジェクト研究「東北マリンサイエンス拠点形成事業」の一拠点として、震災後の海洋生態系の変化を総合的に記録し続けると同時に、地域水産業の復興・発展に資する沿岸海洋生態系の理解に向けた学際的フィールド研究拠点としての発展を目指した活動を行いました。次世代の人材育成等を通じて三陸地域の復興・発展を目指す文理融合型研究教育プロジェクト「海と希望の学校in三陸」は岩手県、さらには奄美群島にも拡大し、文部科学省の「海洋資源利用促進技術開発プログラム、市民参加による海洋総合知創出手法構築プロジェクト」の中核機関に採択されるところまで成長してきました。
また、2024年3月に金沢大学環日本海域環境研究センターと連携協定を締結しました。令和6年能登半島地震の震源を含む日本沿岸域及び外洋域における大気海洋科学を推進するとともに、これまで大槌で震災復興に取り組んだ経験を活かし、教育研究の進展と人材育成に寄与することで、よりよい未来社会の形成に貢献してまいります。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)評価報告書の執筆に多数の教員が参加しているほか、ユネスコ政府間海洋学委員会、北太平洋海洋科学機構、Future Earthやアジア研究教育拠点事業などに参画し、国際協力が必須の大気海洋科学に関する諸問題の解決、そして国連海洋科学の10年(2021-2030)の実施に向けて取り組みを進めています。
気候と社会連携研究機構(UTCCS)には、多様な学術に取り組む学内12の部局から70名を超える教員が参画しており、大気海洋研究所はその主管部局を務めています。気候変動の理解と予測、気候変動の生態系への影響解明、温室効果ガスの排出経路を決める将来の社会システムデザイン、気候正義にかかわる公共政策、さまざまな階層における行動変容、などの分野横断研究を推進する拠点であるとともに、本学のGX推進に協力し、広い視野をもつ若手人材を教育することを目指しています。
海洋アライアンス連携研究機構には学内の7研究科と5研究所が参画しており、大気海洋研究所はその主管部局を務めています。海に関わる研究・教育の部局横断的なネットワーク組織として、我が国が目指す「SDGs実施指針」の優先8分野の1つである「生物多様性、森林、海洋等の環境保全」を中心に現代的課題の発掘とその解決に必要な基礎科学・応用科学の探究を行っています。その一方、学際的な海洋問題に即応できる高度海洋人材の育成に取り組むとともに、シンクタンクの役割を果たすことによって一般社会への情報発信と社会貢献を図り、海洋関連分野における研究・教育の国際的な核を形成することを目的としています。
「さいえんす寿司BAR」や講演会の開催、一般向け書籍・小冊子の刊行など、大気海洋科学に親しみ研究内容について楽しみながら広く知っていただく活動を行っています。毎年10月に柏キャンパスで一般公開を行っており、8,000人以上が来場する一大イベントになっています。大槌沿岸センターでは、2021年4月に開設した展示資料館「海の勉強室」において研究成果の発信と交流を行っています。
北海道大学
帯広畜産大学
東北大学
弘前大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京科学大学
一橋大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
岡山大学
広島大学
徳島大学
愛媛大学
高知大学
九州大学
佐賀大学
長崎大学
熊本大学
琉球大学
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png