

チェルノブイリと福島。人類が原子力発電を始めてから、もっとも深刻な事故が起きた2つの場所である。長崎大学原爆後障害医療研究所の高村昇教授は、その2つの地で、住民の支援にあたってきた世界的にも数少ない研究者の一人だ。
「災害大国日本では、今後ますます我々のような存在が必要になるはずです」と語る高村教授。復興が進む福島で、後進を育てる活動に邁進する。
2020年、人類が「原子力の平和利用」すなわち原子力発電の運用を開始してから66年が経過した。その間、世界中の原子力発電所で、大小さまざまな事故やトラブルが、公式に発表されたものだけでも40回以上発生している。
そのなかで、国際原子力事象評価尺度(INES)が定めるもっとも深刻な「レベル7」に分類される事故は2回ある。1986年にソ連時代のウクライナで起きたチェルノブイリ原子力発電所事故と、2011年、東日本大震災に伴なう大津波によって起きた東京電力福島第一原子力発電所事故だ。
長崎大学原爆後障害医療研究所に勤務する高村昇教授は、チェルノブイリと福島の両方の地で、被災した住民の医療支援、復興支援に長年にわたって携わってきた、世界でも片手で数えられるほどしかいない医師の一人である。
「私はもともと内科を専門とする医師でした。大学院生のときは、いま新型コロナウイルスの診断で話題のPCRを使った遺伝子診断を研究していました。しかし大学院修了後、自分の指導教授であった山下俊一先生が続けていたチェルノブイリの支援に同行する機会をいただき、それがきっかけで被ばく医療科学の道に入ったのです」

被災した福島の土壌の放射線量を、線量計で測定する高村教授。(写真提供:高村教授)
チェルノブイリ原発事故では、原子炉の爆発とその後の火災によって、大量の放射性物質が環境中に飛散した。30km圏内に居住していた約13万5,000人は、事故直後から強制避難を余儀なくされ、復旧作業にあたった作業員のうち、133名が急性放射線障害と診断され、その中で高線量の被ばくをした28名が急性放射線障害で亡くなったことが分かっている。
発電所内で復旧作業にあった作業者のうち、高線量の被ばくをした28名が急性放射線障害で亡くなったことが分かっている。一方で、土壌に飛散した放射性物質は草木に取り込まれた後、それを餌とする乳牛の体内で濃縮され、牛乳を飲んだ人々に体内被ばくをもたらした。その結果、1990年初頭から、チェルノブイリ付近に住む子どもたちに小児甲状腺がんの発生率の明確な上昇が確認されるようになり、その影響は今もなお続いている。
高村教授が指導を受けた山下俊一教授(現・福島県立医科大学副学長)は、放射線被ばくの研究における我が国の第一人者だ。山下教授は、1991年からチェルノブイリ原発周辺に暮らす子どもたちの甲状腺がんの調査にあたってきた。1995年からは、旧ソ連が核実験を行っていたカザフスタン共和国セミパラチンスクの核実験場周辺の調査活動でも、中心的な役割を果たしてきた。
高村教授は、1990年代前半から山下教授のもとで、チェルノブイリやセミパラチンスクの住民を対象に、健康影響の評価や、医療インフラ整備などを行うプロジェクトに参画した。1999年には、WHO(世界保健機関)に技術アドバイザーとして出向し、国際的な保健活動についても実地に学んだ。2000年に長崎大学医学部に戻ると公衆衛生学分野を研究し、2008年に現在の長崎大学原爆後障害医療研究所に着任した。東日本大震災が起きたのは、その3年後の2011年のことだった。
「私が福島に入ったのは、事故が発生して1週間後のことでした。現場は大混乱の状況で、住民の方々の多くは、『自分たちは被ばくしたせいで死んでしまうのではないか』『子どもたちや子孫に影響が出るのではないか』といった不安を抱えながら生活していました」
東日本大震災では、マグニチュード9.0の地震とそれがもたらした巨大な津波により、2万人を超える死者・行方不明者が発生した。津波は沿岸部にあった福島第一原発も呑み込み、原子炉の冷却システムを破壊し、原子炉建屋の爆発事故を引き起こした。
飛散した放射性物質の放出量は90万テラベクレル。チェルノブイリの520万テラベクレルに比べれば数分の一だが、気流に乗って拡散したことで広範囲の土地が汚染された。津波と原発事故によって避難を強いられた付近住民の数は、最大時には16万人以上にのぼった。

長崎大学の学生たちも実習で福島の被災地を訪れ、住民たちとコミュニケーションしながら復興のサポートに取り組んでいる。(写真提供:高村教授)
高村教授は、被ばくに怯える住民たちを前にした講演の冒頭で、自分が太平洋戦争で広島とともに原爆を投下された長崎で生まれ育ったことを話した。そして、幼いころから親や親戚に原爆の被害を聞かされてきたが、自分も自分の子どももまったく健康状態に問題がないこと、長崎でも広島でも世代間をまたぐ被ばくによる健康被害や遺伝的影響は確認されていないことを伝えた。
「それを聞いた福島の避難民の方々の顔が、パーッと明るくなっていくのが分かりました。実はそうした反応は、かつてチェルノブイリで出会った住民の方々も同じでした。チェルノブイリやセミパラチンスクの人々に、私が長崎から来たと伝えると、『その後、ナガサキはどうなったんだ? 無事に復興したのか?』と熱心に聞かれることがよくありました。『みんな健康に生活していて、街も復興している』と伝えると、みんな本当に安心した表情を浮かべました」
高村教授が専門とする「被ばく医療科学」は、一義的には「被ばくした患者の人々に対する治療と被ばくの評価」のことを指す。
だが、研究を実践するフィールドはそれだけではない。実際に事故が起こったときの「被ばくした人」および「被ばくの可能性がある人」の治療や検査を行うのはもちろんだが、「もしも自分が住む土地の近くにある原子力発電所で事故が起こったら、どのように行動するべきか」という住民に対する事前の啓蒙活動や、事故後の放射線による土地や環境の汚染評価および健康への影響評価も実施する。さらには、住民や被災地外の国民との、行政を巻き込んだ適切なリスクコミュニケーションも考える必要がある。そうした「社会医学」としての知見が、被ばく医療科学の専門家には求められると高村教授は言う。
「福島第一原発事故の前まで、そうした総合的な知見を持つ専門家の必要性が、日本ではほとんど認識されていませんでした。そのため災害被ばく医療のプロフェッショナルの育成も十分に行われておらず、だからこそ、私が長崎から非常に遠い福島まで行かなければならなかったわけです」

環境中の放射性セシウムの濃度を測定し、住民が一定期間暮らしたときの被ばく線量を予想するとともに、住民に配布された線量計の使い方を指導する。(写真提供:高村教授)
高村教授は、2011年の震災発生直後から現地に入り、復興支援のために一年のうち数ヶ月は被災地に滞在して調査を続けてきた。そして2013年4月には、長崎大学と、高村教授らが2011年12月から支援を継続していた川内村の間で包括協定が締結され、主に次の4つの支援が実施されることになった。
土壌等の放射性物質測定による、除染効果の評価。
食品・飲料水等の放射性物質測定を通じて、住民の安全・安心を担保すること。
健康相談や講演活動、検診等を通じた住民の健康管理。
保健医療、福祉活動などによる住民の健康増進。
「福島の被災地の中でも、川内村は最初に帰還が始まった地域です。私たちが川内村に設置したサテライトオフィスには、長崎大学の大学院を卒業した保健師の女性が常駐し、住民の方々の支援にあたりました。支援にあたる人間が外部から短期間だけやってきて、すぐに帰ってしまっては信頼が得られません。長崎から放射線科学のプロである20代の女性が滞在して、住民の方々と同じ空気を吸って、同じものを食べて数年に渡って生活する。それができたことは、住民の方々と良い関係性をつくるうえでたいへん大きな意味がありました」
支援する住民と同じ食べ物を食べることは、チェルノブイリで山下教授が実践し、高村教授が学んだ知見であった。原子力災害においては、住民の人々のメンタルヘルスを良好な状態に保つことが、非常に重要になると高村教授は言う。
「福島県民に、放射線の影響は遺伝するかとアンケートをとった結果、『遺伝すると思う』と答えた人が約3割いました。広島、長崎やチェルノブイリの知見から、そうした事象はほぼ心配する必要がないと分かっていますが、まだまだ知られていないのです。原子力災害の支援では、単に放射線の人体影響だけに気を配るのではなく、人々の感情の動きを含めた社会事象を予測し、幅広く対応することが必要となるのです」
地震発生から10年近くが経過した2020年現在も、福島では3万人を超える人々が故郷に帰ることができないままの状態にある。その多くは、福島第一原発に近いがゆえに、帰宅困難地域に指定された富岡町や大熊町、双葉町に住んでいた人々だ。放射性物質の除染活動によって線量が下がり、避難指定が解除された地域でも、全員が一斉に帰還しているわけではない。
「原発から約20 km離れた川内村は、帰還率が81 %ほどとかなり戻っていますが、数kmの地点にある富岡町は約1割、大熊町は1万人の住人のうち200人しか戻っていません。福島の復興はエリアによってフェーズがまったく違います。地域ごとのフェーズを認識しながら、復帰の支援を進めています」
富岡町は、原発の事故直後に住民全員が避難し、2017年の4月から帰還が始まった。富岡町は、原発のある双葉郡の中心的な街で人口も多く、商業や医療など社会活動の中枢を担っていた。富岡町が本格的に復興すれば、ほかの地域の復興にも波及する。そのため、高村教授らは、富岡町に対しても復興支援を行っている。
「住民とのコミュニケーションは『車座集会』を基本としています。講演形式で壇上から話をするのではなく、少人数で輪を囲み、一人ひとりが生活面で困っていることについて、自由に発言してもらうのです。放射線に関しては私たちが答え、『あそこの道路はいつ修理が終わるのか』といった行政面に関する質問は、一緒に参加している役場の方が答えます。車座集会を行うことで、住民のいろいろな問題を解決することができます」
富岡町では、地域の中学校でも授業を行っている。若い世代に安心して富岡に住み続けてもらうことで、地域の将来の担い手を育成することが目的だ。また2013年には、川内村の小学6年生が毎年長崎大学を訪れ、「復興子ども教室」という名称で、放射線についての基礎知識や、長崎が原爆からどう復興していったか、1991年の雲仙普賢岳の噴火の後、自然災害からどう復興したかを学ぶ取り組みも始めた。
高村教授は、福島の被災地とIAEA(国際原子力機関)、ICRP(国際放射線防護院)や海外の国際機関との連携を進めるとともに、海外大学の留学生を受け入れ、現地で放射線被ばく科学の教育を行う活動も積極的に推進している。
「川内村の食品検査場で、農産物の放射性物質の濃度を測定している職員の方に講師をお願いし、長崎大学の学生や留学生を指導してもらっています。実際に災害を経験し、乗り越えた方々が学生に教えることの重みは、他の何にも代えがたいものがあります。留学生にとっても非常に良い機会となっており、川内村が世界の災害対応を担う若い人材を育成する場となりつつあるのです。毎年多くの国内・海外の学生が、人口2,000人の川内村を訪れることで、地域も刺激を受け活性化しています」
また、産業復興のための支援の一環で、川内村の住民との共同研究として行っているのが「きのこマッププロジェクト」だ。川内村は以前からきのこの名産地として知られ、なかでもまつたけが抜群においしいことで有名だった。だが、放射性セシウムはきのこに濃縮するため、住民はきのこを採ってよいのか、判断に迷っていた。
「放射性セシウム濃度は、月日が経てば低下し、きのこもいずれ問題なく食べられるレベルになります。そこで私たちは、住民の方々に『きのこを集めてください』とお願いして、その線量を測り、採れた場所ごとに線量の濃度をプロットすることにしました。毎年秋に採れたきのこを測定し、春に住民に対して説明を行って、継続的に川内村のきのこの状態を観察することにしたのです。きのこに関するこうした持続的な研究は、チェルノブイリでも行われたことがなく、非常に意義があると感じています」
高村教授らは放射線の専門家だが、きのこに関しては素人だ。一方、川内村の農家の人々はきのこについて高度な知識を持っている。
「あるきのこの放射性セシウム濃度が不可解に高かったので、住民に尋ねたら、『これは腐葉土に固まって生える種類のきのこだ』と教えてもらいました。しいたけのような木に生える種類のきのこは線量が低いのに対し、腐葉土に生えるきのこは、土壌と葉っぱに積もった放射性物質の影響をダブルで受けるので線量が高く出るのです。この事実は、この調査で初めて分かった知見です。そんな風にお互いの専門知識を補完し合うことで、初めて分かったことがいくつもあります」

福島第一原発の事故からまもなく10年、その間、高村教授は復興支援に取り組み続けてきた。10年、20年先の「本当の復興」を見据え、これからも活動は続く。(写真提供:高村教授)
「災害・被ばく医療科学」という新しい学問について、高村教授は、「これまでの科学的、社会学的な知見と経験を総合的に踏まえ、災害サイクル全体の危機対応を準備し、復興を行うための必要なエビデンスを学ぶための学問体系」と定義する。
「この学問で得られる知見は、まさにいま、新型コロナウイルスのパンデミックという未曾有の事態にも応用が可能です。日本は災害大国であるからこそ、多くの専門家が求められます。私の将来の夢は、川内村や富岡町をはじめとする被災地出身の子どもたちが、長崎大学に入学して医師や災害対応の専門家となり、この地域の医療・復興を支えてくれることです。川内村の村長さんとも『そこまでは頑張りましょう』といつも言っています」と高村教授は目標を語る。
川内村の復興が始まって今年で8年。長崎大学を訪れて学んだ子どもたちが、高村教授の夢を叶えてくれる日も、そう遠くないはずだ。
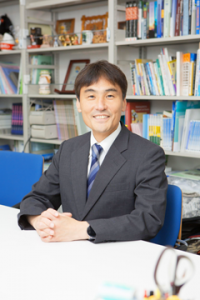

1962年、「原爆被爆者の後障害の治療並びに発症予防及び放射線の人体への影響に関する総合的基礎研究」を目的として設置された。残留放射能の測定、被爆者疾病の病理学的研究、放射線障害の発症機序の解明、白血病や放射線誘発癌の発症機序の解明と治療法の開発などを中心に総合的研究を展開してきた。チェルノブイリ原発事故、福島第一原発事故にもいち早く人材を派遣し、医療再構築とリスクコミュニケーションにあたった。現在も、福島県川内村に長崎大学の拠点を設置するなど、復興の支援を継続する。
【取材・文:大越裕】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png