

トマトは食卓で非常に馴染み深い植物だが、農業生産現場はある課題を抱えている。それを、科学の力で解こうとしているのが、筑波大学つくば機能植物イノベーション研究センターの有泉亨准教授だ。「ゲノム編集」という最先端技術を使って、研究成果を社会実装につなげる取り組みを紹介する。

研究用のトマトは、温室や研究室の中で栽培している。
トマトは世界的に、食卓で人気のある野菜のひとつだ。各種のビタミンをはじめ、栄養素や機能性成分を多く含み、健康にもよい。たとえば赤い色素の一つ「リコピン」は、がん予防などの効果がある。
その生産量は、生食用や加工用などさまざまな用途に向けて、世界175ヶ国で年間1億5,600万トン以上ある。果実を食する果菜類のなかで、もっとも多く生産されている。なお、トマトはナスやピーマンなどと同じくナス科に分類される。
このように、健康効果もあって人気のあるトマトだが、その生産現場には課題がある。それは、いかにして果実を実らせるかだと有泉准教授は語る。なお、植物が果実を実らせることを植物学の用語で「着果」という。
「通常、着果には受粉を伴う必要があります。トマト栽培においても、受粉を媒介するマルハナバチのような訪花昆虫を使うことが多いのですが、夏場は高温でハチの運動性が低下します。また、暑くなりすぎたり寒くなりすぎたり、極端な熱ストレスにさらされると、トマトでは花粉がつくられにくくなり、そのため着果不良が起こります。温暖化の進展で、特に夏場に、トマト栽培に適した温度を超えることが増え、着果不良が日本だけではなく世界的に見ても問題になっています」
そこで、ハチの代わりに着果を促すために使われるのが、「オーキシン」や「ジベレリン」といった植物ホルモンだ。植物ホルモンとは、植物の体内で、微量で生理活性を引き起こす化合物のことだ。植物のなかには、未受粉でもオーキシンやジベレリンのシグナルが活性化される影響で、果実が形成されることがある。受粉を伴わずに着果することを「単為結果(たんいけっか)」と呼び、トマトでもこの現象が起こることが知られている。
この性質を利用して、生産現場で、ハチの代わりにオーキシンやジベレリンが用いられている。スプレーで噴霧すると、受粉していなくてもトマトが実をならせるのだ。だが、この噴霧作業は農家にとって過酷な重労働となる。
「暑さでハチの運動性が低下する夏場に、農家は植物ホルモンを使うわけですが、トマトは温室で栽培されることが多く、夏場の温室は40℃近くになることもあります。ハチや植物ホルモンにより着果を促す作業が、トマト栽培のなかで1~2割を占めるとも言われていて、農業従事者の平均年齢が65歳を超えるなか、トマト栽培の省力化が望まれています」
有泉准教授の研究の柱のひとつが、トマトの単為結果のメカニズムを解明することだ。それにはその前提として、トマトがどのように着果するか、遺伝子や分子の働きを詳細に把握しておく必要がある。
トマトの着果の大きな流れを示したのが図1だ。ここで登場するのが、オーキシン(Aux)とジベレリン(GA)、エチレン(Ethylene)という3つの植物ホルモンと、「SlAA9」「SlDELLA」という2つの遺伝子だ。図中で、実線は活性状態を、破線は不活性状態であることを示している。
「未受粉の状態では、『SlAA9』『SlDELLA』の2つの遺伝子と、植物ホルモンのエチレンが活性化し、全体として着果を抑制しています。すなわち、これら3つの要素はいずれも着果抑制因子です。一方、受粉した状態では、オーキシンとジベレリンが活性化します。つまり、オーキシンとジベレリンが着果を促進するわけです。この働きが、分子レベルでも明らかにされています」
受粉後に、着果のスイッチを入れるのが、受粉によって合成されるオーキシンだ。オーキシンは、着果抑制因子である「SlAA9」を不活性化する。ブレーキ役の遺伝子の働きを止めることで、着果を促進しているのだ。
未受粉の状態で、SlAA9が担っていたのは、ジベレリンの合成を抑制する役割だ。SlAA9が、自身の働きでジベレリン合成を抑制するのと同時に、SlAA9が合成するエチレンの働きによっても、ジベレリンの合成が抑えられる。そのSlAA9が、オーキシンの働きによって不活性化され、その結果としてジベレリンが活発に合成される。ジベレリンは、着果を抑制していたSlDELLAを不活性化し、着果が誘導されるという流れだ。
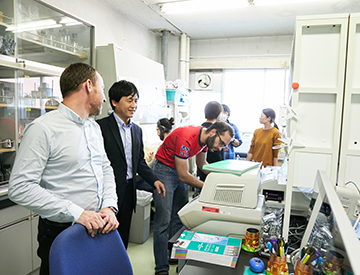
研究室には、海外からの研究生や学生も多い。
「オーキシンとジベレリンは、遺伝子発現をコントロールするだけでなく、子房細胞の成長にも影響を与えます。受粉によってオーキシンが合成されると、雌しべの子房が活発に細胞分裂を始め、それらの細胞がジベレリンの働きによって肥大化し、結果として子房が急激に発達して果実になっていくのです」
未受粉の状態でも、オーキシンやジベレリンの影響でトマトが単為結果するのは、こうしたメカニズムに裏打ちされている。2つの植物ホルモンの働きによって、着果を抑制していた「SlAA9」「SlDELLA」の2つのブレーキ役の遺伝子が不活性化し、着果が誘導されるのだ。
トマトの単為結果は、植物ホルモンによる外的要因だけでなく、遺伝子変異によっても発生する。そうした変異体のゲノムを解析し、どの遺伝子の働きによって単為結果が誘導されるかを突き止める研究が進んでいる。

「遺伝子の働きを突き止めたときは大きな喜び」と有泉准教授。
なお、「ゲノム」とは、DNAの塩基配列情報のすべてのことだ。2012年に、トマトのゲノムのほぼすべてが解読され、およそ34,000個の遺伝子存在が明らかになっただけでなく、ゲノム上での位置や構造も明らかにされた。こうした研究の蓄積があったからこそ、単為結果の変異体が、どの遺伝子の変異によって引き起こされているかにアプローチすることができる。
このトマトのゲノム解読は、世界の複数の研究機関で分担し、日本の研究機関も大きな貢献があった。日本の研究機関というのが、筑波大学ともつながりの強い公的研究機関である「かずさDNA研究所」だ。
一連の研究の進展により、MADS-boxという遺伝子ファミリーが、着果と大きく関わることが分かってきている。
「遺伝子が正常なトマトでは、着果時に、MADS-box遺伝子群の発現が減少します。MADS-box遺伝子群が着果を抑制する働きをしていて、なんらかのきっかけでMADS-box遺伝子群の発現が減少し、着果が進展するものと思われます。一方、単為結果する変異体では、MADS-box遺伝子群が機能欠損していることが突き止められています。着果のブレーキ役であるこれらの遺伝子が働かないことで、単為結果が誘導されるのです」
有泉准教授は、研究のもうひとつの柱が、単為結果トマトを遺伝子改変によってつくり出すことだ。着果や単為結果のメカニズムを明らかにするうえで得た知見が、新たな栽培品種の開発にも生きてくる。
2017年には、「ゲノム編集」という最新の遺伝子改変技術を使って、着果を抑制する遺伝子SlDELLAの配列を操作し、単為結果トマトを開発することに成功した。
広く使われているゲノム編集技術は、「CRISPR/Cas9(クリスパー・キャスナイン)」と呼ばれるものだ。これは、特定箇所を狙ってDNA配列を切断し、遺伝子を改変する。切断したDNAが修復される過程でDNAの配列が変わり、遺伝子の機能も書き換えられるのだ。
この技術は簡便なため広がりを見せているが、大きな弱点がある。DNAの配列を切断するため、それより後の配列が、遺伝子として意味をなさなくなることがあるのだ。DNAにはA・T・C・Gの4種の塩基があり、3つの塩基がひとかたまりになって意味をなしている。このひとかたまりの一部でDNA配列が切断されたり、後続に無意味なDNA配列が挿入されたりすると、遺伝子の機能が大きく損なわれてしまう。そのため、遺伝子の機能が大きく変わってしまい、トマトのさまざまな形質に影響が出ていた。
そこで、有泉准教授らの研究チームが採用したのが、神戸大学の西田敬二教授が開発した「Target-AID」という新しいゲノム編集技術だ。「Target-AIDを使えば、DNAが配列を切断することなく、特定箇所の塩基配列だけを置き換えることができます。後続の配列に影響を与えることなく、狙った遺伝子の機能だけをピンポイントで改変することができるので、他の遺伝子に与える影響を抑えることができます」
この技術を活用し、着果を抑制する遺伝子であるSlDELLAの機能をピンポイントで欠損させ、他の形質に影響を与えない単為結果トマトの開発に成功したのだ。実用化に向けて、研究がさらに進められている。
有泉准教授が農学を志したのは、高校生のころ、バイオテクノロジーに注目が集まったのがきっかけだ。自分でも遺伝子組み換え作物をつくってみたい。そう思って東北大学の農学部に進学した。それ以来、植物の研究に取り組み続けている。
イネやシロイヌナズナの研究をしていたこともあったが、トマトの研究を始めたのは、研究に対するある思いがあったからだ。
「科学技術が目指すのは、研究成果を社会に還元することだと考えています。トマトは民間企業との共同研究も多く、研究が新たな品種の開発に結びつきやすい。たとえば、単為結果の新たなトマトの品種を開発すれば、農業現場が抱える課題を解決することができます。研究成果を社会実装することを目指して、日々研究に取り組んでいます。民間企業と一緒に、社会実装に向けたディスカッションをしているときはとてもワクワクします」と有泉准教授は力を込める。
食卓は、農業従事者だけでなく、農学研究者の手によっても支えられているのだ。
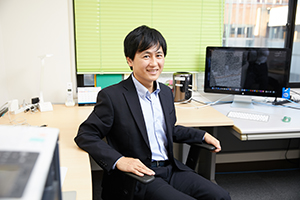

持続的な社会の実現に向け、フードセキュリティやエコセキュリティ等を支援する研究開発、産業化支援を推進するための研究センター。平成29(2017)年4月に設置された。中心は、植物における遺伝子機能解析を精力的に行っている「遺伝子実験センター」と、フィールドを活かした農業研究を推進している「次世代農業研究部門」。植物バイオテクノロジーと生物資源を基調とした基礎・基盤研究から応用・開発、社会実装までをワンストップで行う研究拠点を構築。食料や資源の安定的確保といった持続可能な社会の実現への貢献を目指す。
【取材・文:萱原正嗣 撮影:カケマコト】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png