

触媒とは、それ自身が変化することなく、ほかの物質の化学反応を助ける物質のことだ。多くのエネルギーや時間を必要とする反応や起こりにくい反応を、触媒によってより簡単に低コストで進められるようになれば、エネルギーや時間を節約し、これまでになかった素材を作り出すことができる。
北海道大学触媒科学研究所物質変換研究部門の福岡淳教授は、新たな触媒の開発に取り組んでいる。フードロスの削減につながる化学反応を加速する触媒や、これまで活用しきれていなかった素材から稀少で付加価値の高い素材をつくり出す触媒だ。
触媒は、生活のさまざまなところで活用され、私たちにとってとても身近な存在だ。たとえば、触媒の用途として現在最も多いのがガソリンやディーゼルエンジンの排ガス浄化である。自動車などの排ガスには、炭化水素や一酸化炭素、窒素酸化物などの有害物質が含まれている。
触媒は、これらを二酸化炭素や水、窒素といった無害な物質に変換する化学反応を助け、排ガスの浄化に役立っている。この他にもプラスチックの合成や燃料電池など、触媒は色々な形で私たちの生活を支えている、いわば縁の下の力持ちだ。
福岡教授が開発した「メソポーラスシリカ担持白金触媒」も、既に私たちの身近なところで使用されている。この触媒は、メソポーラスシリカという細かい孔が多数整列した素材に、白金の粒子を固定したものだ。エチレンという物質が二酸化炭素と水に分解される反応を助ける。
エチレンは植物から放出される成分で、野菜や果物、花の熟成や腐敗を進める作用を持つ。したがって、野菜や果物の鮮度を長く維持するためには、輸送・保管においてエチレンを効率的に除去する必要がある。
そこで役に立つのが、このメソポーラスシリカ担持白金触媒だ。エチレンを分解し、野菜や果物の鮮度を長く保つ効果があり、現在では同種のシリカ担持白金触媒が冷蔵庫の野菜室や漬物工場の野菜保管倉庫などで活用されている。昨今問題となっているフードロスの削減にもつながるだろう。
しかし、福岡教授ははじめから、野菜や果物の鮮度保持に役立てようと考えていたわけではない。「当初の目的はエチレンを酸化させてエチレングリコールをつくることでした」と、福岡教授は話す。
もともとこの触媒は、一酸化炭素を酸化して二酸化炭素にするという反応を進める触媒として開発されたものだった。これを別の反応にも活用しようと考え、着目したのがエチレンである。一酸化炭素とエチレンは触媒の反応上、似たような性質を持つ。そのため、一酸化炭素で有効だった触媒がエチレンでも応用できるかもしれないと考えたのだ。
エチレンの酸化は工業的に重要な反応の一つである。エチレンを部分的に酸化させるとエポキシドという物質ができ、さらに水を付加するとエチレングリコールができる。エチレングリコールは、ペットボトルの材料であるポリエチレンテレフタレートなど様々な素材の原料となる。
ところが、エチレンにこの触媒を用いたところ、部分的にではなく完全に酸化され、二酸化炭素と水ができてしまった。
「有用な化合物を作ろうとしたのに、これではエチレンをただ燃やしたのと同じです。石油を分解して製造したエチレンをわざわざ二酸化炭素と水に変えてしまう。高いものを安いものに変えるわけですから、ものを作るという意味では全然価値がない反応でした」
がっかりした福岡教授は、いったんこの研究をやめてしまい、2〜3年の間放置していたという。
「ところがあるとき、触媒の応用に関する論文や解説記事を読んでいて、エチレンの完全酸化が役に立つ分野があることに気がつきました」
それが先述した野菜や果物の保存である。
一般的に、エチレンの除去には、活性炭やゼオライトといった多孔質の材料が用いられる。これらはエチレンを吸着することによって除去効果を発揮するのだが、一定量吸着するとそれ以上効果を発揮しなくなり再利用も難しいため、定期的に交換する必要があった。しかし、触媒はそれ自身が変化することなくエチレンを分解し続けるため、一度設置すれば長期に渡って効果を期待できる。
そこに着目した福岡教授はこの触媒の研究を再開。白金以外の金属や、メソポーラスシリカ以外の素材も使い、さまざまな組み合わせを試みたが、白金とメソポーラスシリカの組み合わせが最も効果が高かったという。

シリカ担持白金触媒(プラチナ触媒)
さらに、温度条件を変えて触媒の効果を調べたところ、0℃の低温条件でも低濃度のエチレンガスを完全に除去することができた。一般的に化学反応は温度が低くなるほど起こりにくくなる。この、低温条件下で微量のエチレンガスを分解するという性能は、これまでに報告されていたどのエチレン分解触媒よりも高度なものだった。低温でも効果を発揮するということは、野菜や果物の保管・運搬時の低温条件でも活用できることになる。
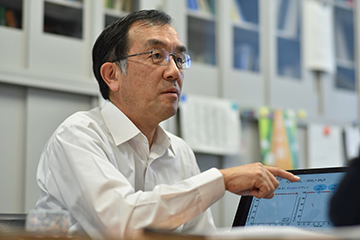
当時のことを思い出しながら、予想外の結果について語る福岡教授。
福岡教授は、一連の研究成果を論文にまとめ、そのなかで「この触媒は野菜や果物の鮮度保持に使えるかもしれません」と記して発表した。
「この論文のプレスリリースが新聞に取り上げられると、ある家電メーカーからこの触媒を冷蔵庫に使ってみたいという問い合わせがきました。ただ、私たちの実験室での試験と冷蔵庫とでは条件が違うので、そんなにうまくはいかないだろうなと半信半疑で触媒をお渡ししたんです。ところが1ヶ月後『良い結果が出ています。何より野菜がシャキッとしています』と連絡を受け、とても驚きました」
その後、共同研究を進め、1年半後にはこの触媒を搭載した冷蔵庫が発売された。その際に「プラチナ触媒」と命名され、これを基盤とした触媒が今でも国内外で販売される冷蔵庫に使われているという。
コンビニエンスストアチェーンからも、プラチナ触媒を使いたいとの申し出があった。そこで、漬物に使う野菜保管倉庫での実証実験を行った。
「バスケットボールのコートほどの広さで、高さは3階分くらいある大規模な倉庫です。冷蔵庫よりも随分大きな空間でしたから、本当に上手くいくのか、こちらも半信半疑でした。まずは試しに倉庫の隅に触媒を数百グラムずつ置いてきました。空間の広さに対してごく少量で、しかもただ置いただけでは意味がないのではないかと思っていました」
ところが2ヶ月後、触媒から離れたところに置いた野菜は腐敗が進んでいたのに対し、触媒の近くにあった野菜は腐敗が進んでいなかったとの連絡を受けた。そこで次は、空調の送風機に触媒を取り付けて試したところ、倉庫全体で十分な効果を発揮し、今後も本格的に活用していくことが決まった。これからは果物の鮮度保持や、輸送・運搬などにも活用していくことを検討しているそうだ。

北海道大学と平川ワイナリーが共同で作ったアップルシードル。
これに使うりんごの貯蔵にも、福岡教授の触媒が使われている。
福岡教授は、実用化だけでなく、反応機構の解明にも並行して取り組んでいる。
「この研究は応用・開発の方が先行しましたが、大学としては、反応の基礎的なメカニズムの研究も進めています。どういう仕組みでエチレンの分解を助けているのか、なぜ白金とメソポーラスシリカの組み合わせが良いのか、などです。仕組みを明らかにすることで、白金の量を減らす、あるいはより安い金属に置き換えるなどの応用や、より幅広い実用にもつながるはずです」と福岡教授は語る。現在は、先行研究やこれまでの知見をもとに仮説を立て、決定的な証拠を掴むべく分析を進めているところだ。
この研究と並行して、福岡教授が取り組んでいるもう一つのテーマが、木材の主成分であるセルロースや、カニやエビの殻に含まれるキチンなど、非食料バイオマスの活用だ。セルロースとキチンは、地球上で余っている炭素資源の1位と2位だ。どちらも十分な有効利用ができていない。
バイオマスは、化石資源に代わる次世代の炭素資源として注目されており、なかでも食料と競合しない非食料バイオマスの活用は、持続可能なものづくりを行ううえで重要な鍵を握る。福岡教授は触媒を使い、セルロースやキチンなどから化合物をつくり出し、有効利用するための研究も進めている。
そのひとつがセルロースを原料としたセロオリゴ糖の生成だ。セロオリゴ糖は、いくつかのブドウ糖が繋がってできたオリゴ糖の一種で、動植物の健康や成長を助ける効果がある。
オリゴ糖が腸内環境の改善に役立つことはよく知られている。これは、人間だけでなく、豚や牛といった家畜についても同様だ。セロオリゴ糖を配合した飼料を子牛や子豚に与えることで腸内環境を整え、下痢などの病気を予防・治療し、成長を促進できることが分かっている。また、セロオリゴ糖は植物の病害耐性を高める効果があるという報告もある。
その有用性が期待される一方でセロオリゴ糖は生成が難しく、現在は酵素を使ってつくることが多い。しかし、そのほとんどはグルコースが2個繋がったセロビオースと呼ばれるもので、3個以上のグルコースが繋がったセロオリゴ糖の生成は非常にコストがかかる。また、他につくる方法がないため、1gあたり100万円という非常に高い価格がついているものもある。福岡教授らの触媒はそれらをより効率よく、低コストで生成できるようにした。
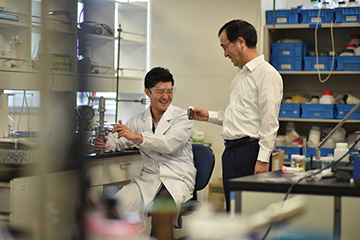
学生と話す福岡教授。右手に持つ瓶には触媒の材料となる活性炭が入っている。
高価で合成が難しい物質を作り出すこの触媒は、いたって普通の、ありふれたものだ。
「活性炭を空気中で焼き、表面を酸化させたものを使います。活性炭自体はそれほど高くはなく、しかもありふれた材料です。特別なものや高価なものでは使ってくれる人が少なくなってしまいますから、誰でも手に入れ、使えるようなものを触媒にしました。私は、触媒は使えないと意味がないと思っています。他の人に使ってもらうとか、実用でちゃんと有用に使えるところまで持って行きたい。この研究はあともう一歩のところで実用化できるところまで来ています」
現在は、北海道大学理学部の研究室と協力し植物への効用を調べ、化学メーカーとの産学連携により実用化に向けた試験を重ねているところだ。
研究テーマを選ぶ上で福岡教授が重視しているのが“人がやらないことをやること”だ。
「みんながやっていることは、競争も激しいですし、新しいことを見つけるのは困難です。だから、ほかの人がやっていない分野で、自分がアプローチできることを探してみることが重要です。セルロースの分解も、これまで酵素や液体の触媒では研究が行われていましたが、固体触媒を試している人はいませんでした。そこに着目し、固体触媒によるセルロースの分解を試したところ、液体触媒や酵素では難しかったオリゴ糖の生成が可能となりました」
セルロースやキチンのような固体の材料に触媒を使用する場合、硫酸のような液体の触媒や、水に溶ける触媒を使用することが多い。固体同士よりも、固体と液体の方が接触する面積が大きいため、より反応が起こりやすいからだ。
固体の材料に固体の触媒を作用させるには、両者が接触する面積をいかに増やすかが課題だ。福岡教授らの研究では、ボールミルという機器で触媒と材料を粉砕処理し、両者の接触面積を増やすことでこの課題を解決した。
「ただ、ボールミルを使った粉砕には電気などのエネルギーが多く必要になります。最初はバイオエタノールなどの燃料をつくろうとしていたのですが、燃料ではそれほど高い価値がつかないので、粉砕処理をしていては採算がとれません。そこで軌道修正をして、高付加価値の化学品をつくることにしました。バイオエタノールでは1リットルで100円にもなりませんが、このセロオリゴ糖は市場価格で1gあたり約100万円の価値があるので、大量のエネルギーを使っても十分利益が出ます」
行き詰まったら着眼点を変え、軌道修正することで、実用的な活用を見出す。この姿勢がエチレンの除去にも、バイオマスの分解にも活かされているようだ。
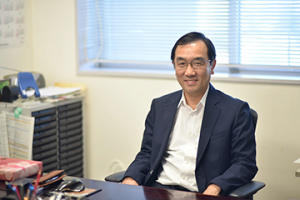

1943年に触媒研究所として設立。1989年に触媒化学研究センターとして、さらに2015年に触媒科学研究所として改組された。国内の触媒研究に従事する研究者の共同利用・共同研究拠点として研究・教育を支える一方、国外の触媒研究拠点とも連携し、積極的に学術交流協定を締結している。また、2010年からは名古屋大学物質科学国際研究センター、京都大学科学研究所附属元素科学国際研究センター、九州大学先導物質化学研究所と共に統合物質創成化学研究推進機構に参画。
【取材・文:平松紘実 撮影:島田拓身】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png