

2011年3月11日――。この日起きた東日本大震災と、その津波が引き起こした福島第一原発事故が、日本のエネルギー事情を大きく変えた。
2018年末時点で、60基ある原子力発電所の51基が停止状態だ。代わりに火力発電所の稼働が増えているが、化石燃料頼みのエネルギー政策には危うさがつきまとう。日本が石油の大半を依存する中東の政治情勢が不安定であることに加え、新興国での石油需要が増え、世界でCO2の排出量も増加し、資源獲得競争も起きている。こうした状況を踏まえ、2018年7月の最新のエネルギー計画では、「再生可能エネルギーの主力電源化」が明記されたが、天候頼みという技術的な課題を克服しきれてはいない。
日本のエネルギーのあり方を考えるにあたり、いまもう一度、原子力発電とは何かを学び直すことも必要だろう。東京工業大学科学技術創成研究院先導原子力研究所の千葉敏教授に話を聞いた。
原子力発電も、発電の原理そのものは火力発電と変わらない。福島第一原発事故のあと、そうした説明をテレビや新聞、ネットのニュースで見たことを覚えている人もいるだろう。
いずれの発電方式でも、水を沸騰させてタービンを回して発電させる。タービンとは要するに大きな羽根車のことで、その先の発電機を回す動力源だ。発電機は磁石とコイルからできており、コイルの中で磁石を、あるいは磁石のN極とS極の間でコイルを回転させると電気が流れる。すなわち、タービンの回転が磁石もしくはコイルを回転させる動力となり、電気を産み出している。タービンを回すエネルギー源は、水を沸騰させて蒸気にしたことで生じた風の力だ。
ではなぜ、原子力で水を沸騰させることができるのだろうか――。それにはまず、原子力とは何かを押さえておかなければならない。
「原子力とは、原子核反応によって生じるエネルギーのことです。原子核反応とは、原子核が崩壊したり分裂したりする現象のことを指します」と千葉教授は説明する。
「あらゆる物質は原子からできています。原子の中心には原子核があり、その周りをマイナスの電荷を持つ電子がまわっています。原子核は、プラスの電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子が結合してできています。そのため原子核全体としてもプラスの電荷を持っています」
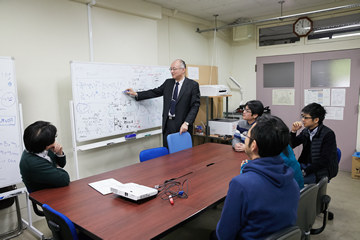
研究室所属の研究者や学生たちと議論する千葉教授。原子力というと無機的なイメージを持たれがちだが、その研究や技術は人が担っている。
ここまでは、高校ないし中学の物理・化学の復習だ。では、原子核反応とは一体何で、それによりエネルギーが生じるのはなぜなのだろうか。
ここで押さえておくべきは、「同位体」という概念だ。元素のなかには、陽子の数が同じであるのに中性子の数が異なるものが存在する。原子炉の燃料として使われるウランにも、同位体がある。自然界に存在するウランのほとんどの99.3%近くは、陽子92個・中性子146個のウラン238だが、中性子が143個のウラン235もごくわずか0.7%ほどの割合で存在する。ウラン235やウラン238の元素名の後の数字は、陽子と中性子の個数の合計値となっている。
「ウラン235に中性子1個をぶつけると、原子核が2つに分裂して2つの原子ができます。分裂してできる2つの原子にはいくつかのバリエーションがありますが、その陽子と中性子の個数の合計は233ないし234です。そして、この核分裂反応からは、2つないし3つの中性子が放出されます。つまり、反応の前後で、陽子と中性子は236個のまま、その数は保たれています。なのですが、反応の前後で質量は変化します。そして、その質量の変化からエネルギーが生じます。不思議に思われるかもしれませんが、これは、かのアインシュタインの有名な特殊相対性理論の公式『E=mc2』からの帰結です。Eはエネルギー、mは質量ですから、質量とエネルギーは等価なのです」
ここから後が、原子核反応によってエネルギーが生まれる本題である。
原子核内の陽子と中性子は、「核力」という互いを引き寄せる力でつなぎとめられている。「単体の陽子と中性子は、バラバラの状態であれば放っておいても離れていきますが、核力で結合した陽子と中性子を引き離すにはエネルギーが必要です。エネルギーは質量と等価です。つまり、陽子と中性子は核力によって結合すると、単体でいるときの質量の合計よりも軽くなります。同じようなことが、ウラン235の核分裂反応でも起こります。ウラン235に中性子をぶつけ、イットリウム95とヨウ素139に分裂し、その過程で2つの中性子が放出されると、陽子と中性子の総数に変化はありませんが、質量が反応前よりも軽くなります。その軽くなった分の質量が、エネルギーとして外部に放出されるのです」
このとき放出されたエネルギーは、分裂した2つの原子核の運動エネルギーとしてあらわれてくる。
「中性子の衝突によってウラン235の原子核が2つに分裂すると、2つの原子核の間で核力が働かなくなるのに加え、プラスの電荷を持つ原子核どうしが電気的に反発する『クーロン力』によって、2つの原子核が反対方向に加速して離れていきます。つまり、運動エネルギーが発生します。加速した2つの原子核は、周囲の原子とぶつかって、電子や原子核などを振動させます。この粒子の振動こそが熱の正体です。その熱で水が沸騰して蒸気になってタービンを回す動力になります」
核分裂によって、原子核の外部に放出されるエネルギーはきわめて膨大だ。その大きさを、化石燃料である石油を燃焼させたときのエネルギー量と比較して、千葉教授は次のように説明した。
「石油の燃焼とは、要するに炭素を燃焼させてCO2になる化学反応です。このとき熱エネルギーが生じるのも、実は反応の前後で質量差が生じているからです。中学・高校の化学で『質量保存の法則』を習ったかもしれませんが、これは厳密には正しくありません。ただし、その質量変化は反応前の炭素のおよそ100億分の1程度。それを計測する術がないから、質量が保存されているように見えますし、化学反応を考えるレベルではそう考えて支障はありません。一方、ウラン235の核分裂による質量変化は、元のウラン235の1000分の1程度です。炭素の燃焼による質量変化と、ケタがいくつも違うことが分かりますよね。その差はざっと1000万倍にもなります。それだけ、エネルギーへの転換効率にも優れています。つまり、少ない資源量で多くのエネルギーを賄うことができるのです」
そう言って、千葉教授は次のような資料を見せてくれた(左図参照)。
「この写真は、長崎県の五島列島の上五島にある石油備蓄基地です。海上に浮かべた5隻の貯蔵船に石油を備蓄しています。1槽の大きさが、長さ390m・幅97m・深さ27.6mです。ここに、国内で消費されるおよそ一週間分の石油が備蓄されています。比較がやや定性的ですが、これと同じエネルギーを産み出すのに必要なウラン資源は、手のひらに収まるほどごくわずかです。国内には、このほかにも海上・地上にいくつも石油備蓄基地があり、あわせて国内消費量の半年分ほどの石油が備蓄されています。これをどう考えるかですよね。原子力にもたしかに運用リスクはありますが、エネルギー効率や備蓄のことも考えて、エネルギーセキュリティを総合的に考えるべきではないかと思います」
話を原子力発電の仕組みに戻そう。ウラン235に中性子を衝突させると核分裂反応が起き、反応前後の質量差によってエネルギーが生じる。それが熱となって水を沸騰させ、蒸気の力でタービンを回して発電する。これがおおまかな流れである。
原子力発電は、質量はエネルギーと等価であるというアインシュタインの特殊相対性理論を抜きにしては語れない。いわば、20世紀の物理学の成果の賜物と言える。だが原子力発電は、20世紀物理学のもうひとつの大きな成果も前提にしている。それが量子力学であり、その発展にもアインシュタインが関わっている。
「光は波であると同時に粒子だという話を聞いたことがある人もいるでしょう。量子力学では、波だけでなくあらゆる物質が、波であり粒子であると考えられています。そんなバカなと思うかもしれませんが、それが量子力学の根幹です。量子力学が間違っているという証拠は見つかっていないので、ひとまずはそういうものだと理解してください。この量子力学の根幹の確立に多大な貢献をしたのが、マックス・プランクとアインシュタイン、ド・ブロイという3人の物理学者です。3人はいずれもこの一連の研究の成果に対してノーベル物理学賞を授与されています」

先導原子力研究所では、原子核反応や原子炉工学、エネルギー変換など幅広い研究に取り組んでいる。写真は、加藤之貴(ゆきたか)教授の研究室の研究設備。加藤研究室では、化学反応を利用して高効率なエネルギー変換・貯蔵技術の研究に取り組む。写っているのは、化学蓄熱材料の反応性を評価する一連の装置。
万物が波であり粒子であるとの意味は大きく2つあると千葉教授は言う。
「ひとつは、波は物質が存在する確率を表し、実際に物質を測定しようすると、それはどこにあるかが確定し、粒子としての性質が前に出てきます。ある瞬間に、粒子は一点にしか存在しえませんが、それ以外の瞬間では、その粒子は波の軌跡上のどこかに存在しうるということです。波は、粒子が存在しうる軌跡を描いていると表現することもできます。もうひとつの意味は、物質のエネルギーの高さが、その物質が波のように見えるか粒子のように見えるかに関わっているということです。エネルギーが低いと波の波長が長くなり、波のように見えるのに対し、エネルギーが高いと波長が短くなって粒子のように見えます。これが、中性子をウラン235の原子核にいかに衝突させやすくするかと関わってきます」
原子力を発電技術として応用するには、中性子をウラン235の原子核に効率的に衝突させなければならない。運任せでは、いかにも効率が悪い。その方法について、千葉教授は、弓道をたとえにこんな説明を始めた。
「五感で感覚的に理解できるマクロな古典物理学の世界では、ある物体を別の物体に衝突させやすくするには、的になる方の物体を大きくすればよいですよね。弓道を例に考えれば、的を大きくすれば当たる確率は上がるはずです。ところが、ウラン235の原子核の大きさは決まっています。ではどうするか。中性子の速度を遅くすると、実に1,000倍近くも的に当たりやすくなるという不思議なことが起こります。これは、五感が通用しないミクロな量子力学ならではのことです」
いったいどういうことなのだろうか。

先の写真と同じく加藤研究室の研究設備。この装置では低コスト高効率の水素製造を可能とする水素透過膜の製作、評価を行う。開発した水素透過膜を用いての核熱などを利用した燃料電池用燃料改質器、さらに大規模水素製造システム開発を目指す。
千葉教授は説明を続ける。
「物質は、エネルギーが低いと波長が長くなるという話を先ほどしました。波長というのは波の山と山の間の長さのことですが、波には横幅もあります。海の波がいい例ですが、幅のない波というのはありえません。波の横幅は、波長の数倍ぐらいという関係があります。つまり、波長の長い波は横幅も大きくなる。つまり、エネルギーを下げると波の幅も大きくなるわけです(図版参照)。中性子をウラン235の原子核にぶつけることを考えると、中性子のエネルギーを下げる、つまり速度を遅くすると、中性子はその分だけ的である原子核に当たりやすくなるわけです。弓道の例では、的を大きくすれば的に当たりやすくなりますが、原子核反応の場合は、的ではなく飛んでいく矢の方が大きくなっていると言えます」
極小のミクロの世界では、私たちの五感が通用しない不思議な現象が起きているのだ。
実は、原子炉に水を使っていることには、このことと関連して大きな意味がある。
核分裂反応によって放出された中性子はエネルギーが高く、そのままでは次の原子核とはなかなか衝突させられない。だが、現実の原子力発電では、この中性子のエネルギーを落とし、つまり速度を落として原子核に再び衝突させている。それにより核分裂の連鎖反応を起こして効率的にエネルギーを産み出している。このときの中性子の減速材として、水が適しているのだ。
「水はご存じのとおり、水素と酸素からできています。水素は陽子1個と電子1個からなります。水素の原子核には中性子は含まれておらず、単体の陽子がイコール原子核です。中性子と陽子はほぼ同じ質量を持っています。ここで、ビリヤードを思い出してください。ビリヤードの玉は、同じ大きさ、重さでつくられています。その玉が正面衝突すると、動いていた玉は静止して、止まっていた玉が動き出しますよね。つまり、質量が中性子とほぼ同じである陽子は、中性子のエネルギーを下げるのに最適なのです」
水は、核分裂反応による熱で蒸気に変わり、タービンを回す運動エネルギーを伝える媒体としての役割のほかに、中性子の「減速材」としての役割を担っている。さらには、水を循環させることで、原子炉の熱が高くなりすぎることも防いでいる。つまり、「冷却材」としての役割も担っている。原子力発電に水を使うことには、このように大きく3つの意味があるのだ。
原子核反応から生まれるエネルギーは膨大だ。そのエネルギーを制御するために、これまで数え切れないほど多くの研究者が、原子核反応に関する膨大な実験や理論計算を行ってきた。こうした原子核に関する膨大な実験データを「核データ」という。千葉教授は、核データを補足する理論研究に力を入れて取り組んでいる。
「原子炉を設計する立場からすると、核データの精度の高さは非常に重要です。実験データの蓄積はすでに十分にありますが、理論的に『なぜそうなるのか』は分かっていないことも多い。その理由を理論的に突き止めることができれば、データの信頼性をさらに高めることができます」
千葉教授の研究のもうひとつの柱が、使用済み核燃料に含まれる「長寿命核分裂生成物(LLFP)」への対策だ。
「原子核反応によってつくられる核分裂生成物のなかには、放射能を長期間出し続ける生命に有害なものもあります。長いものでは100万年も放射能を出します。それをいかにして安全に貯蔵するか。地下に貯蔵庫をつくっていますが、それだけの長期間、その貯蔵庫は構造物として、安全性を保証することができるのか。安全性への懸念も指摘されています。LLFPの保管リスクを減らすには、核反応によってLLFPを寿命の短いものにするか、放射能の影響が低いより安定なものに変えていく必要があります。そのためのシステムを構築し、実証実験に成功しました」
その成果は、米国Nature社が発刊する科学誌『Scientific Reports』のオンライン版に、2017年10月に掲載された。

原子核反応の仕組みを比喩を交えて分かりやすく、そして原子力研究の意義を力強く語る千葉教授。
福島第一原発事故から8年が経過し、いま私たちは、そして原子力研究者は、原子力とどのように向き合うべきか――。その問いに千葉教授は次のように答えてくれた。
「原発事故によって、大きな被害が出たこと、いまだに避難生活を余儀なくされている人が多くいらっしゃることに、原子力研究者として非常に申し訳ない思いがあります。原発には逆風が吹いていますが、エネルギーセキュリティの観点で、どのようなエネルギーを選択するのが最適か、冷静に考える視点を持ってほしいとも思います。運用面でのリスクを小さくする研究も進めています。原発の廃炉に向けても、原子力の知識や技術は不可欠です。世界に目を転じれば、中国やインド、UAE(アラブ首長国連邦)などは原発を推進していこうとしています。原子力を『分からないから怖い』と避けるのではなく、『分かったうえでどう向き合うのか』。それを一人でも多くの人に考えていただきたいと思っています」
原子力研究は、エネルギーだけでなく、他分野との連携や応用も盛んに行われている。核分裂研究は宇宙の元素がどのようにして合成されたかを理解することにもつながり、医療分野では放射線を活用したがん治療も導入されている。千葉教授は、それぞれの基盤となるデータを千葉教授が関連分野の研究者に提供している。つまり、原子力研究がさまざまな分野の研究や技術開発を支えているわけだ。そのためにも、原子力研究のバトンをつないでいくことが必要だろう。

愛犬レオの写真と。

エネルギー問題と地球規模の環境問題の解決を目指す原子力の基盤研究に取り組む。また、放射線応用を含めた原子力分野のフロンティアを開拓するグローバルな拠点研究機関として、米欧や旧ソ連諸国をはじめとして、世界各国の研究機関と連携して研究に取り組んでいる。2011年の福島原発事故以降は、除染をはじめ、福島復興に向けた取り組みにも務めている。
【取材・文:萱原正嗣 撮影:カケマコト】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png