

世界に活火山は約1500ある。日本はそのうちの111、世界全体の約7%が存在する火山大国である。2014年9月には御嶽山の噴火が大きな被害をもたらし、2018年に入ってからは新燃岳の噴火が続き、草津白根山でも噴火が起きた。ひとたび火山が噴火すると、長期にわたって人の暮らしにダメージを与える。被害を少しでも抑えるには、噴火後に起こる事態を可能な限り事前に把握しておく必要がある。そのために火山噴火の歴史を研究しているのが、日本に数人しかいない火山堆積学の研究者、新潟大学災害・復興科学研究所の片岡香子准教授である。

1991年6月に噴火したピナトゥボ火山。その規模と激しさは20世紀最大級だったが、噴火のピークを予測できたため、周辺地域の住人を避難させて人命は救われた。ただし、火山泥流の発生により被害者総数120万人に達する被害を出している。
public domain image from the United States Geological Survey.

ピナトゥボ火山の1991年噴火から4年後に発生した火山泥流により教会の半分(約6m)が火山土砂により埋まってしまった。実際には見えている部分の下に、元の建物が埋まっている。堆積した土砂はかき出さず、その上を生活面として使っている。
「火山噴火は、大きなニュースになります。御嶽山(おんたけさん)のときも、噴火後しばらくは毎日のようにメディアで報道されていました。けれども、噴火が収まって1年も経つとほとんど注目されなくなります」と、片岡准教授は噴火に対する世間の関心の移ろいぶりから話を切り出した。
火山が噴火すると、噴煙が派手に吹き上げられて噴石が飛び散り、火砕流が高速で流れ下る。見た目のインパクトが強い火山噴火は、マスコミにとっての格好のニュースネタだが、噴火そのものは一時的な出来事である。噴火が収まった後でも、火山の周辺に暮らす人たちには被害がもたらされうる。
被害の典型的な例が、1991年にフィリピン・ルソン島のピナトゥボ火山で起こった大噴火によってもたらされたもの。20世紀最大規模といわれるほどの激しい噴火は、10km3以上の火山灰や軽石を噴出した。これほどまでに激しい噴火は、周辺に暮らす人々の暮らしにどのような被害を及ぼしたのだろうか。
「ピナトゥボ火山の噴火では火口から大量の火山灰が放出されたうえ、これらの火山性の土砂が火山周辺に大量に積もりました。熱帯地域では毎年、雨季が訪れると雨が大量に降ります。雨水が火山の斜面に堆積した多量の火山砕屑(さいせつ)物、すなわち火山灰や火山性の土砂などにしみ込んで流れ出すため、毎年のように火山泥流が発生し、火山の周辺地域におびただしい量の土砂が流出して地表を埋め尽くしました。ピナトゥボの火山泥流や河川での過剰な土砂堆積は10年続き、人々の暮らしに大きな傷跡を残したのです」

御嶽山2014年噴火後の濁った河川。観測機器の設営を行っているところ。
片岡准教授らのグループは、戦後最悪の火山災害となった御嶽山の現地調査を、2014年9月の噴火直後から始めた。まず懸念されたのは、台風シーズン到来に伴う二次災害の発生である。実際に噴火後1週間ほどで台風に見舞われ、降雨によって火山灰などが流されて火山泥流が発生している。その後、降雪期に入っても新たな噴火の可能性があったため、噴火の熱による雪解け水が火山泥流を引き起こすおそれもあった。
こうした状況を随時把握するために片岡准教授らのグループは、御嶽山7合目付近で積雪期の気象・積雪観測を行った。さらに上流域に火砕流が流れ込んだ濁川(にごりがわ)において、同年11月から翌2015年5月まで水位のモニタリング、浮流土砂濃度、pH、水質汚染の指標となる電気伝導度などの測定に取り組んだ。
「川の水はひどく濁っていました。噴火の後だから仕方がないとはいえ、流域住民の方々にとって、水の濁りは心理的に不安要素となります。噴火後の2年間に20回以上現地調査に出向き、濁りを自動的に計測する機器やカメラなどを設置して観測を続けました」

片岡准教授は、物腰はとても穏やかながら、ひとたびフィールドに出ると、道なき道をも力強く進んでいくのだという。小柄な体は、バイタリティの塊なのだろう。
火山関連の研究では、噴火が発生するメカニズムに関心を向ける研究者が多い。たしかに、なぜ火山が噴火するのかという根源的な問いは研究心を刺激する。
だが、噴火から次の災害発生に至るまでのプロセス解明も重要な研究テーマだ。噴火によって発生した火山灰や火山性の土砂に、雨水や融雪などの影響が加わり、火山泥流が起こり被害をもたらす。火山泥流が発生するメカニズムをより詳しく解明できれば、噴火による被害を最小限に抑えられる可能性が出てくる。
「噴火から火山泥流発生へとつながる一連のプロセスを総合的に理解するには、複数の学問領域におけるある程度の知見が必要です。火山そのものに関する知識は言うまでもなく、堆積学の知見に基づいて土砂の動きや泥流の流れを解析したり、水文学により流域全体での水と土砂の流れがもたらす影響を把握する必要があります。一方で、火山活動によって形成された地形を理解するには地形学の知識が欠かせません。このように、火山によって引き起こされる現象を理解するには、広範囲にわたる複雑なプロセスを総合的に見ていく必要があります。私の知る限り、これら複数の学問領域を、幅広く研究対象としている研究者はあまりいません」
火山周辺地域の地形は、過去の火山活動によって形成されてきたものだ。噴火時と噴火後に山頂付近から流れ出た土砂は、火山泥流という短時間の現象を引き起こすだけでなく、河川の流れによって、長い時間をかけて地層の中に固定されていく。そのため、火山周辺の地層を読み解けば、過去にどのような火山泥流が起こったのか、また火山土砂の流域への長期的な影響を、ある程度推測できる。
地層とはいってみれば、火山活動の過去帳である。そこに刻まれた歴史を読み解けば、次の噴火の際に起こる現象をある程度予測するための基礎資料となる。
「さまざまな学問分野において確立されたアプローチを組み合わせ、多面的に活用しなければ解明できない事象があります。それを何とかして解き明かしたい。私が取り組んでいるテーマは、単一の学問領域を掘り下げるだけでは解明できません。とはいえ複数の領域を一人で掘り下げるのは無理ですから、『広く、可能な限り深く』とならざるを得ません。実際の研究活動は、各学問をつなぐ通訳的な仕事と言ったほうがよいでしょう。けれども、いくつかの学問領域を横断することで見えてくる世界が確かにあるのです」
噴火が引き起こす災害を防ぐためには、学問領域にとらわれることなく、噴火後に火山泥流が引き起こされる一連のプロセスを理解しておかなければならない。大きな被害をもたらしかねない火山噴火の全体像を、誰かが的確に理解しておくことは社会的に必要である。

安達太良火山西麓での火山泥流堆積物を探査する、災害・復興科学研究所が所有する地中レーダー探査機器(GPR)。
片岡准教授は、現在から数万年前ぐらいまでの比較的新しい地層を調査対象に定めている。これぐらいの期間であれば、地層に残された記録を丹念に読み解いていくことで、過去の出来事をある程度克明に再現できるのだ。
地下に埋没した地層構造を広域に調べるには、最新鋭の「地中レーダー探査機(Ground Penetrating Radar: GPR)」を使う。地中に向けて電磁波を発射し、内部からの反射波を計測して地質構造を解析する。解析結果を読み解けば、堆積構造が明らかになる。火山泥流や火砕サージによってつくられた地層なら、それができたときの流れの方向や速さなどを解析できる。火砕サージとは、火砕流に似ているが火山ガス成分を多く含むためより高速で流動する現象のことだ。地中レーダー探査機(GPR)の性能は近年とみに向上しており、地中の様子をより克明に解析できるようになっている。
このGPRを活用しながら、過去数万年ぐらいまでの間に起きた火山泥流を調べ、一回あたりの火山泥流で動いた土砂の量などを推測する。地層と地形から読み取った情報を複数領域の学識を駆使して解釈すれば、過去の噴火時に発生した火山泥流の動きや火山土砂流出の過程をある程度再現できる。
「過去に起こった現象を理解できれば、その知見は今後の災害に備えたハザードマップづくりに活かせます。仮に今後、どこかの火山が噴火するとして、噴火に伴う火山泥流の動きなどを事前に掴めていれば、噴火時の避難行動にも活かせるはずです」
火山噴火により、過去の噴火でつくられたカルデラ湖が大規模決壊を起こし、破局的な洪水が発生することがある。片岡准教授は以前、日本でも代表的なカルデラ湖である秋田・青森の十和田カルデラから奥入瀬川流域と、熊本の阿蘇カルデラから白川流域を対象とした調査・研究に取り組んだことがある。カルデラ湖決壊が引き起こした洪水について、堆積学的・地形学的アプローチと古水文学的解析を駆使した復元をおこなった。
「堆積物の分布や、地図上と実測量に基づく地形・地質のデータから、洪水が引き起こした侵食・運搬・堆積量を見積もりました。その結果、阿蘇カルデラと十和田カルデラのいずれにおいても、これを起源とするとするカルデラ湖決壊洪水のピーク流量は、数万から数十万m3/sであったこと、その流れにより堆積した土砂は1.4km3以上と計算されました。このときの計算によるひとつの成果として、奥入瀬川流域にある傾斜扇状地や段丘などの地形と堆積物は、現在の河川流の数千倍から数万倍程度の流量を持つ、ほぼ1回の大規模洪水によって形成されたことが分かりました」

道なき道を進み、さらに崖を登って地層観察する片岡准教授。地道な観察を繰り返すフィールドワークが研究の第一歩となる。
片岡准教授の研究は、常にフィールドワークから始まる。
まずは露頭と呼ばれる、地質や岩石が露出している部分を探して地層を観察する。地層を見る際に必要なのが、火山学や堆積学の知識である。地層中の粒子の並び具合を調べ、粘土の混じり具合などを見れば、過去に起こった泥流の流れを復元できるうえ、石が動いた速さまで分かるという。地層に含まれる火山性物質を調べれば、マグマの噴出を伴う噴火だったのか、あるいは水蒸気噴火だったのかも見極められる。
「次にもう少し大きなスケール、具体的には数百メートルから数キロぐらいまでの範囲で地形の状態を調べていきます。さらに、噴火の痕跡が秘められた地層と地形を上流から下流まで俯瞰的に見れば、過去の状況が浮かび上がってくるのです。一方では顕微鏡レベルの観察も欠かせません。地層中に含まれる粒子を細かく見ていくと、それがいつの噴火によるものかを特定できる可能性があります」

沼沢火山からの巨大せき止め湖決壊洪水による堆積物(高さ20mの崖)。巨大な礫(つぶて)を含み、大規模な堆積構造が見られる。
顕微鏡による観察でもわからない場合は、化学組成分析を行う。目で見えるマクロレベルから、機器を使って精密解析するミクロレベルまで。マルチスケールでの精査が、過去の噴火の全体像をよみがえらせる。
火山学、地形学、堆積学、水文学に化学や物理学の知見まで援用しながら、細部の要素情報を丹念に積み上げて統合し、より大きく複雑なシステムを理解する。火山噴火が引き起こす一連の事象を理解するには、マルチスケールでの分析と多様な学問分野の専門知識が求められるのだ。
ただし、フィールドワークで得られるデータは、長い歴史の中でみれば特定の時点における単発のデータであり、そこには不確定要素が紛れ込まざるを得ない。そうしたデータの偏差をいかに補整して、実態を解き明かすのか。
地層観察から得られた結果を補う手段として、コンピュータシミュレーションも重要な役割を果たす。片岡准教授が観測や観察で得たデータを提供し、シミュレーションを実施する。その結果、新たな視点が生まれることもある。このようにして、火山堆積学が取り組むべき課題は広がっていく。
片岡准教授は、物事の根本的な理屈を突き詰める思考を何より好む。ところが地学科に進んで取り組んだフィールドワークは「割り切れないことばかり」だったという。数学も地学も同じサイエンスでありながら、地学にはあまりにも割り切れないことが多い。しかも、過去の出来事を論理的に再現したとしても、本当にその通りだったかを確かめる術がない。
「それでも歴史を遡って可能な限り論理的に追究していくのが地学です。不確実性の中でも最も理路の通った説明を求めるとどうなるのか。一人で悪戦苦闘している内にこうした研究もおもしろいと思えるようになりました」
卒業論文のテーマを考えているとき、指導教員から「地形学と地質学を合わせると、興味深い内容がわかるはず」と指導を受けた。テーマとして取り上げたのは、三重県鈴鹿川流域の段丘構成層である。この地域を、地形学から捉えた先行研究と地質学から調べた先行研究の両方の視点から見たことが、今の研究につながる原体験となっている。

さまざまな学問分野の文献を読み込み、総合的に現象を理解する姿勢が求められる。
その片岡准教授は今、自らの専門を「火山堆積学」と呼んでいる。純粋火山学でも純粋堆積学でもない。地質学と地形学の素養の上に、火山学と堆積学の2つの学問領域を積み上げて、火山現象の歴史を復元して総合的に理解する。同じスタイルで研究を進めている仲間は、日本にほとんどいない。
「とはいえ、決して孤立しているわけではありません。自分がマルチリンガルなだけに、どの分野の専門家とも共同研究できるのが私の強みです。海外では似たような研究をやっている人も多いので、彼らとの論文を通じた交流から学べることも多くあります。そもそも地層から過去のイベントを復元するノウハウについては、海外の研究者が書いた論文を読んで知りました。これは自分にとっては目から鱗が落ちるような経験でした」
研究者が少ない分野だが、取り組むべきテーマはいくらでもある。火山噴火史に加えて、片岡准教授が取り組む火山泥流史が整備されていったとき、火山噴火の評価が変わり、噴火の予知や災害対策のあり方が大きく進歩することだろう。

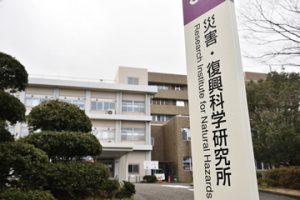
中越地震などの災害研究をはじめ、日本海側ラインや環東アジア規模での災害・復興科学の研究拠点として、大規模な複合連動災害の学理や対策の研究に取り組んでいる。自然災害と復興に関する課題解決に向けて、幅広い分野が連携した研究の実施と、その成果の社会還元を特長として、環境動態研究、複合・連動災害研究、防減災技術研究、社会安全システム研究の部門を備える。
【取材・文:竹林篤実 撮影:大島拓也】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png