

ひところSNSを賑わせた「ALSアイスバケツチャレンジ」を覚えているだろうか。マーク・ザッカーバーグやビル・ゲイツらの著名人が、バケツに入った氷水を頭からかぶり、その様子を動画撮影してSNSなどで公開していた。難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)への理解を深め、寄付を募るチャリティー活動である。
一度発症すると一生治らない、そんな神経難病ALSに苦しむ人を助けたい。名古屋大学環境医学研究所の山中宏二教授は、突き動かされるような思いに駆られて研究に取り組む。着目したのは意外な細胞だった。
ALSは不治の病である。中高年に多い疾患で、発症すると筋肉を動かす全身の運動神経が、徐々に死んでいく。まず手足が麻痺し、続いて言葉を話せなくなり、やがて食べることも困難になる。発症から数年後には、呼吸をつかさどる筋肉までが麻痺してしまい、そうなると人工呼吸器なしでは生きていけない。病状が確実に悪化する一方で、感覚や記憶、思考能力は正常に保たれるため、患者は病魔の進行を自覚しながら生きなければならない。この残酷な病に苦しむ患者は、日本に約9,000人、世界で約12万人いる。
ALSを発症するメカニズムは未だ解明されておらず、今のところ満足できる治療法はない。患者の約1割は遺伝性(遺伝性ALSもしくは家族性ALS)だが、残り9割の患者に遺伝子の異常は見つかっていない(孤発性ALS)。つまりALSを発症するリスクは誰にでもあるのだ。
ALSは運動神経に障害が起こって発症する。だから、ほとんどの研究者は、運動神経細胞をターゲットに定めて研究に取り組んでいた。
「けれども、当たり前の話ですが、運動神経細胞は単独で活動しているわけではありません。もしかすると、まわりの細胞もALSと何らかの関わりを持っているかもしれない。そんな疑問から研究を始めたのが、10数年前のことでした」と、山中教授は、研究のスタートを振り返る。
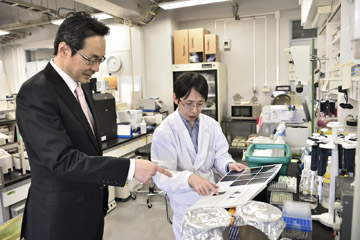
教員や学生と実験ノートを見ながら、実験結果と今後の進め方について議論する。今では教授自らが実験を行うことはないものの、これまでの経験に基づいたアドバイスは、研究者にとっての貴重な指針となる。
山中教授が目をつけたのは、運動神経細胞を取り巻くグリア細胞だ。グリア細胞は神経細胞そのものではないが、神経系を構成する細胞であり、脳神経の機能調節など重要な役割を担っている。ALSとの関わりについては以前から、その病巣において、グリア細胞が増加あるいは著しく活性化するなどの知見が明らかになっていた。
「ただ当時は、グリア細胞の異常はあくまでも、運動神経細胞が死ぬために引き起こされる二次的な現象と考えられていました。しかし、本当にそうだろうかと疑問を感じたのです。因果関係が逆とはいえないにしても、グリア細胞の増加が、病状に何らかの影響を与えている可能性もある。当時の最先端の研究に、運動神経細胞の死を抑制する薬剤をALSマウスに投与した研究がありました。モデルマウスの寿命はある程度延長しましたが、治療効果は十分とは言えませんでした。つまり病状の進行には、運動神経細胞死以外の何らかの要因が関わっている可能性が否定できない。その要因はグリア細胞ではないかと考えたのです」
グリア細胞に目をつけた山中教授らの研究チームは、ALSの進行に2つのグリア細胞「アストロサイト」と「ミクログリア」が深く関わっている事実を突き止める。
研究チームが目をつけたのは、以前からヒトの遺伝性ALSの原因遺伝子のひとつとして知られていたSOD1遺伝子である。この遺伝子が発現して生成されるタンパク質SOD1は、細胞内において活性酸素を解毒する酵素として働く。その遺伝子が変異すると、SOD1タンパク質の構造が異常になり、神経細胞を傷害すると考えられている。
「ポイントは、変異型SOD1遺伝子が影響を及ぼす範囲です。この遺伝子は、運動神経細胞だけでなく、グリア細胞など運動神経細胞のまわりの細胞にも作用しています。だとすれば、グリア細胞にも何らかの異変が起こっているのではないか。そう考えて変異型SOD1遺伝子の働きを調べる研究プロジェクトを開始したのです」

患者を一人でも多く救いたい。だから山中教授は、100万人の患者を救える可能性のある研究者の道を選んだ。
ALSの研究では、ALSを引き起こす要因となる遺伝子と病態の関係を調べるため、特定の変異型遺伝子を導入したマウス(ALSモデルマウス)が使われる。山中教授らのプロジェクトでは変異型SOD1遺伝子の影響を調べるために次の3種類のALSモデルマウスが作製された。すなわち運動神経細胞、アストロサイト、ミクログリアのうち、どれか一つの変異型SOD1遺伝子を取り除いたALSモデルマウスである。つまり運動神経細胞は正常でアストロサイトとミクログリアに異常を持つマウス、アストロサイトが正常で他の二つが異常、ミクログリアが正常で他の二つが異常な3タイプのマウス、これらのモデルマウスが、研究を大きく前に進めた。
運動神経細胞から変異型SOD1遺伝子を取り除いたマウス(つまり運動神経細胞のSOD1遺伝子が正常なマウス)では、そもそもALSを発症しないのではと期待されたが、ALSを発症し、病気の進行速度もほとんど変わらなかった(ALSの発症時期が遅くなりはした)。
次にグリア細胞のひとつであるアストロサイトから変異型SOD1を除去すると、病気の進行が約2.2倍遅くなり、生存期間も約20%伸びた。この結果から、運動神経細胞とミクログリアに異常があっても、アストロサイトが正常なら、病気の進行が抑制される可能性が示唆された。
さらに変異したミクログリアとALSの関わりも明らかになった。SOD1遺伝子の変異により病的変化を起こしたミクログリアからは、一酸化炭素や炎症を引き起こすタンパク質など神経障害性の物質が放出されていた。これらの有害物質は運動神経の神経炎症を引き起こし、その結果としてALSが進行する。だがアストロサイトが正常であれば、ミクログリアの活性化を抑えることができ、病態進行を抑制できる。
研究結果からわかるのは、アストロサイトやミクログリアがALSの進行を遅らせるターゲットになりうること。これらの細胞内で起こっている分子の変化を明らかにできれば、治療のターゲットとなる分子を同定できる。ALSの発症そのものの抑制や完治は難しいにしても、その進行を遅らせる可能性を示された。この研究成果は、2008年に英国の科学雑誌『Nature Neuroscience』オンライン版に掲載された。
次に山中教授らの研究チームが着目したのは、孤発性ALSの病巣に異常に蓄積しているタンパク質TDP-43だ。このタンパク質とALSの関わりが新たな研究対象となった。
研究チームはまず、TDP-43遺伝子に変異がある遺伝性ALS患者の臨床情報の解析に取り組んだ。ポイントは、変異TDP-43タンパク質の「半減期」である。正常なタンパク質は合成と分解を繰り返し、常に新しいものに置き換えられている。「半減期」とは、合成されたタンパク質の半分の量が入れ替わるまでの時間である。
解析の結果、ALSの発症年齢が早い患者ほど、変異TDP-43タンパク質の半減期が長くなり、変異TDP-43タンパク質が安定化する傾向が明らかになった。
変異TDP-43タンパク質のように半減期が長くなると、どのような問題が起こるのか。つくられたタンパク質が代謝することなく、長い間細胞内に溜まり続けてしまう。こうして細胞内に蓄積した変異TDP-43タンパク質が問題を起こすのだ。
「溜まった変異TDP-43タンパク質は、やがて切断され、あるいは不溶化して神経細胞に害を与えます。これは遺伝性ALSに関して明らかにされたメカニズムですが、孤発性ALSにおいても、変異TDP-43タンパク質の蓄積が、ALS発症に関わっている可能性が考えられます。問題は、変異TDP-43タンパク質の蓄積から、運動神経細胞の変性に到るまでの詳細なプロセスです。この機序を解明できれば、ALSの発症メカニズム解明や治療薬の開発が進むと期待できます」
続いて教授らのグループは、アストロサイトから分泌されるタンパク質の一種TGF-β1がALSの進行に関与していることを突き止めた。TGF-β1は本来、炎症を抑えるほかグリア細胞や免疫細胞の分化、組織修復など有用な機能を担っている。一方でALS患者の脳脊髄液中では、TGF-β1が増加することも以前から知られていた。
「まずALSモデルマウスやALS患者の脊髄組織を調べたところ、組織内のアストロサイトにTGF-β1の増加が見られました。そこで脳と脊髄のアストロサイトで、TGF-β1の産生量を増やすように遺伝子操作した新たなモデルマウスを作製しました。その結果、TGF-β1を増加させたALSモデルマウスでは、発症後の進行が速くなり、生存期間が短くなりました。一方、モデルマウスにTGF-βシグナル阻害剤を投与してTGF-β1の産生を抑えると、マウスの生存期間が延びました」
TGF-β1は本来有用なタンパク質だが、アルツハイマー病では神経炎症を引き起こすことがすでに知られていた。山中教授らはALSにおいても、その増加がALSを進行させる要因のひとつであることを明らかにしたのである。
遺伝性ALSは、遺伝子の変異によって引き起こされる。では孤発性ALSは、どのようなメカニズムで発症するのか。山中教授らのグループは、運動神経細胞のエネルギーに着目した。
「数ある神経細胞の中でも、もっとも大きいのが運動神経細胞です。たとえば腰から延びている運動神経などは、足の指先まで伸びており、その長さは、神経突起の末端まで含めると1メートルぐらいになります。これに対して、脳内の神経細胞は、長くてもせいぜい10センチぐらいに過ぎません。この長さの違いに注目してたどり着いた研究テーマが、細胞へのエネルギー供給です。大きな運動神経細胞は、より多くのエネルギーを必要とするはず。だとすればエネルギー不足によって、運動神経細胞の異常が引き起こされる可能性があるのではないか。細胞内でエネルギー産生に関わっている器官はミトコンドリアです。そこでALS患者のミトコンドリアを調べてみました」
この研究で明らかになったのは、細胞内の小胞体とミトコンドリアの接触部「小胞体・ミトコンドリア膜間領域(Mitochondria-Associated Membranes:MAM)」の崩壊が、ALS発症を引き起こすまでのプロセスである。
ミトコンドリアでは、カルシウムイオンがエネルギー産生に使われる。カルシウムイオンは通常、小胞体からMAMを経由してミトコンドリアに供給される。そのためMAMが崩壊すると、ミトコンドリアへのカルシウムイオン供給が滞り、細胞を維持するのに必要なエネルギーが不足してしまう。
「MAMの崩壊を引き起こすのは、2つの遺伝子であることを突き止めました。ひとつは遺伝性ALSの原因遺伝子として知られるSOD1、もう一つはMAMに存在して作用するSIGMAR1です。これらの遺伝子が変異することで、MAMの崩壊を引き起こしています。そのためミトコンドリアでのエネルギー産生が十分に行われなくなり、運動神経細胞に必要なエネルギーが供給されず異常を引き起こすのです」
この山中教授らのグループの研究成果は、世界初の知見として評価され、欧州の医学誌『EMBO molecular medicine』オンライン版に掲載された。
アストロサイトに関連して、次に山中教授らのグループが着目したのが、多くの生物が先天的に備えている「自然免疫反応」である。ALS病巣に対して、自然免疫はどのような反応をしているのか。ALSにおける自然免疫反応に関する研究報告は、これまでほとんどなかった。そこで教授らのグループは、自然免疫が本来の機能を発揮していないためALSが進行する可能性を調査した。
「自然免疫反応においては、そのスイッチを入れるセンサー(Toll様受容体と呼ばれる)があります。このセンサーが病原体特有の糖脂質や核酸などを認識するとスイッチが入り、『MyD88』もしくは『TRIF』という分子を介して感染防御反応が起こります。この2つの分子を欠損させたALSモデルマウスを作製してみたところ、TRIFを欠損した場合のみALSモデルマウスの生存期間が著しく短くなりました。」
TRIF欠損マウスでは、なぜALSの進行が加速するのか。その謎を解く手がかりは、TRIFが備えているもうひとつの機能にあった。
TRIFは、病原体に感染した細胞に自己細胞死(アポトーシス)を促し、病原体の伝播を防ぐ役割も担う。TRIFを持つALSモデルマウスでは、異常なアストロサイトがアポトーシスによって除去されたのに対し、TRIFを欠損させたモデルマウスでは、異常なアストロサイトが十分に除去されなかった。異常なアストロサイトは、正常なアストロサイトより大型化しており、活性酸素を大量に放出する。それによって運動神経細胞に害を及ぼし、ALSの進行を加速させるのだ。
従って自然免疫分子TRIFの機能を活性化させれば、異常なアストロサイトのアポトーシスを促し、ALSを改善する治療法の開発につながる。ALSの新たな治療法開発の道筋を示す研究成果は、英国科学誌『Cell Death & Differentiation』電子版に掲載された。
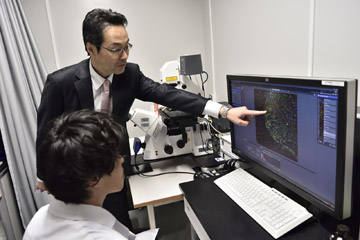
実験により得られた画像結果を見ながら、その解釈を研究員と検討する。
山中教授はさらに、ALSでの研究成果を他の神経疾患に応用する研究も進めている。
「ALSで取り組んでいるような神経炎症を標的とした治療法開発は、神経炎症が病態に関わることが最近注目されているアルツハイマー病にも応用可能と考えています。仮にアルツハイマーの進行を10年遅らせることができればどうなるでしょう。何もしなければ75歳で発症していた人が、85歳まで健康に暮らせるのです。アルツハイマーを発症すれば、介護を含めて家族や社会的な負担が極めて大きいことを考えれば、その発症を遅らせるのは社会的に大きなインパクトがあります。5年遅らせるだけでも、世界的に大きなメリットをもたらすのではないでしょうか」
山中教授が研究の道へと進んだきっかけは、祖母の脳梗塞である。教授が高校2年のとき祖母は脳梗塞で倒れ、その後手足の不自由な状態で闘病生活が10年ほど続いた。そのとき担当してくれた若手医師の献身的な姿を見て、医師の仕事に憧れるようになった。
脳の病気に興味をもったのは「ちょうどそのころに、神経難病の遺伝子が明らかにされつつあり、京都大学を卒業する直前にアルツハイマー病を引き起こす最初の遺伝子がわかった」からだという。
京都大学大学院在学中には神経内科領域の基礎研究を究めるために、生化学の研究室に学内留学し生化学や分子生物学の研究に取り組んだ。異常なタンパク質を分解するメカニズムが、神経変性疾患の研究に役立つと考えたのだ。その後アメリカでの留学体験が、今に至る道を開いた。
「留学時の同僚たちは、その多くが自分の研究室を持って独立しました。彼らの姿を見て、私も研究者として独立したいと強く思いました。日本に戻って医局に所属する臨床医になれば、自分のやりたい研究を続けるチャンスは限られています。臨床医として一生かけて診る人の数は限られています。けれども研究者として成果を出せれば、多くの人を、それこそ何百万人もの患者さんを救える可能性がある。幸運にも、理化学研究所で小さいユニットながら、研究室のトップとして活動する機会に恵まれ、それからALSの研究を本格的に進めました」

研究の基本は、新しく発表された論文をチェックすること。毎日、数多くの論文に目を通し、重要な内容が含まれている論文は熟読する。
理化学研究所で、いくつものALS研究の成果を出した後、2013年に名古屋大学環境医学研究所に移り、やがて所長を務めるようになった。所長としての役割については、次のように語る。
「研究所では、以前は特殊な環境における医学を研究していました。今は現代の医学研究を牽引する考え方に基づいて、ヒトの体全体を『環境』と捉え、人体の環境維持と疾患の克服を目指した基礎医学研究を進めています。特に神経系と生活習慣病、そしてゲノム科学の3つの分野を中心に研究を進めています。私の役割は、若い研究者が思う存分研究に打ち込める環境を整えること。みんなの雑務を取り除くのが一番の仕事です」
笑いながら語る山中教授の、ALS患者を救いたいとの強い思いは、今もまったく変わらない。認知症の進行を少しでも遅らせる治療法の開発も、自らに新たに課した使命である。


1946年に設置された附置研究所で、神経系、内分泌・代謝、ゲノム、循環器などを中心に人体の恒常性維持機能や、疾患によるその破綻メカニズムに関する基礎医学研究と独自の創薬開発研究に取り組んでいる。研究所名の環境医学とは、「体内環境」を理解しその維持に貢献する医学研究を意味する。様々な臓器やシステムからなる人体を「体内環境」という視点から理解し、疾患の克服に貢献することを目標に研究を進めている。
【取材・文:竹林篤実 撮影:大島拓也】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png