

高齢化の進行に伴い、認知症患者の数は増える一方である。認知症は、ひとたび発症すると治療法がない実に厄介な病だ。今後、深刻な社会問題となりかねない認知症の予防と治療は、現代医学に突きつけられた喫緊の課題である。
その認知症の一つのタイプである「脳小血管病」の分子病態機序の解明に取り組んでいるのが、新潟大学脳研究所の小野寺理教授だ。小野寺教授のグループによる、認知症予防につながる画期的な研究成果は、医学界を代表する雑誌『The New England Journal of Medicine』に掲載された。

語り口は穏やかだが、教授が抱えている研究テーマは、今後の日本社会を左右しかねない重大な問題と密接に関わっている。
厚生労働省の調査によれば、65歳以上の認知症発症者は、2012年の時点で約462万人と推計されている。今後も患者は増え続ける一方であり、2025年には認知症患者が700万人、予備軍ともいえる軽度認知障害患者と合わせて約1300万人に上ると予想されている。
認知症には、アルツハイマー型、脳血管型、レビー小体型、前頭側頭型の4つのタイプがある。認知症全体の約60%はアルツハイマー型であり、これに次いで約20%が脳血管型だ。アルツハイマー型認知症は、脳にアミロイドβやタウと呼ばれるタンパクが溜まり、神経細胞が死滅するために認知機能に障害が起こる。脳血管障害による血管性認知症(脳小血管病)は、脳梗塞などにより血管障害が起こり、アルツハイマー病と同じく神経細胞が死滅して認知症を引き起こす。
「脳小血管病による脳血管性認知症は、本人が気づかないうちに進行しているケースがよくあります。実際、50代の人がMRIを撮ると、半分ぐらいの人に兆しが見られるほどです。ただし、そこから病気が広がる人と広がらない人に分かれるのです。広がる人はやがて脳血管性認知症へと移行していきます。これはゆっくりとではありますが、確実に悪化し、良くなることはまずありません。この病気の初期症状は、頭の回転が少し鈍くなったような感じで、まわりからはただボーッとしているだけのように見えます。いいおじいちゃんと言えないこともありません。しかし、さらに病状が進行すると認知障害を起こしたり、感情をコントロールできなくなったりします」と、小野寺教授は脳血管性認知症の症状を説明する。
4タイプの認知症はいずれも、今のところ発症すると治す手立てのない病である。徐々に進行し、時間を重ねると症状が悪化していくのは、脳血管性認知症もアルツハイマー型も同じである。発症後の治療法を開発し、また発症を防ぐ方法を見つけることが、医学者にとって喫緊の課題となっている。
ところで身体には、リンパ管が張り巡らされている。リンパ管は、免疫機能と排泄機能を担う。リンパ管を通して人は、新陳代謝に伴って排出される老廃物を回収し排泄しているのだ。
ところが不思議なことに、脳にはこれまでリンパ管が見つかっていなかった。というよりもむしろ、脳にはリンパ管のないことが、医学界では当たり前の事実として認識されていたのだ。となると素人発想で一つ疑問が浮かんでくる。仮にリンパ管がないとすれば、脳内の老廃物は、どのようにして排泄されているのか——。この問いと改めて向き合うことで、小野寺教授は研究を進めていった。
「リンパ管の謎を解く答えは、直径10μm程度の脳の小血管にありました。10年ぐらい前からイギリスの学者が唱えていた説で、脳内の排泄物は、小血管のすぐ脇の空間を流れていたのです。小血管の筋細胞が収縮と弛緩を繰り返すことで、血管脇の空間がリンパ管の役目を果たして老廃物などの汲み出し機構を担っている。従って、脳小血管病により血管が傷めば排泄機能が衰え、不要物が脳内に蓄積します。血管が傷む理由については、血管の老化ではないかと推測しています。正確に表現するなら、小血管の筋細胞の老化です。筋細胞が衰えて、血管が収縮しなくなり、血管が血管として機能しなくなるのです」
では、なぜ血管が傷むのか。そのメカニズムを小野寺教授の研究グループは突き止めた。遺伝性脳血管障害の一つに、脳内の白質に伸びる小血管が詰まるために認知症を引き起こす「カラシル(CARASIL)」と呼ばれる病気がある。カラシルの患者から遺伝子を採取して解析した結果、「HTRA1」遺伝子に共通して異常のあることがわかったのだ。
「タンパク質分解酵素であるHTRA1の機能が損なわれると、細胞などを増加させる増殖因子の一つ、トランスフォーミング増殖因子(TGF-β)の分泌量が増加します。これによりTGF-βシグナルが増加し、小血管内に張り付くタンパク質が増えると、小血管の筋細胞が変性します。つまり血管の筋細胞が失われてしまい、血管が収縮しなくなるのです」
この2009年の小野寺グループの研究成果は、『The New England Journal of Medicine(NEJM)』に掲載された。同誌は200年以上の歴史を持つ、医学界のトップジャーナルである。2000年以降、同誌に論文が掲載された日本人が中心のグループははわずかに14グループ、小野寺教授の研究グループはその一つとなった。
脳の小血管が傷んでいくメカニズムは解明された。であれば、そのメカニズムのどこかを打ち破れば、血管障害を止めることができるはずだ。具体的にはTGF-βシグナルの亢進により筋細胞が変性するのだから、これを止めれば良いことになる。すなわち解決策は、TGF-βシグナルの亢進を抑える化学物質を見つけることである。もちろん、それは言うほど簡単な作業ではない。けれども、少なくとも治療、さらには予防への道が開けたことは間違いない。
「脳血管障害は、遺伝性だけではありません。小血管の筋細胞老化が引き起こす障害は、誰にでも起こる可能性があります。そもそも加齢による筋細胞の衰えは、誰にも避けられないことです。けれども、薬により筋細胞の老化を遅らせることができるのなら、病気を予防できたり、発症を遅らせることが期待できます」
2016年5月、小野寺教授の研究グループは、新たな研究成果を発表した。従来、脳小血管病は、人が持っている2つのHTRA1遺伝子の両方が変異した場合(ホモ接合変異)のみ発症すると考えられていた。ところが欧米の先行研究により、遺伝子の1つに変異が起こった場合(ヘテロ接合変異)でも発症することが明らかになった。これを受けて小野寺教授のグループは、日本人の脳小血管病における頻度とその発症メカニズムを解明したのだ。
「70歳未満で重度の脳小血管病を発症した患者さんから同意を得てDNAを採集して調べた結果、5%程度の患者にヘテロ接合変異が見つかりました。これを解析した結果、変異を起こした片方のHTRA1タンパクが、もう一つの正常なHTRA1タンパクの機能を阻害する性質を持つことと、そのメカニズムが明らかになりました」
教授らの研究成果は“Distinct molecular of HTRA1 mutants in manifesting heterozygotes with CARASIL”のタイトルで、2016年5月24日発刊の『NEUROLOGY』誌に掲載された。

日々の地道な研究が、画期的な成果につながる。顕微鏡による緻密な観察は、研究の第一歩だ。
脳内で神経細胞が活動すれば、それだけ血流量が増える。こうした血液の流れの変化を視覚的に捉える装置が、fMRI(functional magnetic resonance imaging)だ。脳内での血流の増加具合がわかれば、脳のどの領域がどのような活動と連動しているかを知ることができる。その血流に関して小野寺教授は、意識の深淵に関わる領域の話をしてくれた。
「たとえば何らかの神経細胞が活動すれば、脳内のある部分で血流が増えます。神経活動の何かを感じて、小血管の筋細胞が弛緩して血流を増やすのです。通常、小血管は収縮していて、必要なときだけ弛緩する。このようなメカニズムに脳が進化した理由は、人の脳があまりに巨大化したからではないかと思います。脳全体が常にフル稼働していたら、脳はオーバーヒートして簡単に壊れてしまうでしょう。だから必要な部分だけを集中して動かすシステムになったのではないでしょうか。その脳を動かすカギを握るのが小血管なのです。小血管はそれほど重要な役割を果たしている臓器ですが、人間の脳の小血管に直接アクセスすることは、現状では不可能です。だから簡単には研究できません。ただし、人の行動や意識、要するに人がどういう存在なのかを理解するためには、小血管の解明を進めることが欠かせないと思います」

ラボ内では、いつでも研究員の相談を聞き、的確なアドバイスを送る。
小野寺教授はほかにも、難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)の発症メカニズム解明に取り組んでいる。ALSは運動神経細胞がなくなるために発症することはわかっているが、その原因は未だ解明されておらず、治療法も開発されていない。
教授らのグループは、まず2008年に新しい遺伝性のALSを発見した。2013年には、ALS同様に運動機能が損なわれる子どもの神経難病「脊髄性筋萎縮症(SMA)」に着目し、SMAの発症メカニズムとALSに共通点があることを突き止めた。その後さらに研究を重ねて、2016年にはALSの新しい発症メカニズムを提唱している。
「ALSは脳の変性疾患で、9割が遺伝と無関係に起こる孤発性です。孤発性ALSでは運動神経細胞が侵されるために、脳の命令が筋肉に伝わらなくなります。ALSの神経細胞では、TDP-43というタンパク質が細胞質内に溜まっていることがわかっていましたが、それがALSを引き起こす原因なのか、ALSによって引き起こされた結果なのかまではわかりませんでした。そんなとき、当科の出張医が勤務している病院から、家族性つまり遺伝性ALSの患者さんの病理診断結果が上がってきました。これを解析すると、孤発性ALSと同様、TDP-43が溜まっている現象が見つかり、この方の遺伝子を検索すると、TDP-43をつくる遺伝子に異常があることがわかりました。この事実は、遺伝性ALSでは、TDP-43をつくる遺伝子の異常がTDP-43の異常な蓄積を引き起こし、それがALSを引き起こしていることを示唆します。すなわち、ALSに共通して見られるTDP-43の異常は、ALSの結果ではなく、ALSを引き起こす原因であったのです。この結果を踏まえて、TDP-43の異常がALSを引き起こす機序のさらなる解明に向けて取り組んでいます」
小野寺教授グループの研究により、正常な運動神経細胞では、TDP-43を作るリボ核酸(RNA)の働きによってTDP-43の量を調節していることが明らかになった。これに対してALS患者では、細胞の核内にTDP-43が存在しないため、TDP-43が足りないものと細胞が誤認してしまい、過剰にTDP-43を作ってしまうのだ。その結果TDP-43が溜まることで細胞死に至る。
小野寺教授らの研究により、TDP-43が過剰につくられるメカニズムが分かってきた。TDP-43をつくるRNAを減らすことができれば、発症や症状の進行を止められるかもしれない。難病ALSが難病でなくなる可能性が見えてきたのだ。
新潟大学脳研究所には、遺族から提供された患者さんの凍結脳標本が、ホルマリンで固定されたものに加えて3万点以上もある。これだけの標本を持つ研究機関は、国内にはまず見当たらない。この標本が、脳研究を支える研究基盤となっている。さらに同研究所には、県内外の病院から脳に関する様々な症例の情報が集まってくる。ALSの例でも、ほかの病院からの病理診断結果が研究を大きく前進させた。なぜ、新潟大学脳研究所には、これほどの標本や病理診断の情報が集まってくるのか。

研究室内には、CTスキャン画像を含む研究所創設時からのカルテがすべて保存されている。
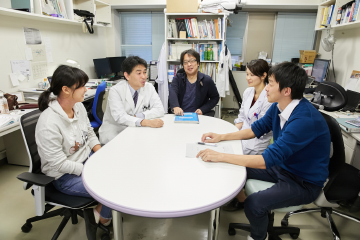
研究についてのディスカッションでは、メンバー全員に意見が求められる。
「脳研究所の特長は、臨床部門があり、実際に患者さんと接することです。要するに研究所に入ってくるメンバーは私も含めて全員が、病気をなんとか治したいと思っている者ばかりです。しかも研究所立ち上げ時から、ここで学んだ医師が新潟県内の各病院に散らばっていて、そこで何かあれば、彼らから直ちに連絡が入ります。資料保存に力を入れているのも脳研究所の特長です。1974年に当時11歳で遺伝病を患っていた患者さんのカルテが、今でも残っています。この方の遺伝子を2001年に採取し、子ども時代のカルテと遺伝子解析の結果を突き合わせて分析することで、病態の経年変化と病名の特定につなげたこともありました」
ALS研究でも、脳研究所に提供された患者の献体組織が活用された。多数の貴重な献体は、県内外に張り巡らされたネットワークがあるからこそ得られたものだ。研究所開設時のテーマは、新潟水俣病だった。地域に根ざした医療の積み重ねが、研究に厚みを与えているのだ。

今後は自らの研究はもとより、後進の育成にも力を注ぎたいと教授は語る。
小野寺教授が脳研究者を目指したきっかけは、助産婦を勤めていた祖母の影響によるものだという。
「私が物心ついたころ、祖母は脳梗塞に侵されていて左半身麻痺の状態でした。その祖母が、医者になれと口癖のように言ってたのです。やがて高校生になると、脳の不思議さに魅力を感じ、脳に関わることをやりたいと考えるようになりました。当時、脳の本格的な研究所は新潟大学を含めて日本に数えるほどしかありません。その頃たまたま手にとった雑誌に、脳研究所の生田先生が書いた文章が載っていました。その文章に感銘を受けたのが、ここを選んだ理由です。脳はまだわからないことだらけで、新しい知見が続々と出てきます。学生時代に習った疾患名など、ほとんどすべてが変わっているほどです。だからこそ、研究には強いやりがいを感じます」
ごく身近にありながら、未だメカニズムの解明されていない脳。その深遠なる世界を解き明かす最先端の研究を、患者と向き合いながら進めていく。研究成果を臨床に活かし、一人でも多くの人を難病から救うために。そんな強い思いが、今日も教授を研究に向かわせている。

『The New England Journal of Medicine』に論文が掲載された研究者だけに与えられる記念のキャップ
1986年、新潟大学医学部医学科卒業、1993年、医学博士。2002年、新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター准教授、2011年より同教授、2016年より現職。2002年ベルツ賞、2008年日本神経学会賞。2009年に発表した論文「HTRA1の変異と家族性の虚血性脳小血管障害との関連」はNEJM誌に掲載された。

日本で最初に設置された脳神経に関する国立大学附置研究所であり、脳機能の解明と脳疾患の克服を目指している。発端は1938年に発足した「新潟神経学研究会」に遡り、1957年には新潟大学医学部附属脳外科研究施設として設置された。1967年、大学附置研究所への昇格が認められ、新潟大学脳研究所の誕生となる。最近では特に、興奮性アミノ酸受容体の構造と機能、脳特異タンパク及び遺伝性神経疾患の病態に関する研究において、先駆的な業績を挙げている。
【取材・文:竹林篤実/撮影:カケマコト】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png