
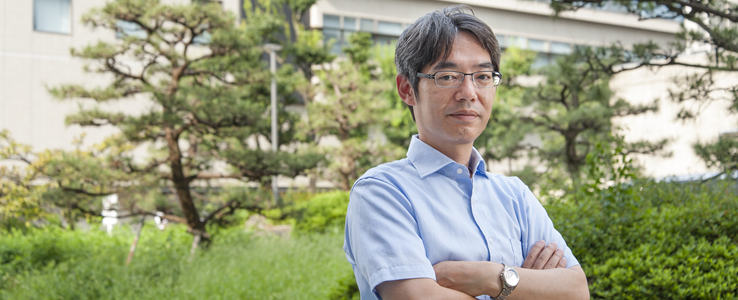
人間の体を病原体から守ってくれる「免疫機構」。近年、分子生物学の発展と歩調を合わせ、そのメカニズムの解明が進みつつある。京都大学ウイルス研究所の竹内理教授は、なかでも自然免疫が起こす“炎症”の仕組みに注目。二つのRNA(リボ核酸)に結合するタンパク質が、それぞれ異なるタイミングで「炎症のブレーキ」の役割を果たしていることを突き止めた。画期的な創薬や治療の開発にもつながる免疫研究の、最前線について伺った。
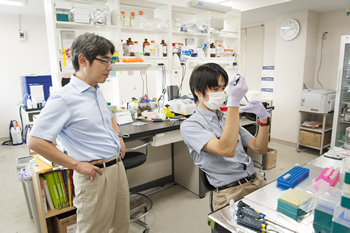
研究員たちと日々実験を繰り返す研究室で。2014年には博士研究員の一人が「第21回東アジアシンポジウム」に参加し,「Outstanding Young Scientist 1st Place TOMY Award」を受賞、また別の一人が同年の日本免疫学会でベストプレゼンテーション賞を受賞するなどの活躍を見せた。
京都大学ウイルス研究所の竹内理教授の研究テーマは、「自然免疫システムの機構解明」である。
自然免疫とは、生物が病原体に感染したとき、いちばん初めにそれを「敵」と認識して排除するシステムのことをいう。生物が持っている、もっとも基本的な防御システムだ。
免疫にはもう一つ「獲得免疫」と呼ばれるものもある。はしかや水疱瘡などの病気は、一度かかれば、基本的に同じ病気に感染することはない。それは人体に、感染したウイルスなどの病原体の特徴を記憶し、次からは効率的にそれを殺す仕組みが備わっているためである。
自然免疫と同様の防御機構は、昆虫やカブトガニなどの下等生物にも備わっているが、獲得免疫を持つ生物は脊椎動物以上に限られる。そのため、長年、免疫学者の間では、獲得免疫より自然免疫のほうが“下等”なシステムであると考えられてきた。
しかし2000年代に入ってから、獲得免疫が正常に機能する上で、自然免疫が非常に重要な役割を果たしていることが解明された。自然免疫と獲得免疫は、いわば車の両輪のように相互を補完しながら、どちらも高等生物の生存にとって欠かせない「バリア」となっていることがわかったのだ。これは、大阪大学・微生物病研究所・審良(あきら)静男教授らの研究グループによる成果で、竹内教授も一員としてこの研究に参加していた。
竹内教授がいま注目し、研究の中心テーマとしているのが、「自然免疫における“炎症”の制御機構」である。
炎症といえば、病気にかかったときに発熱したり、皮膚炎などにかかったときに、傷口が化膿して赤く腫れ上がる様子をイメージする。その他にも炎症は痛みを発生させるなど、不快な症状を起こすがゆえに、治療においては抗生物質や消炎剤で抑えることも多い。しかし炎症の実体は、病気や感染症の原因であるウイルスや細菌を殺すため、免疫機構が起こす極めて重要な防御反応である。
「炎症反応において中心的な役割を担っているのが、“マクロファージ”と呼ばれる細胞です。マクロファージは“貪食細胞”とも呼ばれ、生体内に入ってきた病原体などの異物を、自らの中に取り込んで殺す役割を果たしています。またそれと同時に、病原体が侵入したことを他の細胞に知らせる“警報装置”としての機能も持っています」
マクロファージの表面には、「トル様受容体」と呼ばれる突起が備わっており、これが病原体のRNA(リボ核酸)やDNA(デオキシリボ核酸)、糖脂質などの構造を認識する。感染を認識したマクロファージは、周囲の細胞に情報を伝達するため、「サイトカイン」と呼ばれるタンパク質を放出する。
サイトカインには、TNF、IL1、IL6など、複数の種類が存在する。これらが血流に乗って周囲の細胞に広がっていくことで、病原体を捕食するリンパ球などを引き寄せ、造血作用を亢進し、発熱を促すなど、ドミノ倒しのように次々と炎症反応を起こしていく、という仕組みだ。

研究室には細胞を計測するフローサイトメーター、リアルタイムPCR装置など、さまざまな分析機器、顕微鏡が所狭しと並ぶ。
炎症反応というのは、ミクロの目で見れば、病原体に侵された細胞が分解され、修復されていくプロセスと言える。そのため、もし病原体に感染しても炎症が起こらなければ、その生物はやがて多くの細胞が病原体に侵食され、死に至ることになる。
しかし一方で、病原体に免疫機構が過剰に反応し、必要以上の炎症を引き起こせば、逆にそれが原因で健康が損なわれたり、生命の危機に陥ることがある。いわゆる「自己免疫性疾患」と呼ばれる病気が、そうした免疫システムの過剰反応によって引き起こされる病である。
「そのため生物内には、炎症を極めて精密に制御する仕組みが備わっています。最近では、動脈硬化や肥満による糖尿病、メタボリックシンドロームなどがこの免疫システムの不調による血管の慢性的な炎症が要因で起こっているとも言われており、免疫反応の制御機構の解明は、数多くの病気の治療に役立つと期待されているのです」
竹内教授が現在研究の中心テーマとするのは、この免疫機構の「伝達物質」であるサイトカインの放出と抑制が、どういう仕組みでコントロールされているのかの解明だ。
「サイトカインが放出されるプロセスは、かなり明らかにされつつありますが、抑制、すなわちブレーキのほうの仕組みはあまりわかっていませんでした。そこで我々が注目したのが、サイトカイン放出の引き金である“mRNA”(メッセンジャーRNA)です」
生物の細胞内でタンパク質がつくられる際、mRNAが重要な役割を果たす。核の中にあるDNAの情報がmRNAによって“翻訳”され、その情報にもとづいてタンパク質がつくられ、細胞外部に放出される。つまり細胞内にmRNAがなければ、タンパク質であるサイトカインが合成されることはない。
「そのmRNAを分解する役割を担っているのが、“レグネース1(Reganse-1)”と“ローキン(Roquin)”という2種類のタンパク質です。レグネース1とローキンは、それぞれが役割を終えたmRNAを分解することで、サイトカインの必要量以上の放出を抑制しているのです。我々は、このレグネース1とローキンが、細胞内のどこで、どのタイミングでそれぞれ働いているか、実験によって明らかにしました」
また竹内教授らは、レグネース1とローキンが、二つとも同じmRNAのある特殊な構造(“ステムループ構造”と呼ばれる)を目印にして、標的を見つけていることも解明した。二つのタンパク質は、対象の認識方法も、分解という機能も同じだが、その機能する場所、時期が違うことで、巧妙に炎症をストップさせていたのだ。
「自動車にフットブレーキと、サイドブレーキがあるのと同じです。レグネース1が走っている車を止めるフットブレーキの役割、ローキンは駐車中の車が動き出さないようにするサイドブレーキのイメージです」
「さらに別のわかりやすい例をあげるなら、レグネース1とローキンは、スーパーの店頭で働いている人か、問屋で働いている人の違いのような感じでしょうか。どちらの人も、食料品の在庫を管理する仕事をしています。それぞれの人が、お互いの場所で目を光らせているから、腐った食べ物が店頭に並んだり、必要以上の量の野菜が出荷されないようになっているわけです。同様に人体の中でも、レグネース1とローキンが、違う場所とタイミングでRNAを分解することで、過剰な免疫応答が抑制されているといえるでしょう」
実際に、レグネース1とローキンをノックアウトしたマウスは、生まれてからすぐに自己免疫性疾患を発症し、内臓に腫瘍ができて死亡することもわかっている。
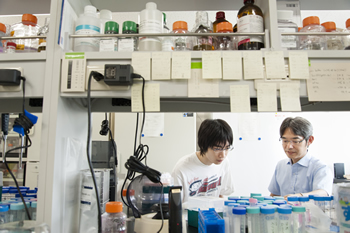
免疫不全症や、自己免疫疾患には、未だに原因がよくわからない病気がたくさんあるという。「炎症のメカニズムを解明することで、そうした病気の治療や予防に少しでも貢献できれば、研究者としてそれ以上の喜びはない」と竹内教授は言う。研究室に所属する学生たちも同じ思いだ。
「炎症の早期、後期でそれぞれのタンパク質が果たす役割がさらに判明してくれば、炎症性疾患の病態の解明や、新たな治療法の開発にもつながっていくのではないか、と考えています。またレグネース1とローキンは、マクロファージなどの自然免疫を担当する細胞だけでなく、獲得免疫において病原体を殺す役割を担う“T細胞”の活性化にも関与しています。二つのタンパク質の働きがもっと解明されることで、免疫機構がトータルに見えてくるはずです」
加えて竹内教授は今後、レグネース1とローキンのほかにも、RNAを分解する酵素の研究を視野に入れる。その中には、外部から侵入したウイルスのRNAを分解していると思われるものもあり、免疫機構全体を解明する上でも、重要な研究テーマとなることは確実だ。
竹内教授は福井県に生まれ、高校卒業後、大阪大学医学部に進学、後の大阪大学総長、岸本忠三教授のもとで免疫学を学んだことが、この研究の道に入るきっかけとなった。岸本教授は、サイトカインの一種であるIL6を発見し、関節リューマチの特効薬の開発に多大な貢献をした人物だ。竹内教授は大学を卒業後、研修医として内科勤務を経て、免疫学の世界的権威として知られる大阪大学の審良静男教授の研究室に入った。それが、今に至る道を決定づけた。
「1999年、ヒトには10種類のトル様受容体があることが発見され、どんな機能を果たしているのか、世界中で研究が始まっていました。私もそこで初めて論文を発表し、それぞれのトル様受容体が、どういう機能を持つかについてまとめました」
研究をしていて何より面白いのは、「世界で他の誰も知らないことがわかったとき」だと竹内教授。「重箱の隅をつつくようなテーマではなく、免疫システムの中枢を明らかにするような研究に取り組んでいきたいと思っています。それはとても難しいことでもありますが(笑)」と抱負を語る。
21世紀に入ってから、各種の計測・分析技術の発展により、免疫学は急激な進歩を続けており、世界各国の研究競争も年を追うごとに熾烈さの度合いを増している。その先端を走る竹内教授の研究からは、今後も目が離せない。
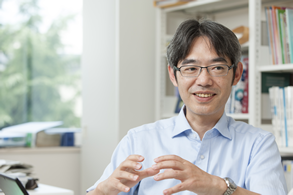

1956年、「ウイルスの探究並びにウイルス病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究」を目的に設立。細胞内の遺伝子・蛋白質合成システム、ウイルス複製を抑えるインターフェロンの発現誘導システム、病原体からの防御反応を支える血球免疫システムなどの分野で多くの成果をあげる。ヒトの発がんレトロウイルスとして世界で初めて、日本に100万人以上の感染者がいる HTLV を見い出すなど、先駆的な研究を行う。
http://www.virus.kyoto-u.ac.jp
【取材・文:大越裕/撮影:楠本涼】
 bana1.png (300px×80px)
bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)
bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png
NovelPrize2015.png